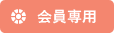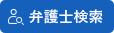貧困問題(貧困問題対策本部)
活動の概要
貧困と格差が拡大する現状に立ち向かうべく、日弁連は2010年4月に貧困問題対策本部を設置し、活動を進めています。
本部内には①セーフティネット部会、②ワーキングプア部会、③女性と子どもの貧困部会のほか、自殺対策プロジェクトチームや社会保障基本法起草プロジェクトチームなどのPTが設置され、多様化する各課題に取り組んでいます。
2022年4月以降、組織体制をさらに強化し、貧困に関わる人権侵害を社会から根絶するために必要な対応策の提言や調査研究、そして対外的諸活動のため、労働・生活保護相談体制の強化や最低賃金の引上げ、雇用保険制度等の改善、複雑化する子どもの貧困対策、女性やひとり親の貧困問題への調査提言、自殺対策の推進などの重点項目を中心として、貧困をなくし未来に希望を抱くことのできる社会の実現のための取組を進めています。
 社会保障基本法起草に関する活動(社会保障基本法起草プロジェクトチーム)
社会保障基本法起草に関する活動(社会保障基本法起草プロジェクトチーム)
詳しい活動内容や最新の情報
1 各地の弁護士会・市民団体等との連携や体制の強化
(1)各弁護士会との連携強化
全国各地の弁護士会で貧困問題に対応する組織が設置されたことを受け、後記キャラバンや全国協議会等のさまざまな機会を通じ、連携の強化を図ります。
(2)貧困問題対策全国キャラバン
日弁連の取組を広く市民の皆様に知っていただくとともに、全国の弁護士会や各地で活動する団体等との連携を強めるため、「貧困問題全国キャラバン」による市民集会を毎年開催しています。近年はオンラインやハイブリッドでの開催も盛んです。
(3)貧困問題対策全国協議会の開催
各地の貧困問題への取組について、全国的に情報を共有し、意見交換を行うために各弁護士会の担当者による全国協議会を、2010年以降毎年開催しています。
2 相談体制の構築
(1)各地での相談体制の構築
労働と生活に関する総合相談や生活保護に関する相談体制を各地で構築するためのマニュアルを作成・配布したり、法律扶助制度の活用や各地の実践例など有益な情報等についてもさまざまな機会を通じて共有し、各地での相談体制の構築に役立てています。
(2)時宜にかなったホットラインの実施
毎年12月の生活保護ホットラインや毎年3月・9月の暮らしとこころの相談会など、全国一斉での電話相談会(ホットライン)を開催したり、雇用保険、児童扶養手当など特定のテーマに関する電話相談会を適宜開催するなど具体的対応を行うとともに、各種相談会で得た情報等を各地に共有し、相談体制の充実に努めています。
3 人権擁護大会決議
これまで数々の人権擁護大会シンポジウムを当本部が中心となって成功させ、以下の人権擁護大会決議を採決・公表しました。
これまでに作成した人権擁護大会シンポジウムの基調報告書や資料集は こちらをご参照ください。
こちらをご参照ください。
- 「生活保障法」の制定等により、すべての人の生存権が保障され、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める決議(2024年)
- 地方自治の充実により地域を再生し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める決議(2021年)
- 若者が未来に希望を抱くことができる社会の実現を求める決議(2018年)
- 全ての女性が貧困から解放され、性別により不利益を受けることなく働き生活できる労働条件、労働環境の整備を求める決議(2015年)
- 貧困と格差が拡大する不平等社会の克服を目指す決議(2013年)
- 強いられた死のない社会をめざし、実効性のある自殺防止対策を求める決議(2012年)
- 希望社会の実現のため、社会保障のグランドデザイン策定を求める決議(2011年)
- 貧困の連鎖を断ち切り、すべての子どもの生きる権利、成長し発達する権利の実現を求める決議(2010年)
- 貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議(2008年)
- 貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の尊厳に値する生存を実現することを求める決議(2006年)