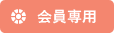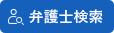死刑制度の問題(死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部)
日弁連は、2002年11月22日に「 死刑制度問題に関する提言」を発表し、また、2004年10月8日に第47回人権擁護大会で「
死刑制度問題に関する提言」を発表し、また、2004年10月8日に第47回人権擁護大会で「 死刑執行停止法の制定、死刑制度に関する情報の公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議」を採択しました。 さらに、2011年10月7日の第54回人権擁護大会では、「
死刑執行停止法の制定、死刑制度に関する情報の公開及び死刑問題調査会の設置を求める決議」を採択しました。 さらに、2011年10月7日の第54回人権擁護大会では、「 罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択しています。
罪を犯した人の社会復帰のための施策の確立を求め、死刑廃止についての全社会的議論を呼びかける宣言」を採択しています。
この提言・決議の内容を実現するため、前身である「日弁連死刑執行停止法制定等提言・決議実現委員会」の活動を引き継ぎ、「死刑廃止検討委員会」を設置し、上記「提言」と「決議」の実行のため、以下のような活動を行いました。そして、2016年10月7日の第59回人権擁護大会では、「 死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択しています。
死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択しています。
この宣言を受け、これまでの死刑廃止検討委員会の活動を引き継ぎ、宣言の実現に向けて、2017年6月に「死刑廃止及び関連する刑罰制度改革実現本部」となりました。