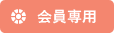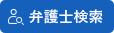公害・環境問題(公害対策・環境保全委員会)
活動の概要
日弁連は、公害による深刻な生命・身体被害を人権問題と位置づけ、当初、人権擁護委員会の中に「公害問題対策特別委員会」を設置して取り組んでいましたが、1969年5月に独立した組織として「公害対策委員会」を発足させました。その後、1985年に現在の「公害対策・環境保全委員会」に改称し、国・自治体の環境政策を前進させ、公害被害の救済、環境破壊の防止を図るために、調査研究活動をはじめ、これに基づく意見書等の作成、シンポジウムの開催、書籍の出版等の活動を行っています。
活動紹介
公害対策・環境保全委員会は、現在7つの部会および複数のプロジェクトチームから構成され、多様化する公害・環境問題に取り組んでいます。
各部会、プロジェクトチームの活動紹介
環境法部会
環境法部会では、環境法制度に通じる一般的な問題に取り組んでおり、特定の具体的な分野・テーマごとに活動する他部会と異なる活動を行っています。現在は、環境権、環境問題に関する情報へのアクセス・意思決定への市民参加・司法へのアクセスを定めたオーフス条約やエスカス協定などの内容の日本国内における実現、動物関連法の改正などに取り組むとともに、環境法教育として、法科大学院生等を対象とした環境法サマースクール・環境法フィールドワークを実施しています。
廃棄物部会
廃棄物部会では、これまで廃棄物の発生抑制や適正処理・循環利用等の問題に関する調査・研究や意見書の作成に取り組んできました。近年では、2011年の福島第一原発事故により発生した放射能汚染廃棄物についてのあるべき法制度の在り方の提言や、海洋プラスチック問題に関してプラスチック資源循環政策に関する提言、建設発生土およびその盛土等の問題についての政策に関する提言などを行っているところです。今後もこれらの問題を含む廃棄物の問題について、更なる調査や研究を進めていきます。
大気・都市環境部会
大気・都市環境部会では、大気汚染、騒音、低周波、振動、まちづくり(都市計画)、歴史的建造物の保存、建築紛争、交通政策、デジタル社会における地域の在り方と自治体の役割などに関わる問題を取り扱っています。誰もが良好な環境のもと、快適で心豊かに住み続ける権利を有することを確認し、持続可能な都市の実現のために現行の都市計画・建築法制を抜本的に改め、土地利用、建築、都市交通、景観などについての、統合的な都市法制を整備することを求めています。 主な意見書・会長声明等としましては、 建設アスベスト損害賠償請求訴訟最高裁判所判決に関する会長談話(2021年5月21日)、
建設アスベスト損害賠償請求訴訟最高裁判所判決に関する会長談話(2021年5月21日)、 持続可能な都市を実現するための高経年マンション再生に関する意見書 (2023年3月16日)、第63回人権擁護大会における
持続可能な都市を実現するための高経年マンション再生に関する意見書 (2023年3月16日)、第63回人権擁護大会における 地方自治の充実により地域を再生し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める決議(2021年10月15日)などがありますので、ご覧ください。
地方自治の充実により地域を再生し、誰もが安心して暮らせる社会の実現を求める決議(2021年10月15日)などがありますので、ご覧ください。
水部会
水部会では、河川や、湖沼などの湿地、干潟や沿岸域など、水に関わる環境問題について、調査・研究を行っています。
当連合会作成の「 湿地の保全及び再生等に関する法律要綱案」を踏まえ、「
湿地の保全及び再生等に関する法律要綱案」を踏まえ、「 重要な湿地の保全・再生へ向けた適正な管理を行うための法制度の創設等を求める意見書」(2023年5月12日)を公表しました。
重要な湿地の保全・再生へ向けた適正な管理を行うための法制度の創設等を求める意見書」(2023年5月12日)を公表しました。
また、毎年のように発生する豪雨災害等を踏まえ、環境保護の観点に加えて治水の観点から従来の安易なダム建設に反対し、あるべき流域治水のあり方について調査・研究を行っています。
自然保護部会
自然保護部会では、自然環境の保全および自然資源の持続可能な形での利用について国内外の法制度、地方自治体の取組みなどについて調査・研究を進めています。2017年第61回人権擁護大会では「 生物多様性の保全と持続可能な自律した地域社会の実現を求める決議」(2017年10月6日)が採択され、この実現に向けた活動をしています。
生物多様性の保全と持続可能な自律した地域社会の実現を求める決議」(2017年10月6日)が採択され、この実現に向けた活動をしています。
また、これまでの開発による環境破壊の問題に加え、近年では観光客の急激な増加に伴うオーバーツーリズムの問題、過疎化が進んでいく中で地方の自然が荒廃していく問題、大規模太陽光発電設備および大規模風力発電設備の設置に伴う環境破壊の問題など、新たな問題が生じており、これらの問題についても調査・研究を行っています。
エネルギー・原子力部会
エネルギー・原子力部会では、国のエネルギー政策や原子力政策の問題等について、調査・研究を行い、意見を発表しています。2011年3月、福島第一原子力発電所で発生した事故では、大量の放射能を環境中に放出し、甚大な被害を与えています。当部会では、二度とこのような原子力災害を起こさせないよう、2013年、2014年、2015年の人権擁護大会において福島第一原発事故に関するシンポジウムを開催し、2022年の人権擁護大会においては「 第64回人権擁護大会シンポジウム第1分科会「高レベル放射性廃棄物問題から考える脱原発~原発に頼らない、地域社会と日本のエネルギー自立~」をテーマとしたシンポジウムを開催して、重要な決議・宣言をとりまとめました。 また、各種意見書を発表するなど、脱原発に向けた取組みを行っています。最近発表した主な意見書等としましては、「
第64回人権擁護大会シンポジウム第1分科会「高レベル放射性廃棄物問題から考える脱原発~原発に頼らない、地域社会と日本のエネルギー自立~」をテーマとしたシンポジウムを開催して、重要な決議・宣言をとりまとめました。 また、各種意見書を発表するなど、脱原発に向けた取組みを行っています。最近発表した主な意見書等としましては、「 福島第一原子力発電所事故により発生した汚染水等の処理について海洋への放出に反対する意見書」(2022年1月20日)、第64回人権擁護大会における「
福島第一原子力発電所事故により発生した汚染水等の処理について海洋への放出に反対する意見書」(2022年1月20日)、第64回人権擁護大会における「 高レベル放射性廃棄物の地層処分方針を見直し、将来世代に対し責任を持てる持続可能な社会の実現を求める決議」(2022年9月30日)・基調報告書、「
高レベル放射性廃棄物の地層処分方針を見直し、将来世代に対し責任を持てる持続可能な社会の実現を求める決議」(2022年9月30日)・基調報告書、「 脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案についての会長声明」などがありますので、ご覧ください。
脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律案についての会長声明」などがありますので、ご覧ください。
化学物質・食品安全部会
化学物質・食品安全部会では、化学物質の健康影響および食の安全の問題に関する調査・研究を行っています。近時では、「 ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書 」(2017年12月21日)、「
ネオニコチノイド系農薬の使用禁止に関する意見書 」(2017年12月21日)、「 海洋プラスチック問題に対する意見書」(2018年12月20日)、「
海洋プラスチック問題に対する意見書」(2018年12月20日)、「 今後のプラスチック資源循環政策についての意見書」(2021年3月18日)等を公表しました。また、2023年2月13日にシンポジウム「香害問題を考える」を開催し、香りによる不快や体調不良を訴える人がいる問題(香害)にも取り組んでおります。この他、改正農薬取締法における農薬再評価制度の問題点や、PFAS(PFOS・PFOAなどの人体に有害な有機フッ素化合物)が全国各地で高濃度で検出されている問題などについて、調査・研究を行っております。
今後のプラスチック資源循環政策についての意見書」(2021年3月18日)等を公表しました。また、2023年2月13日にシンポジウム「香害問題を考える」を開催し、香りによる不快や体調不良を訴える人がいる問題(香害)にも取り組んでおります。この他、改正農薬取締法における農薬再評価制度の問題点や、PFAS(PFOS・PFOAなどの人体に有害な有機フッ素化合物)が全国各地で高濃度で検出されている問題などについて、調査・研究を行っております。
気候変動対策プロジェクトチーム
当プロジェクトチームでは、気候変動問題について国内外の最新の動向を調査・研究し、日本がとるべき対策やあるべき制度を検討しています。
具体的な活動としては、2022年11月には、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)第27回締約国会議(COP27)へ委員を派遣し、各国の弁護士との知見共有、協議にも積極的に取り組んでいます。また、2023年3月には気候変動訴訟に関する欧州調査を実施し、イギリス、オランダ、ベルギー等の気候変動訴訟の現状を視察しました。これら現地視察等の活動や、世界の気候変動訴訟に関する調査・研究を踏まえ、日本における気候変動対策の推進のために、検討を行っております。
近時では、2023年3月3日付けで「 GX実現に向けた基本方針及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案についての会長声明 」を公表しています。声明では、当連合会がこれまで表明してきた危険な気候変動を回避し、地球規模および日本における持続可能な経済社会の構築を進める観点から、GX法案の根本的な見直しを求めています。
GX実現に向けた基本方針及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律案についての会長声明 」を公表しています。声明では、当連合会がこれまで表明してきた危険な気候変動を回避し、地球規模および日本における持続可能な経済社会の構築を進める観点から、GX法案の根本的な見直しを求めています。
リニア新幹線問題に関するプロジェクトチーム
当プロジェクトチームは、JR東海のリニア中央新幹線計画の工事実施計画認可に先立ち、2014年3月に発足し、同年6月、自然環境等の各種懸念が解消されるまで認可すべきではないという意見書( リニア中央新幹線計画につき慎重な再検討を求める意見書)を取りまとめ、公表しました。その後、工事が進行する中で地下水保全や残土処分、工事による生活環境の悪化など、意見書で指摘した問題が現実化しています。当プロジェクトチームでは、意見書公表から5年後の2019年、南アルプストンネルの現場で大量の残土が発生する長野県大鹿村と自然由来のヒ素・フッ素等を含有した残土の処分が問題となっている愛知県春日井市を調査し、「リニア新幹線工事の現状と課題~日弁連意見書の公表から5年を経過して」を開催しました。また、2022年11月には再び長野県大鹿村にて前回から3年経過後の状況を視察、2023年8月には、絶滅危惧種であるハナノキの群生地で、その他の希少野生動植物も多く生息生育している湿地が残土の処分先候補となっている岐阜県御嵩町美佐野を視察しました。コロナ禍を経て人流も大きく変化した今、改めて、リニア計画を見直す必要があるのではないか、引き続き検討を続けております。
リニア中央新幹線計画につき慎重な再検討を求める意見書)を取りまとめ、公表しました。その後、工事が進行する中で地下水保全や残土処分、工事による生活環境の悪化など、意見書で指摘した問題が現実化しています。当プロジェクトチームでは、意見書公表から5年後の2019年、南アルプストンネルの現場で大量の残土が発生する長野県大鹿村と自然由来のヒ素・フッ素等を含有した残土の処分が問題となっている愛知県春日井市を調査し、「リニア新幹線工事の現状と課題~日弁連意見書の公表から5年を経過して」を開催しました。また、2022年11月には再び長野県大鹿村にて前回から3年経過後の状況を視察、2023年8月には、絶滅危惧種であるハナノキの群生地で、その他の希少野生動植物も多く生息生育している湿地が残土の処分先候補となっている岐阜県御嵩町美佐野を視察しました。コロナ禍を経て人流も大きく変化した今、改めて、リニア計画を見直す必要があるのではないか、引き続き検討を続けております。
空き家問題・地域再生に関する政策提言検討プロジェクトチーム
当プロジェクトチームは、人口減少時代における地方自治・地域再生の在り方、都市計画・都市政策の在り方を含めた空き家対策についての政策提言、地方自治・地域再生に密接に関連する地方自治体のデジタル化・地方自治体情報システムの標準化、高経年マンションの対応策をどうするかといった問題について、調査・検討を続けております。主な意見書等としましては、 自治体戦略2040構想研究会第二次報告及び第32次地方制度調査会での審議についての意見書(2018年10月24日)、
自治体戦略2040構想研究会第二次報告及び第32次地方制度調査会での審議についての意見書(2018年10月24日)、 第32次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書(2020年3月18日)、
第32次地方制度調査会で審議中の圏域に関する制度についての意見書(2020年3月18日)、 「地方公共団体の広域連携」に係る第32次地方制度調査会 答申に対する会長声明(2020年6月26日)を公表しているほか、シンポジウム「
「地方公共団体の広域連携」に係る第32次地方制度調査会 答申に対する会長声明(2020年6月26日)を公表しているほか、シンポジウム「![]() 人口減少時代の地方公共団体のあり方を考える~多様性と自主性を尊重した広域連携を目指して~ (PDFファイル;7.6MB)」(2021年1月26日)、シンポジウム「
人口減少時代の地方公共団体のあり方を考える~多様性と自主性を尊重した広域連携を目指して~ (PDFファイル;7.6MB)」(2021年1月26日)、シンポジウム「 デジタル共通基盤の構築と自治体への影響」(2021年9月9日)、シンポジウム「
デジタル共通基盤の構築と自治体への影響」(2021年9月9日)、シンポジウム「 デジタル社会における地域のあり方と自治体の役割」(2022年12月22日)を開催していますので、ご覧ください。
デジタル社会における地域のあり方と自治体の役割」(2022年12月22日)を開催していますので、ご覧ください。
福島原発被害回復プロジェクトチーム
当連合会は2013年第56回人権擁護大会において、既存の原子力発電所を、できる限り速やかに、全て廃止する旨や、福島第一原発事故の被害を完全回復すること等を決議しました( 福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議)。エネルギー・原子力部会では脱原発等の取組を進めており、当プロジェクトチームでは被害の完全回復に向けて意見書や会長声明等を発出しています。最近のものでは2022年3月28日付け「
福島第一原子力発電所事故被害の完全救済及び脱原発を求める決議)。エネルギー・原子力部会では脱原発等の取組を進めており、当プロジェクトチームでは被害の完全回復に向けて意見書や会長声明等を発出しています。最近のものでは2022年3月28日付け「 福島第一原発事故損害賠償請求集団訴訟についての最高裁決定を受け、改めて国に対し、原子力損害賠償に係る中間指針等の見直しを求める会長談話」などが挙げられます。
福島第一原発事故損害賠償請求集団訴訟についての最高裁決定を受け、改めて国に対し、原子力損害賠償に係る中間指針等の見直しを求める会長談話」などが挙げられます。
また、子ども・被災者支援法の内容をより具体化すべく、同法の改正に向けた意見も検討中です。
アイヌ民族権利保障プロジェクトチーム
当プロジェクトチームでは、北海道等の先住民族であるアイヌ民族の権利が保障されることを目指して活動しています。知里幸恵さん没後100周年に当たる2022年に、彼女が人生の大半を過ごした北海道旭川市で開催された第64回人権擁護大会では、「 アイヌ民族の権利の保障を求める決議」が採択されました。今後も当プロジェクトチームでは、決議内容を実現するため、法改正・法制定に向けた働きかけや、決議内容の更なる具体化に向けた研究などを進めていきます。
アイヌ民族の権利の保障を求める決議」が採択されました。今後も当プロジェクトチームでは、決議内容を実現するため、法改正・法制定に向けた働きかけや、決議内容の更なる具体化に向けた研究などを進めていきます。
メガソーラー問題検討プロジェクトチーム
当プロジェクトチームは、メガソーラーや大規模風力発電所の建設に伴い、自然環境や生活環境の著しい破壊等の問題を生じさせる事例が増加しており、そのような問題発生への懸念によって、再生可能エネルギーの推進にも影響が生じかねない状況にあることを踏まえ、当該問題への対応を検討するために発足しました。
プロジェクトチームの活動としては、①森林法、FIT法、環境アセス法などの再エネ発電所の設置に関わる現行法の問題点、②エネルギー自治の観点による再エネ発電のあり方、③再エネ発電所の設置に伴う著しい開発行為に対処するための、条例による適正な規制やゾーニング実施の在り方などの検討を行っております。上記検討に基づき、「 メガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境と景観破壊及び生活環境への被害を防止するために、法改正等と条例による対応を求める意見書」(2022年11月16日)を公表したほか、シンポジウム「
メガソーラー及び大規模風力発電所の建設に伴う、災害の発生、自然環境と景観破壊及び生活環境への被害を防止するために、法改正等と条例による対応を求める意見書」(2022年11月16日)を公表したほか、シンポジウム「 メガソーラー及びメガ風力が自然環境及び地域に及ぼす影響と対策~再生可能エネルギーと自然環境及び地域の生活環境との両立を目指して~」(2022年12月5日)およびシンポジウム「
メガソーラー及びメガ風力が自然環境及び地域に及ぼす影響と対策~再生可能エネルギーと自然環境及び地域の生活環境との両立を目指して~」(2022年12月5日)およびシンポジウム「 メガソーラー及び大規模風力による開発規制条例の実効性確保~地域の自然環境及び生活環境を守るための処方箋~」 (2023年9月16日)を開催しました。
メガソーラー及び大規模風力による開発規制条例の実効性確保~地域の自然環境及び生活環境を守るための処方箋~」 (2023年9月16日)を開催しました。
水俣病問題検討プロジェクトチーム
公害対策・環境保全委員会と人権擁護委員会は、水俣病に関する人権救済申立てが日弁連になされたのを機に、共同で「水俣病問題検討プロジェクトチーム」を立ち上げ、「公害の原点」と言われる水俣病の被害者の方々の幅広い救済を求めるための調査・検討を行っています。当初は、水俣病特別措置法の問題点等を重点的に取り上げ、近時は、水俣病認定審査業務を、最高裁2013年4月16日付け義務づけ訴訟判決の趣旨に沿ったものに改善するように求める活動を行っています。
最近の発行物
日弁連公害対策・環境保全委員会50周年記念誌
「公害対策・環境保全委員会 2030年への環境弁護士の挑戦」
公害対策・環境保全委員会は、2019年5月に設立50周年を迎えました。これを記念して、環境問題の解決に向けた展望を記した書籍を作成しました。詳しくは ![]() こちら (PDFファイル;9.6MB)をご覧ください。
こちら (PDFファイル;9.6MB)をご覧ください。
※日弁連では本出版物の一般配布・販売等は行っておりません。
2010年版弁護士白書 特集1
「そしていのちを守る戦いは続く~公害・環境問題における40年の軌跡と将来戦略」
公害対策・環境保全委員会は、2009年5月に設立40周年を迎えました。委員会では、記念シンポジウムの開催とともに、40年にわたる委員会活動の軌跡と将来への展望を「2010年版弁護士白書」の特集として掲載しました。詳しくは ![]() こちら (PDFファイル;2.6MB)をご覧ください。
こちら (PDFファイル;2.6MB)をご覧ください。
公害対策・環境保全委員会編『公害・環境訴訟と弁護士の挑戦』
(法律文化社/2010年10月5日発行)
本書では、四日市公害訴訟、熊本水俣病訴訟など、実際に訴訟に取り組んだ弁護士が、「なぜ訴訟をおこすのか」「訴訟で何を求め、困難をどうのりこえたか」「法廷外の活動にどのように取り組んだのか」などの訴訟の経緯や争点、課題を詳述しています。
公害対策・環境保全委員会では、次の世代を担う皆さんに、教科書や判例集には載っていない具体的な取り組みを知っていただくために、編者として本出版に携わりました。
※日弁連では本出版物の販売等は行っておりませんので、購入に関するご質問等については法律文化社にお問合せください。
日弁連公害・環境ニュース
公害対策・環境保全委員会では、年に数回「日弁連公害対策・環境保全委員会ニュース」を発行し、委員会の活動について紹介しています。
最新号 公害・環境ニュース78号
<CONTENTS>
- 第66回人権擁護大会シンポジウム第3分科会開催へ
- シンポジウム「メガソーラー及び大規模風力による開発規制条例の実効性確保~地域の自然環境及び生活環境を守るための処方箋~」の開催報告と、ブックレットの出版案内
- 第14回環境法サマースクール報告
- 「神宮外苑地区第一種市街地再開発事業」に対する東京都環境影響評価条例の適用に関する会長声明
- シンポジウム「持続可能な都市環境形成・まちづくりとデジタル化」の報告
- リニアの残土処分・湿地保全に関する会長声明
- 高レベル放射性廃棄物の処分、廃炉等に関するドイツ・スイス調査報告
- 【最新号】公害・環境ニュース第78号はこちら (PDFファイル;1.6MB)