再審についてのQ&A
Q1 なぜ一回終わった裁判をやり直す必要があるの?
- Answer
-
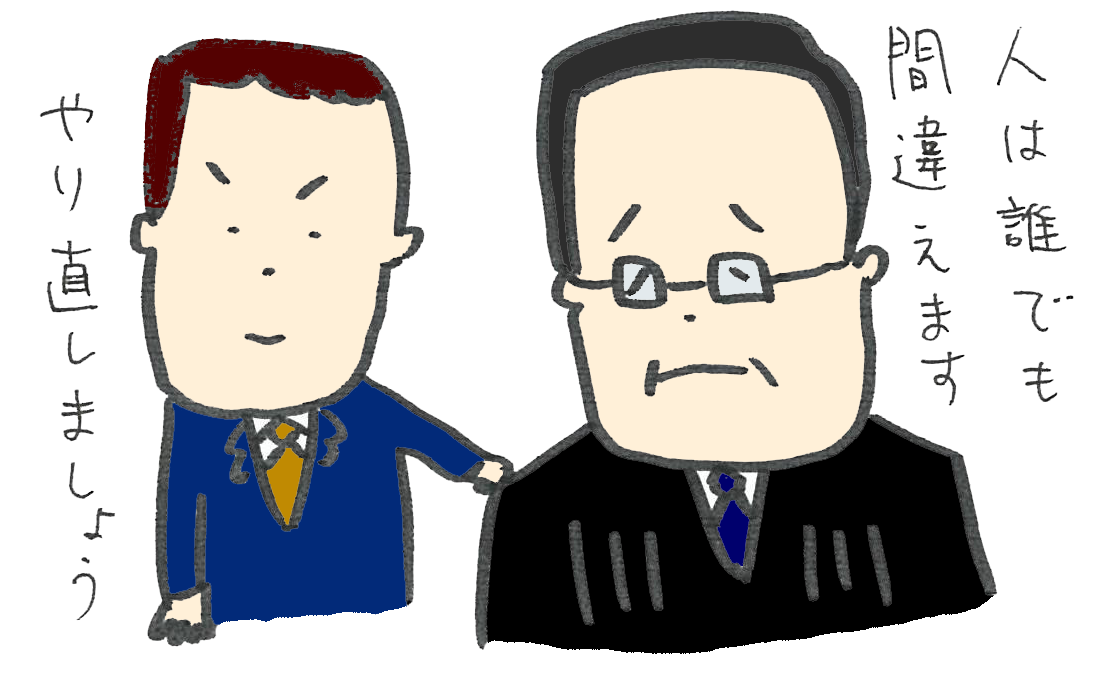
裁判をやり直すことを再審といいます。この再審制度は、わが国だけではなく、諸外国にも存在しています(詳しくは、
 「諸外国における再審法制の改革状況」(PDFファイル;931KB)をご参照ください。)。
「諸外国における再審法制の改革状況」(PDFファイル;931KB)をご参照ください。)。
では、なぜ再審制度が必要なのでしょうか。
刑事裁判では、被告人(刑事裁判にかけられた人)がその犯罪を行ったことを、検察官が証明しなければなりません。そして、検察官の立証(証明するために証拠調べを行うこと)によって、被告人が犯罪を行ったことが「合理的な疑いがない程度」に証明された、と裁判官が判断したときに、その被告人は有罪となります。逆にいえば、「合理的な疑いが残る」ときには、裁判官は無罪判決を言い渡さなければなりません。
もっとも、検察官は、裁判に提出する証拠を選別できますので、裁判官はすべての証拠を見ているわけではありませんし(
 Q3をご参照ください。)、また、裁判官の判断も、人間が行うことですので、間違いがあり得ます。
Q3をご参照ください。)、また、裁判官の判断も、人間が行うことですので、間違いがあり得ます。
日本では、そうした間違いが起こり得ることを前提に、「三審制」といって、地方裁判所(または簡易裁判所、家庭裁判所)、高等裁判所、最高裁判所という三段階の裁判を受けられる制度をとっています。
しかしそれでも、検察官が選別した限られた証拠の中で、裁判官という人間が判断するのですから、「絶対に間違えない」とはいえません。現に死刑えん罪4事件(
 Q2をご参照ください。)といわれる事件がありました。また、科学技術の進化でDNA型鑑定の精度が上がり、以前のDNA型鑑定で犯人とされた人が実はそうではなかったということが後から分かった事例(
Q2をご参照ください。)といわれる事件がありました。また、科学技術の進化でDNA型鑑定の精度が上がり、以前のDNA型鑑定で犯人とされた人が実はそうではなかったということが後から分かった事例( 足利事件)や、犯人とされた人が有罪となった後に、真犯人が現れたことによって、その人が犯人ではなかったことが明らかとなった事例(氷見事件)もあります。
足利事件)や、犯人とされた人が有罪となった後に、真犯人が現れたことによって、その人が犯人ではなかったことが明らかとなった事例(氷見事件)もあります。
裁判は人間が行うものである以上、間違いがあり得るのです。
えん罪による処罰は、国家による究極の人権侵害です。人間の判断の間違いを訂正し、えん罪被害者を救済する。そのために、「裁判のやり直し」=再審制度があるのです。
Q2 今の日本の裁判で、間違いが起きることなんてあるの?
- Answer
-
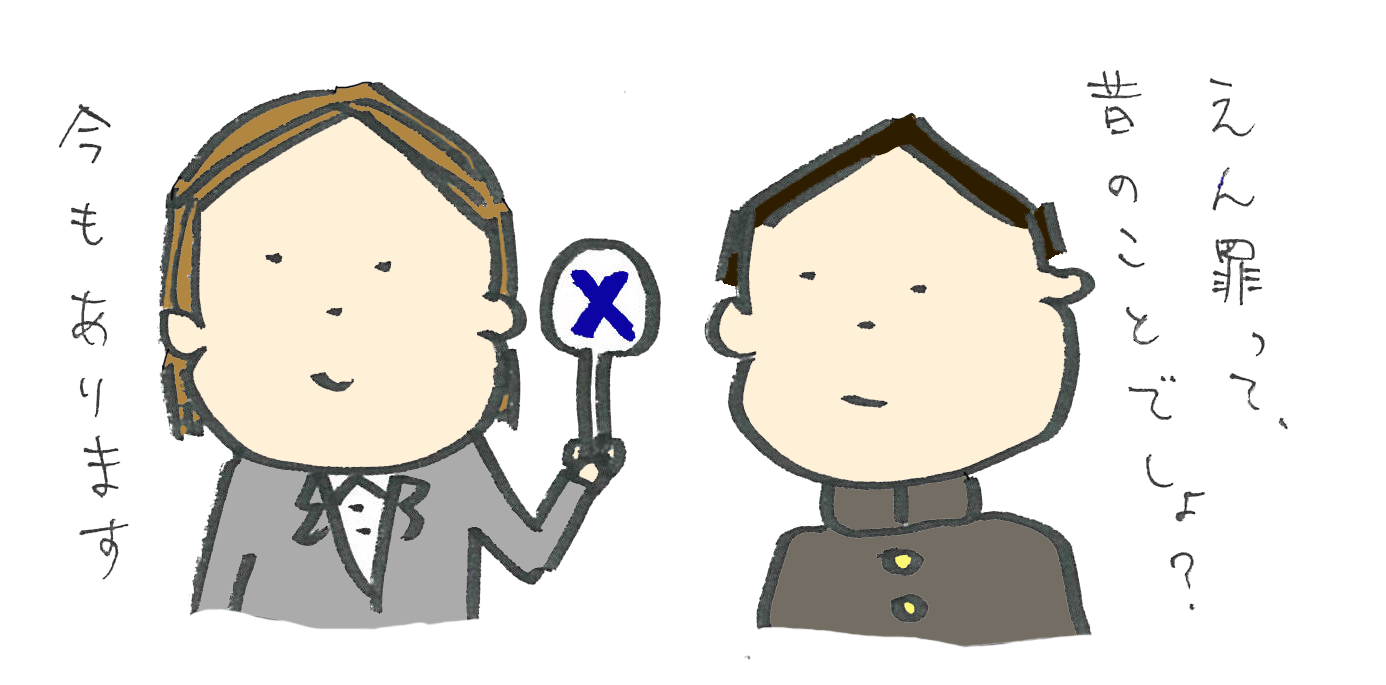
残念ながら、起きると言わざるを得ません。
今の制度では、検察官は、被告人(刑事裁判にかけられた人)に有利な証拠を裁判に出さなくても良く、裁判官は、捜査機関(警察や検察)が集めたすべての証拠を見て判断しているのではありません(
 Q3をご参照ください。)。
Q3をご参照ください。)。
被告人に有利な証拠が裁判に出されないままになっていたり、時には、捜査機関が有罪方向の証拠をねつ造したのではないかと疑いが持たれる事件もあります(
 袴田事件等)。
袴田事件等)。
また、裁判官も人間ですから、限られた証拠の中で被告人が有罪かどうかを判断するときに、その判断を間違えることもあり得ます。例えば、真犯人ではなかった人が、取調べで嘘の自白を迫られ、裁判の場でも自白をしたらどうなるでしょうか。
昭和20年代から30年代にかけて、免田事件、財田川事件、島田事件、松山事件という4つの事件が起きました。この4事件は、いずれも被告人が自白し、死刑が確定した事件でした。けれど、後の昭和50年代から平成にかけて、これらすべての事件で、やり直しの裁判が行われ無罪になっています。いずれの事件も、客観的な証拠が少なく、捜査機関による自白の強要があったとされた事件でした。「私がやりました」という自白が正しいかどうかは、例えば凶器に付いていた血液のDNA型鑑定のように科学的に判断することはできません。また、自白は、話した内容そのままではなく捜査機関が話をまとめて作った供述調書という形で裁判官の目に触れることが多いので(今は、一定の事件では取調べの録音・録画が行われています。)、特に判断を間違う危険があります。
先に述べた4事件では、4人もの方が、自分が犯罪をやっていないのに、やったと認定されて死刑判決を言い渡され、それが正されることなく死刑判決が確定してしまったのです。これらは「裁判所が間違うことがある」ということを如実に示しています。
また、このような誤りは昔に限ったわけではありません。21世紀になってからも、やっていない事件の犯人にされて刑務所に入れられ(2007年に有罪が確定し、2017年まで服役させられました。)、やり直しの裁判の結果無罪になったという人もいます(
 湖東事件)。
湖東事件)。
Q3 刑事裁判って、すべての証拠を裁判官が見て判断しているんじゃないの?
- Answer
-

いいえ、そうではありません。
刑事事件は、捜査機関(警察や検察)による捜査から始まります。捜査機関は、捜索や逮捕といった強制捜査をしたり、任意に関係者から事情を聴取したりするなどして、特定の人が特定の犯罪を行ったことの証拠を広範に集めていきます。
例えば、窃盗(万引き)一つとっても、捜査によって獲得される証拠はかなり多岐にわたります。商品が無くなったとされる店(現場)を撮影した写真、店に被害品が入荷した事実を示す伝票、犯人の行動が記録されている防犯カメラ映像、被害店舗関係者(店長、犯人の犯行を目撃した人、犯人を追跡した人、犯人を取り押さえた人など)の供述などがあります。
そして、刑事裁判では、「その人(被告人)が犯罪を行ったこと」を証明しなければならない検察官が、集められた証拠の中から、被告人が有罪であることを証明するために、裁判に提出する証拠を選んでいきます。検察官は、捜査機関が集めた多くの証拠(時には膨大と言えるほど多い場合もあります。)の中から、「被告人が犯罪を行ったことを証明する方向(有罪方向)の証拠」を厳選して裁判に出せばよく、「その被告人が犯人ではないことを示す方向(無罪方向)の証拠」は出さなくてもよいのです。
結果として、裁判官は、捜査機関が集めたすべての証拠を見ているわけではなく、「検察官が選んで、裁判に提出した証拠」と被告人・弁護士が集めた証拠を基に、その被告人が犯罪を行ったかどうかを判断しなければならないのです。
なお、検察官が裁判に提出した証拠以外に捜査機関がどのような証拠を持っているのかについては、裁判官はもとより、被告人も弁護士も、長い間、これを知る手段がなく、裁判官や被告人・弁護士にとってはブラックボックスでした。
近年、公判前整理手続という手続が導入されたことで、その手続が適用される事件については、検察官が事件について保管している証拠のリストが示されるようになりましたが、証拠書類のタイトルがリストに記載されているだけで、中身は全く分からない(例えば、多くの書類には単に「捜査報告書」というタイトルが書かれているだけです。)など、「捜査機関がどのような証拠を持っているのか」を知る手段としては、今もなおまったく不十分と言わざるを得ません。
Q4 弁護士は、捜査機関(警察や検察)が集めた証拠を全部見られるんじゃないの?
- Answer
-
いいえ、そうではありません。
弁護士は、捜査機関が集めたすべての証拠を見ることができるわけではありません。
起訴されて刑事裁判になるまでは、弁護士は一切の証拠を見ることができません。
起訴された後も、弁護士が見ることができる証拠は、原則として検察官が裁判に提出しようとしている証拠に限られ、加えて法律上、被告人・弁護士に開示(証拠を見せること)を義務付けられている証拠や検察官が任意に開示した証拠を見ることができる場合があるくらいです。
そして、判決が出て確定した後も、弁護士はすべての証拠を見られるわけではありません。有罪判決が確定すると、法律等の規定に従って、裁判に提出された証拠も提出されなかった証拠も検察庁で保管されますが、そのすべてを見たりコピーしたりする権利は弁護士に認められていないのです。
やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続(再審請求手続)においても、同様です。再審請求手続に関する法律の条文にも、証拠開示について明確に定めたものはありません。裁判官の有している訴訟指揮権や、検察官の自発的な対応に依存せざるを得ないのが現状です。
このように、弁護士には、捜査機関が持っているすべての証拠を見る権利がないので、捜査機関が持っている証拠の全体像を把握することもできないのです。
Q5 捜査機関が、証拠を隠すことなんてあるの?
- Answer
-
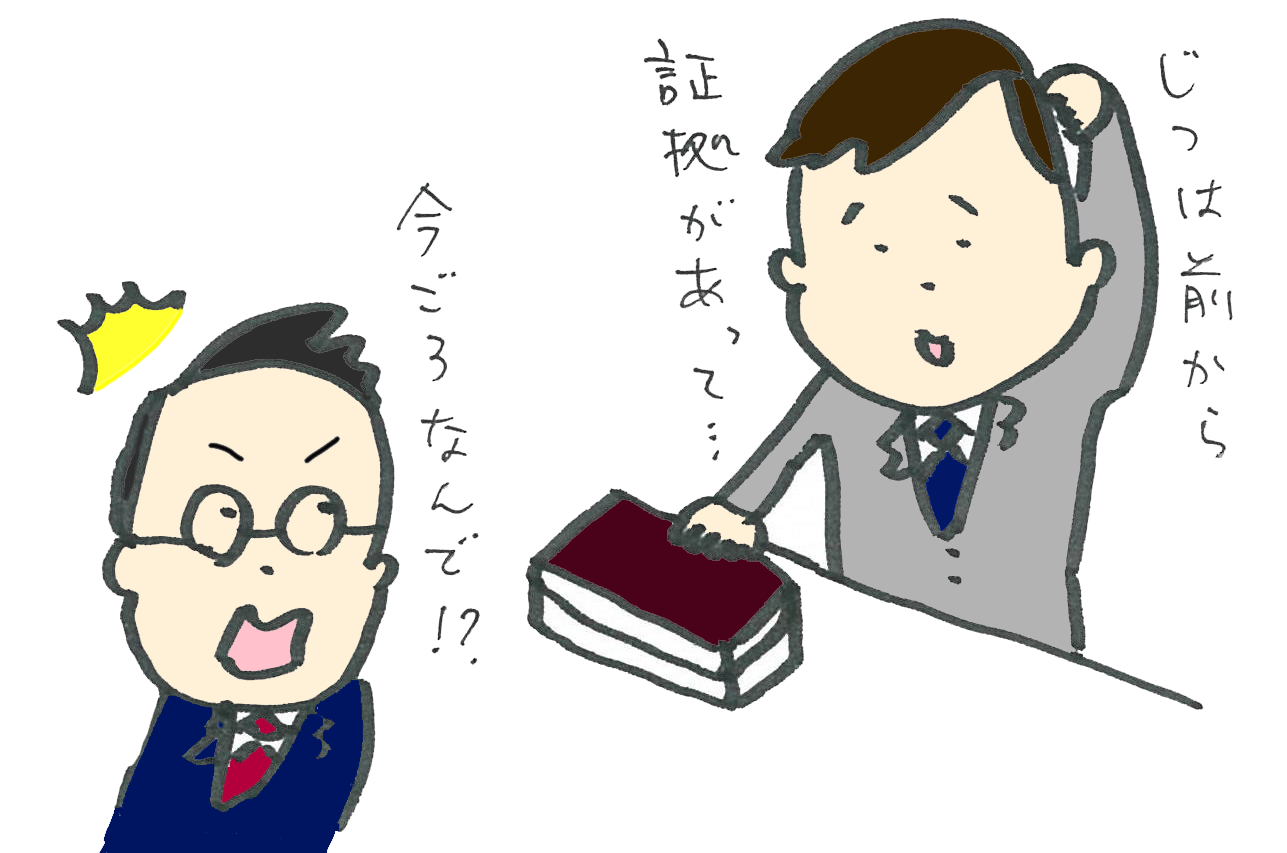
残念ながら、あるのです。
有罪判決が確定した後、やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続(再審請求手続)において、弁護士が証拠開示(検察官の保管している証拠を見せること)を求め続けた結果、それまで弁護士には全く知らされていなかった証拠が新たに開示され、その証拠が大きな理由となって再審開始決定や再審無罪を勝ち取った事件が多くあります。その中には、捜査機関(警察や検察)が証拠を隠していたと考えざるを得ないものがありました。
例えば、
 布川事件では、弁護士が、再審請求手続の過程で、検察官に対して証拠開示を求め続けた結果、死亡原因について自白の内容と矛盾する内容が記載された死体検案書や、それまで検察官が「不見当(見当たらない)」と回答し続けていた録音テープが開示されるなどしています。しかも、その録音テープは不自然に編集されたものでした。
布川事件では、弁護士が、再審請求手続の過程で、検察官に対して証拠開示を求め続けた結果、死亡原因について自白の内容と矛盾する内容が記載された死体検案書や、それまで検察官が「不見当(見当たらない)」と回答し続けていた録音テープが開示されるなどしています。しかも、その録音テープは不自然に編集されたものでした。
 東住吉事件では、再審請求手続の中で、被告人が捜査機関によって虚偽の自白に追い込まれたことを示す証拠が開示されています。
東住吉事件では、再審請求手続の中で、被告人が捜査機関によって虚偽の自白に追い込まれたことを示す証拠が開示されています。
また、
 湖東事件では、被害者の死亡原因について、被告人の自白と矛盾する内容の捜査報告書が開示されています。しかも、それが開示されたのは、再審開始決定が確定し、やり直しの裁判に向けての打合せが行われていた時のことでした。実は、その捜査報告書を含む多くの証拠は、長年にわたり、検察官に送られることなく、警察で保管されていたのです。
湖東事件では、被害者の死亡原因について、被告人の自白と矛盾する内容の捜査報告書が開示されています。しかも、それが開示されたのは、再審開始決定が確定し、やり直しの裁判に向けての打合せが行われていた時のことでした。実は、その捜査報告書を含む多くの証拠は、長年にわたり、検察官に送られることなく、警察で保管されていたのです。
これらは、捜査機関(警察や検察)による証拠隠しの一例でしかありません。
Q6 捜査機関は、なぜ重要な証拠を隠そうとするの?
- Answer
-

捜査機関(警察や検察)は、被告人の有罪判決を獲得するために力を尽くします。それが行き過ぎて、捜査機関は、有罪獲得のためにそろえた証拠に矛盾するような証拠は、無視したり、これを弁護士に見せなかったりします。捜査機関の見立てと合致しない、場合によっては矛盾するような証拠を裁判に提出したり、弁護士に見せたりすると、捜査機関の望むような有罪判決が出なくなったり、有罪判決が覆ったりします。これは、警察や検察にとって大変不名誉なことで、できる限り避けたいのです。それで、重要な証拠を隠すような行動に出るのだと考えられます。
最近の例として、
 湖東事件を紹介します(
湖東事件を紹介します( Q5でも説明していますので、ご参照ください。)。この事件では、事件から1年以上経った後、殺害を自白したとして被告人が逮捕されましたが、実は、その逮捕よりも前の時点で、警察は、全く別の死亡原因が十分に考えられるということを解剖医から聞き取り、その内容を捜査報告書にまとめていました。それにもかかわらず、警察は、その捜査報告書を検察官に送っていませんでした。被告人の有罪判決が確定し、その後、再審開始決定がなされるに至り、警察は初めてその捜査報告書を含む多くの証拠を検察官に送ったのです。検察官は、弁護士の粘り強い開示請求を受けて、その捜査報告書を含む多くの証拠を開示しました。
Q5でも説明していますので、ご参照ください。)。この事件では、事件から1年以上経った後、殺害を自白したとして被告人が逮捕されましたが、実は、その逮捕よりも前の時点で、警察は、全く別の死亡原因が十分に考えられるということを解剖医から聞き取り、その内容を捜査報告書にまとめていました。それにもかかわらず、警察は、その捜査報告書を検察官に送っていませんでした。被告人の有罪判決が確定し、その後、再審開始決定がなされるに至り、警察は初めてその捜査報告書を含む多くの証拠を検察官に送ったのです。検察官は、弁護士の粘り強い開示請求を受けて、その捜査報告書を含む多くの証拠を開示しました。
これは、極めて悪質な証拠隠しの例です。
やり直しの裁判では、当然のことながら、裁判所は無罪判決を言い渡しました。
Q7 悪いことをしてなければ、逮捕されたり裁判で有罪になったりすることなんてないんじゃないの?
- Answer
-

そんなことはありません。
犯罪の捜査をする警察官も、起訴(刑事事件について裁判官の判断を求める手続)をする検察官も、そして最終的に有罪無罪の判断をする裁判官も、みんな同じ人間です。犯人と疑っている人に対する思い込みや、犯人の特徴を示す証拠や証言の評価を誤って、犯人を見誤り、無実の人を逮捕・起訴したり、有罪の判決をしてしまうことなどが、絶対に起こらないなどということはできません。無実の人が有罪になることは起こり得るのです。実際、裁判でいったん有罪が確定した方が、やり直しの裁判の結果、無罪になったという事例はいくつもあります。つまり、本当は悪いことをしていないのに、逮捕されたり裁判で有罪になったりした人が何人もいるということです。
また、本来は決して許されないことですが、警察や検察などの捜査機関が、証拠をねつ造したり、被告人(刑事裁判にかけられた人)に有利な証拠を隠したと疑われる事件すらあるのです。
だからこそ、無実であるにもかかわらず、刑罰を受けなければならなかったえん罪被害者の方々を、すみやかに救済できる制度を作ることが必要なのです。
Q8 今までに、裁判のやり直しが認められて、無罪になった人はどのくらいいるの?
- Answer
-

司法統計によると、再審が開始され無罪になる人数は、年間数人から20人くらいですが、多くは身代わりなどがはっきりした事件で、検察官が再審(やり直しの裁判)を請求したものです。その中には、氷見事件(2007年に再審無罪)のように、裁判でも事実を争わず、服役を終えた後に再審無罪となったというケースも含まれています。この事件は、捜査機関(警察や検察)の執拗な追及により、本当は違うのに性犯罪の犯人であることを認めて有罪判決を受け、服役まで終えた方が、真犯人が別件で逮捕されたことがきっかけとなって実際は犯人でなかったことが判明し、検察官が再審請求をして無罪になった事件です。
これに対し、えん罪かどうかが激しく争われている事件で、再審が開始され無罪になることは極めてまれで、1年の間に1人いるかどうかだと言っても過言ではありません。そのような事件の多くは、日本弁護士連合会が支援したものであり、支援した事件でみると、1963年に無罪判決が確定した吉田事件をはじめ、これまでに合計18の事件で、やり直しの裁判の結果、無罪判決が確定しています(2023年8月31日時点)。この他にも、近年では、「
 大阪強姦再審無罪事件(2015年)」、「ロシア人おとり捜査事件(2017年)」などで、やり直しの裁判が行われた結果、無罪判決が確定しています。
大阪強姦再審無罪事件(2015年)」、「ロシア人おとり捜査事件(2017年)」などで、やり直しの裁判が行われた結果、無罪判決が確定しています。
Q9 裁判のやり直しが認められて無罪になった人たちの裁判は、どのくらいの時間がかかったの?
- Answer
-
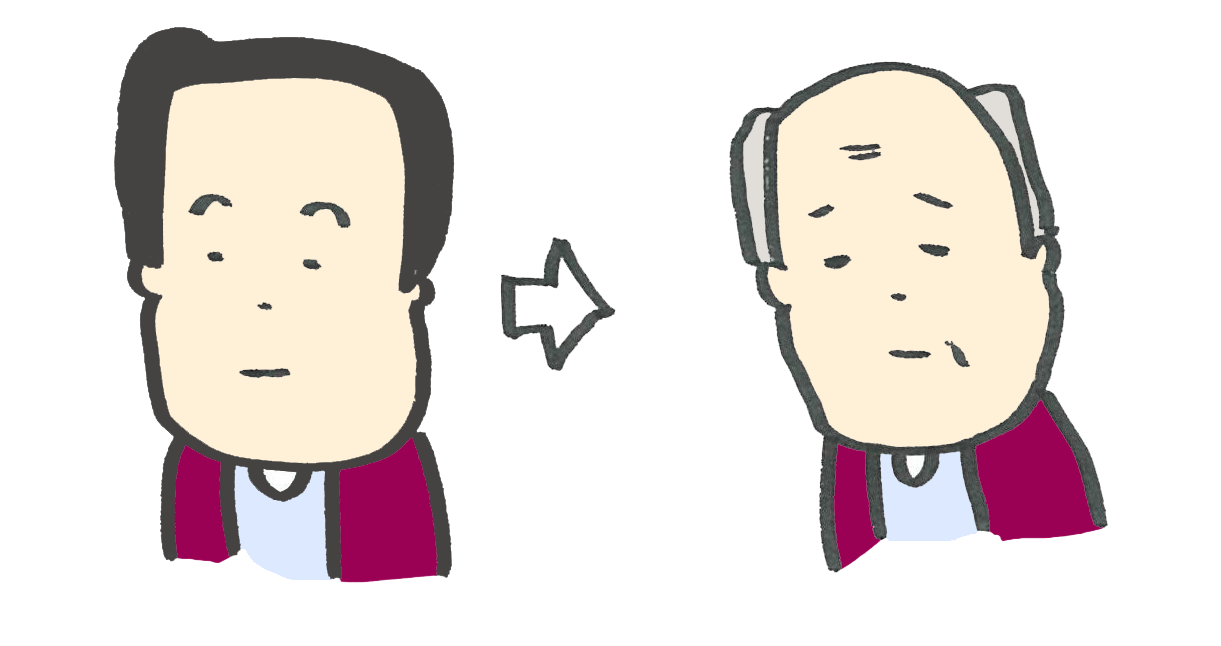
現在、裁判のやり直し、すなわち再審が開始するまでに、とてもとても長い時間がかかっています。
たとえば、やり直しの裁判の結果、無罪判決が確定した
 布川事件では、1983年12月に1回目の再審請求(やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続)をしましたが退けられ、2回目の再審請求により2005年9月に水戸地裁土浦支部が裁判のやり直しを認めたものの、検察官の不服申立てにより、最高裁で裁判のやり直しが確定したのは2009年12月のことでした。ここまでで26年もかかっています。
布川事件では、1983年12月に1回目の再審請求(やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続)をしましたが退けられ、2回目の再審請求により2005年9月に水戸地裁土浦支部が裁判のやり直しを認めたものの、検察官の不服申立てにより、最高裁で裁判のやり直しが確定したのは2009年12月のことでした。ここまでで26年もかかっています。
さらにその後、やり直しの裁判(再審公判)で再審無罪判決が確定したのは2011年6月のことですから、最初の再審請求から実に27年以上の歳月を要しています。
こんなにも時間がかかるのは、①再審請求の裁判自体のやり方・手続が法律で定まっていないこと、②裁判所が「裁判のやり直し」を認め、有罪の判決には疑いがある、と認定しても、検察官がこれに不服申立てをすれば、「やり直す」かどうかの審査が続き、「やり直し」の裁判は行われないからです。
それ以外の事件でも、名張事件は50年間、
 袴田事件は42年間、
袴田事件は42年間、 大崎事件は28年間、
大崎事件は28年間、 日野町事件は21年間も、裁判のやり直しを求めてきました。袴田事件は、ようやく裁判のやり直しが確定しましたが、それ以外の事件は、今も求め続けています(2023年8月31日時点)。これらの事件は、いずれも一度は裁判官が裁判のやり直しを認めたにもかかわらず、検察官の不服申立てにより、やり直しをするかどうかの審査が著しく長引き、袴田事件以外は、未だに裁判のやり直しができないままとなっています。
日野町事件は21年間も、裁判のやり直しを求めてきました。袴田事件は、ようやく裁判のやり直しが確定しましたが、それ以外の事件は、今も求め続けています(2023年8月31日時点)。これらの事件は、いずれも一度は裁判官が裁判のやり直しを認めたにもかかわらず、検察官の不服申立てにより、やり直しをするかどうかの審査が著しく長引き、袴田事件以外は、未だに裁判のやり直しができないままとなっています。
Q10 裁判のやり直しを決める裁判は、他の刑事裁判みたいに、誰でも見ることができるの?
- Answer
-

現状では、見ることができません。
現在の法律では、やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続(再審請求手続)は、公開(誰でも傍聴できる。)とされていません。そのため、一般の人は見ることができない状態で、裁判官、検察官、弁護士の話し合い等によって審理が進められています(公開した極めて例外的な事例もあります。)。
しかし、本来、裁判は公開が原則とされています。これは、憲法にも定められている大事な原則です。
*憲法82条1項:裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
*憲法37条1項:すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
なぜ公開が原則とされているかというと、非公開でこっそりと裁判が行われてしまうと、国民(傍聴人)の監視が無い中で、公正な裁判が行われない可能性があるからです。
ですから、再審請求手続も公開すべきです。
Q11 再審の手続って、どのように進んでいくの?
- Answer
-
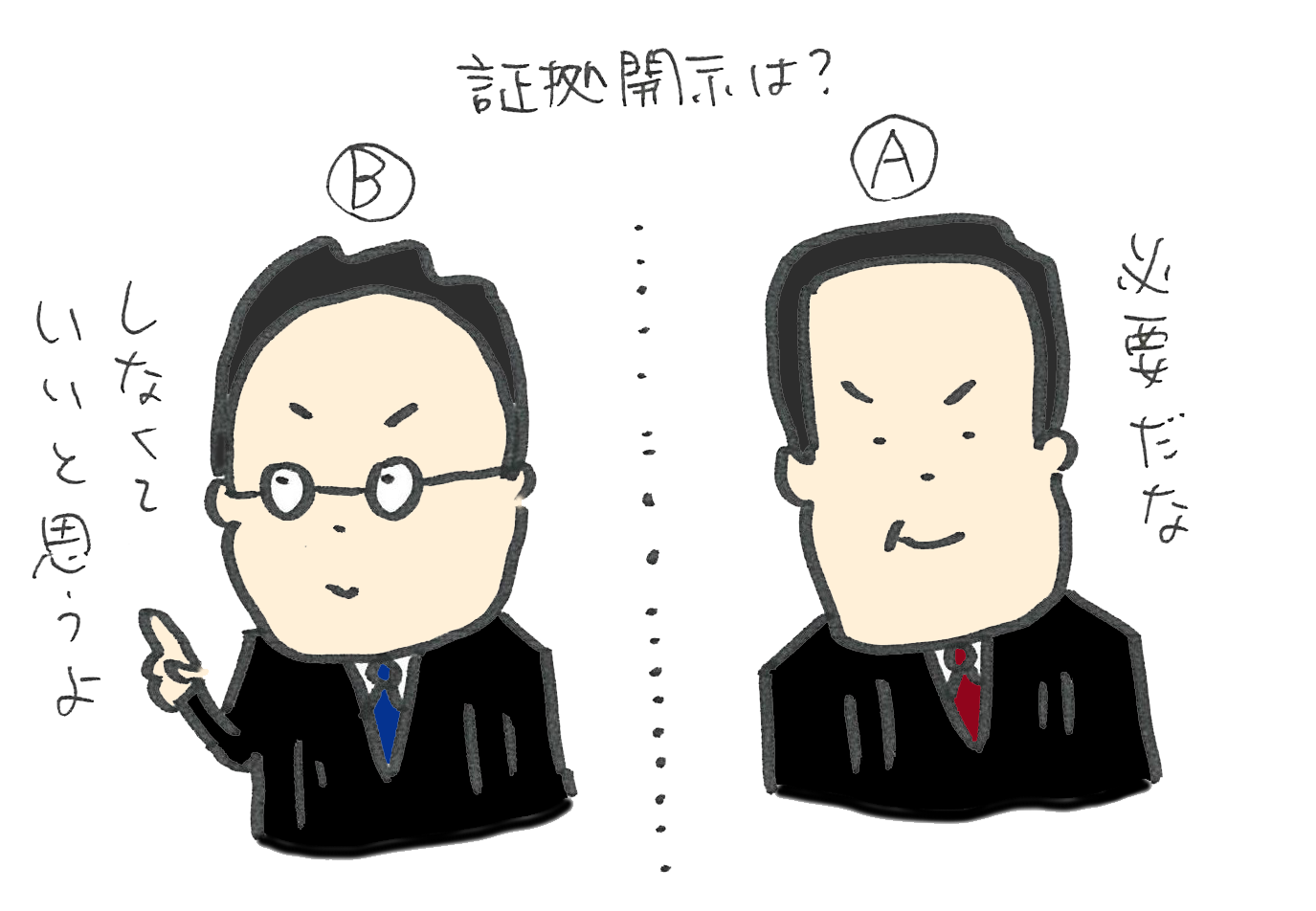
やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続(再審請求手続)は、裁判官が主体的に手続を進める「職権主義」がとられていますが、今の日本の法律(刑事訴訟法)には、再審の手続に関する規定は、わずか19条しか定められておらず、具体的にどのように審理をして判断するのかという手続の規定がありません。
したがって、手続の進め方については、裁判官に広い裁量が与えられており、手続の進み方は「担当裁判官次第」と言えます。
そして、このような裁判官の広い裁量は、再審制度の目的(えん罪被害者の救済)からすれば、無実の人を救うために積極的に用いられるべきですが、裁判官の中には、積極的に審理を進めようとする人もいれば、そうでもない人もいるのです。担当裁判官が審理に消極的だったために、本来救われるべき人が救われないということもあり得ます。このように、今の規定のままでは、再審請求手続の進め方は担当する裁判官次第ということになり、積極的な裁判官であれば救われたはずの人が消極的な裁判官によって救われなかったのではないか、といういわゆる「再審格差」が生じてしまうのです。
このような格差が生じないように、再審請求手続についても、通常の刑事裁判と同様に、手続に関する法律の規定をしっかり作るべきです。
Q12 やり直しの裁判(再審公判)を早く始めるために、再審開始決定に対して検察官の不服申立てを禁止すべきっていうけど、それって公平なの?
- Answer
-
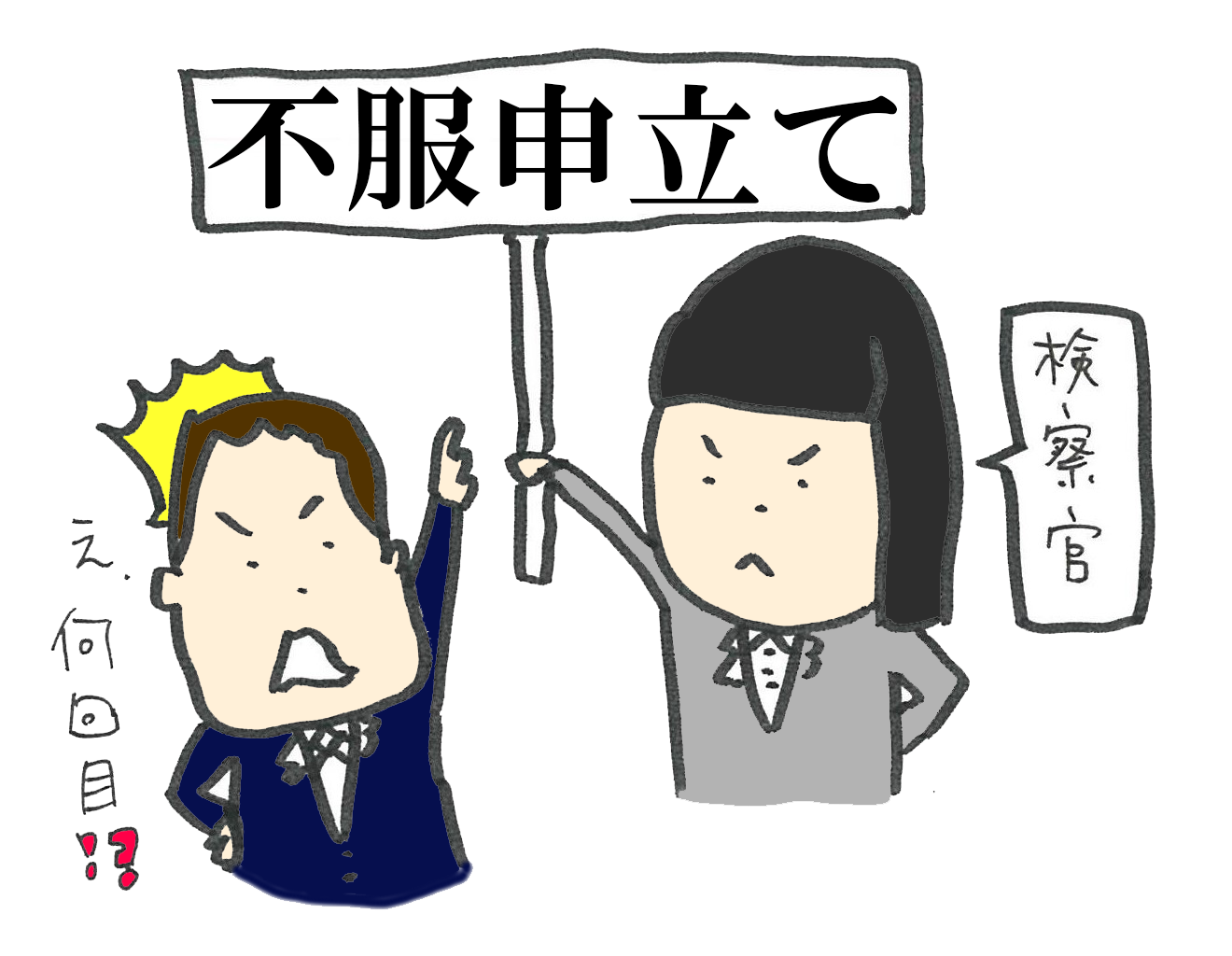
公平だと考えます。
やり直しの裁判を始めるかどうかを決める手続(再審請求手続)は、すでに通常の刑事裁判で争われて確定した判断について、もう一度裁判のやり直しをするかどうかを決める手続であり、しかも、えん罪被害者を救うためだけに設けられた制度です。
また、再審請求手続で再審開始決定が出ても、それだけで、元被告人(刑事裁判にかけられた人)の無罪が決まるわけではなく、その後に、やり直しの裁判(再審の公判)が始まり、そこで、改めて有罪か無罪かが判断されます。このように、再審の手続は2段階の構造になっています。
裁判官がいったん「再審開始決定」を出したということは、過去の有罪判決に合理的な疑いが生じていることを表していますから、検察官がそれを争うのであれば、再審請求手続の後に控えているやり直しの裁判(再審公判)で、改めて元被告人が「やはり有罪である」という主張・立証をすればよく、その検察官の主張と、元被告人・弁護士の主張とを改めて闘わせればよいはずです。
しかし実際は、検察官が再審開始決定に対する不服申立て(即時抗告・特別抗告など)を繰り返すことにより、再審公判が始まるまでにとても長い時間がかかり、今も無実の人が苦しめられているのです。
たとえば、死刑判決を受けていた免田栄さんが再審無罪となった免田事件(1948年に発生した強盗殺人事件)では、1956年に熊本地裁八代支部が再審開始を決めたものの、この決定を不服とした検察官が即時抗告をし、福岡高裁がこれを取り消してしまいました。その後も免田さんが諦めずに裁判のやり直しを求めた結果、1983年にやり直しの裁判(再審公判)で免田さんの再審無罪が確定しましたが、23歳で逮捕された免田さんは57歳になっていました。検察官の不服申立てがなければ、1950年代、つまり免田さんが30代のうちに社会に戻れていたはずです。
他にも、再審無罪が確定した事件についてみてみると、
 布川事件は約4年3か月、
布川事件は約4年3か月、 東住吉事件は約3年7か月、
東住吉事件は約3年7か月、 松橋事件は約2年3か月、
松橋事件は約2年3か月、 湖東事件は約1年3か月もの期間、再審開始決定に対する検察官の不服申立てによってやり直しの裁判(再審公判)の開始が遅れ、それだけの時間が失われてしまいました。まだ再審公判の段階ですが、
湖東事件は約1年3か月もの期間、再審開始決定に対する検察官の不服申立てによってやり直しの裁判(再審公判)の開始が遅れ、それだけの時間が失われてしまいました。まだ再審公判の段階ですが、 袴田事件は、1966年6月に発生した事件で、事件発生から57年も経過しましたが、2014年に再審開始決定が出たのに、検察官の不服申立てにより裁判のやり直しを認めるかどうかの審理が続き、その結果約9年もの間再審公判が開始されずにいました。
袴田事件は、1966年6月に発生した事件で、事件発生から57年も経過しましたが、2014年に再審開始決定が出たのに、検察官の不服申立てにより裁判のやり直しを認めるかどうかの審理が続き、その結果約9年もの間再審公判が開始されずにいました。
また、名張事件(事件発生は1961年3月)、
 大崎事件(「事件」発生は1979年10月)については、今も、再審請求手続が続いています。どちらの事件についても、少なくとも一度は裁判所が裁判のやり直しを認める決定(再審開始決定)を出しているのですが、検察官が不服申立てをして開始決定が取り消されたため、審理が長期化してしまっています。名張事件で有罪判決を受けた元被告人は、審理の途中、89歳で亡くなってしまいました。
大崎事件(「事件」発生は1979年10月)については、今も、再審請求手続が続いています。どちらの事件についても、少なくとも一度は裁判所が裁判のやり直しを認める決定(再審開始決定)を出しているのですが、検察官が不服申立てをして開始決定が取り消されたため、審理が長期化してしまっています。名張事件で有罪判決を受けた元被告人は、審理の途中、89歳で亡くなってしまいました。
無実の人の大事な時間が失われている、汚名をそそぐことができないままに無実の人が亡くなっていく、このような現状をそのままにしておくことはできません。
このように、検察官は、再審公判の段階で改めて自らの主張・立証ができる上、検察官の不服申立てのために、えん罪被害者の救済が大幅に遅れ、救済が阻まれている現状をみれば、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止しても決して不公平ではありません。




