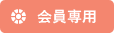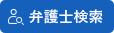特定調停スキーム利用の手引(改訂版)をご活用ください
特定調停スキーム利用の手引とは
日弁連は、「中小企業等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」(以下「金融円滑化法」といいます。)が終了したことを受けて、中小規模の事業者の抜本的な再生スキームとして、2013年12月5日、「金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム利用の手引」(通称「手引1」)を策定しました(その後、2014年6月19日および同年12月12日に改訂。)。
また、同月に、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が事務局となって、経営者保証を提供せず融資を受ける際や保証債務の整理の際の「中小企業・経営者・金融機関共通の自主的なルール」として「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表したのを受けて、日弁連は、保証債務のみを整理する「単独型」について、簡易裁判所の特定調停手続を利用する場合のスキームとして、2014年12月12日、「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引」(通称「手引2」)を策定しました。
さらに、2017年1月には、事業者の早期の任意の廃業を支援するスキームとして、「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引」(通称「手引3」)を策定しました(その後、2018年5月18日に改訂。)。
<改訂履歴>
2020年2月 実質的な中身を変えずに全体的構成を見直し体裁を揃える
「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務整理に関する書式を充実
手引1の題名を現行のものに改訂
2023年11月 「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」(2022年3月)および「廃業時における「経営者保証に関するガイドライン」の基本的考え方」(2022年3月)に対応
【手引1(一体再生型)】事業者の事業再生を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引
(旧名称「金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム利用の手引」。通称「手引1」)
2013年12月3日作成
2014年6月19日改訂
2014年12月12日改訂
2020年2月19日改訂
2023年11月29日改訂
手引1の特定調停スキームは、民事再生等の法的再生手続によれば事業価値の毀損が生じて再生が困難となる中小企業について、弁護士が、税理士、公認会計士、中小企業診断士等の専門家と協力して再生計画案を策定し、金融機関である債権者と事前調整を行った上、合意の見込みがある事案について特定調停手続を経ることにより、一定の要件の下で債務免除に伴う税務処理等を実現し、その事業再生を推進しようというものです。事業者の事業再生にあたっては、経営者保証人も同時に保証債務整理することが合理的であることから、「経営者保証に関するガイドライン」にも対応しています。
2023年11月29日更新
| 全体 |
|
| 別紙1 |
|
| 別紙2 |
|
| 書式1 |
|
| 書式2 |
|
| 書式3 |
|
| 書式4-1 |
|
| 書式4-2 |
|
| 書式4-3 |
|
| 書式4-4 |
|
| 書式5 |
|
| 書式6 |
|
| 書式7-1 |
|
| 書式7-2 |
|
| 書式8-1 |
|
| 書式8-2 |
|
| 書式9 |
|
| 参考1 |
|
| 参考2 |
|
【手引2(単独型)】経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引 (通称「手引2」)
2014年12月12日作成
2020年2月19日改訂
2023年11月29日改訂
手引2の特定調停スキームは、保証人の債務整理のみを特定調停で進める単独型の活用を想定して、特定調停手続による「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理の手順についてまとめたものです。
2023年11月29日更新
| 全体 |
|
| 別紙1 |
|
| 別紙2 |
|
| 書式1 |
|
| 書式2-1 |
|
| 書式2-2 |
|
| 書式3 |
|
| 書式4 |
|
| 書式5-1 |
|
| 書式5-2 |
|
| 書式5-3 |
|
| 書式6-1 |
|
| 書式6-2 |
|
【手引3(廃業支援型)】事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引 (通称「手引3」)
2017年1月27日作成
2018年5月18日改訂
2020年2月19日改訂
2023年11月29日改訂
手引3の特定調停スキームは、円滑な廃業・清算のニーズが高まっていることを受けて、特定調停手続の活用により、事業の継続が困難で金融機関に過大な債務を負っている事業者について、「経営者保証に関するガイドライン」の適用により保証債務を処理することも含めて、債務免除を含めた債務の抜本的な整理を行い、かかる事業者を円滑に廃業・清算させて、経営者や保証人の再起支援等を図るものです。
2023年11月29日更新
| 全体 |
|
| 別紙1 |
|
| 別紙2 |
|
| 別紙3 |
|
| 書式1 |
|
| 書式2 |
|
| 書式3 |
|
| 書式4-1 |
|
| 書式4-2 |
|
| 書式5-1 |
|
| 書式5-2 |
|
| 書式6 |
|
| 書式7-1 |
|
| 書式7-2 |
|
| 書式8 |
|
| 書式9 |
|
| 書式10-1 |
|
| 書式10-2 |
|
特定調停スキームについての税務上の取扱いに関する国税照会について
中小企業の事業再生のための特定調停スキームについての税務上の取扱いに関する国税照会について
2013年12月から運用が開始された中小企業の事業再生のための特定調停スキームにより策定された再生計画に関する税務上の取扱いについて、国税庁に対し、日弁連と日本税理士会連合会が共同で照会を行い、2014年(平成26年)6月27日付けで回答を得ています。
この回答では、本スキームに基づき策定された再建計画により、照会内容に記載した手順で債権放棄が行われた場合、
(1)債権者においては、債権放棄額を損金算入することが可能なこと
(2)債務者においては、債務免除益等の範囲内で期限切れ欠損金を損金算入することが可能なこと
が明確になっております。
事業再生型の特定調停スキームを利用する上で重要な情報ですので、参照の上、ご活用いただければ幸いです。
- (国税庁ウェブサイト)特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて
- 特定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(補足説明) (PDFファイル;245KB)
特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の 取扱いに関する国税照会について
国税庁のウェブサイトに「特定調停スキーム(廃業支援型)に基づき債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて」が掲載されています。
本照会の趣旨概要は以下のとおりです。
イ 債権放棄をした債権者(金融機関等)の税務上の取扱い
特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づく債権放棄の額は、法人税基本通達9-6-1(3)ロに沿って検討すると、貸倒れとして損金の額に算入されると考えられること
ロ 債務免除を受けた債務者(個人事業者)の税務上の取扱い
特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づく個人事業者の債務整理は、所得税法第44条の2第1項に沿って検討すると、各種所得の計算上、総収入金額に算入しないこと
ハ 保証人が保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の税務上の取扱い
特定調停スキーム(廃業支援型)として本手順に従い、特定調停において成立した調停条項に基づき、保証人が保証債務を履行するためにその有する資産を譲渡し、保証債務の履行により取得した求償権を書面により放棄した場合は、所得税法第64条第2項に沿って検討すると、「求償権の全部または一部を行使することができないこととなったとき」に該当すると考えられること
廃業支援型の特定調停スキームを利用する上で重要な情報ですので、参照の上、ご活用いただければ幸いです。