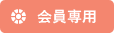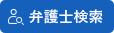法教育コラム
いつかの未来のために(法教育コラム)
第144回 奈良弁護士会の法教育委員会の活動をご紹介します!
日弁連市民のための法教育委員会 委員
奈良弁護士会法教育委員会 副委員長
市ノ木山 朋矩

奈良弁護士会「法教育に関する特別委員会」の活動
奈良弁護士会では、社会の担い手となる子どもたちを含む市民の皆さまが、自身で考え、社会のルールを主体的に活用できる力を伸ばすことのお手伝いをさせていただけたらとの思いから、「法教育委員会」を設置し、精力的な活動を続けています。
法教育の核心:自律的な問題解決能力の育成
法教育委員会が目指す「法教育」とは、単に実社会の法や司法制度を知識として教える、伝えるものではありません。その目的は、個人の尊重、平等、自由と責任、正義といった法の基礎にある原理の理解を通じて、自ら考え、行動する力と態度を養うことにあると考えます。
法やルールが、権力者から与えられるものではなく、「自分たち自身を守るために、自分たちで作るものだ」ということを理解してもらうこと。そして、自分の意見を持つだけでなく、他者の意見に耳を傾け、正義や公平といった普遍的な価値に基づいて問題の解決を図る。このような考え方や姿勢を、今後の社会を担う子どもたちに早くから学んでもらうことは極めて重要であると考えています。
教育現場と連携する多様な活動
法教育委員会は、学校等における法教育の普及・推進の一翼を担えたらとの思いから、教育関係者との協働関係に基づき下記各活動を展開しています。
1 現場との接点:「出張授業」と「いじめ予防出前授業」
(1)学校等の要請に応じて弁護士が学校に出向く「出張授業」を企画・実施しています。弁護士の仕事について生徒からインタビューを受ける形式が多く、生徒にとって法曹という職業を身近に感じられる機会となっています。
(2)また、2013年度からは、小・中学生を対象に「いじめ予防出前授業」を奈良県全域で実施しています。いじめが取り返しのつかない結果に繋がりう得ること、被害者や傍観者の心情を、具体的な事例やわかりやすい例えを用いて生徒に伝え、いじめを許さない環境づくりを促しています。
2 実践的な学びの場:「ジュニアロースクール」と「高校生模擬裁判選手権」
(1)中学生・高校生等を対象に、模擬裁判や模擬調停を体験してもらい、法律クイズに挑戦してもらうイベントとして「ジュニアロースクール」を毎年開催しています。参加生徒の学年に幅があるため、扱う事案やクイズの難易度設定に工夫を凝らして実施しており、参加者からは、法律が身近に感じられたとの声が寄せられています。
(2)「高校生模擬裁判選手権」に出場する学校の支援も継続しています。2025年度は初めて、これまで支援し続けてきた学校に加え、新たに1校に声をかけた結果として、支援する学校が2校に増加しました。県内で2つの学校が出場することは、生徒たちにとって大きな刺激となり、また、支援する弁護士間での情報共有も進んだことで、支援の質の向上にも寄与したものと思います。
(3)この他、大学における講義、裁判傍聴への協力等も積極的に行っています。
2025年度の新たな一歩:全国規模のセミナーの開催地として
2025年度には、日本弁護士連合会(日弁連)主催の法教育セミナーを奈良で開催するという大きな経験を得ました。全国の法教育に関心のあるメンバーが一堂に会し、特に現代社会の重要テーマである情報リテラシー教育について深く学び合うことができました。
奈良弁護士会「法教育に関する特別委員会」のこれから
法教育委員会は、この全国規模のセミナーの成功を足掛かりとして、活動を通じて得られた知見やネットワークを活かし、奈良県における法教育の普及、その土台としての法教育現場との関係構築にいっそう励む所存です。