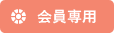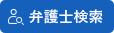取調べの問題事例
取調べの問題事例 事例1
検察官が、弁護士による弁護人になろうとする者としての被疑者との接見を妨害したことについて、裁判所が、国家賠償請求訴訟で担当検察官の行為の違法性を認め、当該弁護士に対する慰謝料の支払を命じた事案(2019年、業務上横領事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、自らが代表取締役を務める会社の売上金を着服して横領したとの嫌疑を受けており、その件の取調べを受けるために、任意で検察庁(東京地方検察庁特別捜査部)に出頭しました。
B弁護士は、Aさんの妻から電話連絡を受け、Aさんと面会して弁護人になってほしいと依頼されたことから、検察庁を訪れてAさんとの接見を求めました。対応したY1検察官は、Aさんの取調べ終了後に改めて連絡するなどと述べたため、B弁護士はAさんとの速やかな面会を要求し、また、Aさんに弁護士と面会する意思があるか否かを確認するように求めましたが、Y1検察官はこれを拒みました。その後も、Y1検察官は、B弁護士がAさんの妻と連絡した電話番号の使用者等を調査する必要があるなどと述べて、結局、Aさんの取調べが終了するまでの間、B弁護士との接見を認めませんでした。
Aさんの取調担当であったY2検察官は、上記の接見妨害が行われている間に、本件の取調べを続け、Aさんの自白調書を作成しました。
その後、B弁護士が原告となって提起した国家賠償請求訴訟において、東京地方裁判所(民事第1部)は、Y1検察官の対応について、国家賠償法上の違法が認められると評価し、被告(国)にB弁護士に対する慰謝料10万円の支払を命じる判決を言い渡しました。
その後、国は、この第一審判決に控訴し、検察官が接見を認めなかったことは違法ではなかったと改めて主張しましたが、控訴審(東京高等裁判所第5民事部)は、国の主張に理由はないとして控訴を棄却しています(原告も、慰謝料の増額を求めて控訴しましたが、控訴審は棄却しています。)。
 令和2年11月13日 東京地方裁判所判決(裁判所ウェブサイト)
令和2年11月13日 東京地方裁判所判決(裁判所ウェブサイト)
取調べの問題事例 事例2
録音録画が実施されていない状況での警察による取調べにおいて作成された自白調書について、取調官の誘導によって虚偽の自白をさせられた可能性があることを指摘して、無罪判決を言い渡した事例(2017年、迷惑防止条例違反)。
- 概要を見る
-
Aさんは、女性のスカート内を盗撮したとの疑いをかけられ、在宅のまま被疑者として警察の取調べを受けました。Aさんにはその時点で弁護人が選任されておらず、取調べも、録音録画が行われない状態で実施されました。
取調べを担当した警察官Xは、「私は、録画ボタンを押し(略)持ち手部分の外側に付いたカメラレンズが天井を向くようにして女性のスカート内に約5秒間差し入れた」など、撮影行為時の具体的な内容をあたかもAさんが説明していたかのように記載した供述調書を作成し、Aさんはこれに署名をしました。検察官Yは、この時作成された自白調書を証拠として、Aさんを迷惑防止条例違反で略式起訴しました。
その後、Aさんは、弁護士Bに相談し、取調べで、取調官の見立てに沿った説明を認めて供述調書に署名してしまったことを説明しました。Aさんは、改めて、略式起訴ではなく、正式な裁判を行うように申立てを行いました。
裁判では、Aさんが持っていた携帯電話に録画されていた事件当時の映像が証拠として調べられましたが、Aさんの自白調書に記載されているような方法でスカート内を盗撮した場面は撮影されていませんでした。判決は、Aさんの自白調書について「警察による取調べの経験も乏しいと窺われる被告人において、繰り返し任意での出頭・取調べを受ける中で、そのような罪悪感などから取調官の誘導にのる形で本件自白ができあがってしまったとしても何ら不自然とはいえない。そうすると、本件自白の信用性を認めることはできない。」として、Aさんに、無罪判決を言い渡しました。
 平成30年9月7日 福岡地方裁判所判決(裁判所ウェブサイト)
平成30年9月7日 福岡地方裁判所判決(裁判所ウェブサイト)
取調べの問題事例 事例3
警察官による取調べで、黙秘権を行使する被疑者に対して、個人の尊厳を著しく傷つける発言がなされた事案(2018年、殺人未遂事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、東南アジアの国から、日本で働くことを希望して来日しました。Aさんは、仕事を求める外国人を日本へ派遣する「ブローカー」であった甲さんとの間で口論となり、Aさんが持っていた包丁で甲さんに怪我をさせてしまいました。
警察は、Aさんを、殺意をもって甲さんを突き刺したとする殺人未遂罪で逮捕・勾留しました。Aさんは、甲さんを殺そうとしたことはなく、もみ合いの中で刃物が刺さってしまったことを弁護人Bに説明しました。弁護人Bは、Aさんに対し、取調べでは、黙秘権を行使するようアドバイスし、Aさんはこれに従いました。
Aさんは、身体的性別は女性ですが性自認は男性であるトランスジェンダーでした。Aさんの取調べを行った警察官Xは、黙秘するAさんに対し「男として生きていきたいというなら、やったことに責任をもつ男らしさを見せた方が良い。」「男なら男らしく、自分のやったことに向き合って生きていく必要がある。」などと発言しました。警察官Xの発言は、Aさんの性自認についての配慮を欠き個人の尊厳を傷つけるものであり、かつ、Aさんに保障されている黙秘権の行使を不当に妨害しようとする、極めて悪質なものでした。この取調べは、録音録画されていたため、上記のような不当な発言があったことを、弁護人Bは、取調べ記録映像を視聴して確認しています。
弁護人Bは、Aさんから上記の様な取調官の発言があったことを聞いて、直ちに担当検察官Yおよび検事正宛の苦情申入れを行いましたが、担当検察官Yは、Aさんを起訴した後になって、取調べを担当した警察官Xに口頭で注意をしたとの報告をしてきたのみでした。
Aさんは、その後、殺人未遂罪で起訴され、裁判員裁判で審理がなされました。判決では、Aさんに殺意があったとは認められず、殺人未遂罪よりも法定刑の軽い傷害罪が成立すると判断されました。Aさんには、直ちに刑務所に服役する必要はないとする執行猶予付きの判決が言い渡され、その後、母国に帰りました。
取調べの問題事例 事例4
警察官が、被疑者に対して、黙秘権および弁護人との接見交通権を侵害する取調べを行ったことについて、裁判所が、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟において、担当警察官の取調べの違法性を認め、慰謝料の支払を命じた事案(2021年、青少年保護育成条例被疑事件)。
- 概要を見る
-
会社員のAさん(当時19歳)は、女児にわいせつな動画を見せたとの疑いをかけられて甲県警察に逮捕され、その後10日間警察署の留置場で勾留されました。勾留満期に釈放されたAさんは、家庭裁判所での審判を受けましたが、家庭裁判所は、「非行事実なし」(Aさんが嫌疑を受けた事件を起こしたことは認められない)との決定をしました。
その後、Aさんは、勾留中に担当警察官から違法な取調べを受けたことによる慰謝料等の支払を求めて、甲県を被告として国家賠償法に基づく損害償請求訴訟を提起しました。裁判所は、取調べに違法があったことを認め、被告(甲県)に、Aさんに対する慰謝料の支払いを命じる判決を下しました(双方の控訴が棄却され、判決は確定しています。)。
判決において、裁判所は、取調べを担当した警察官Xが、事実を否認して黙秘権を行使するAさんに対して「都合が悪くなると黙ってばっかり」「調べるうちにどんどん不利になるものばかり出てきている」「本当のことを言ったら周りの評判が下がると思っているんじゃないか」などと繰り返し発言したとの事実を認定した上で、黙秘権の行使が不利益や社会的非難を受けるに値するかのような誤解を与える発言だと指摘し、取調べ方法として相当性を欠き、黙秘権を実質的に侵害する違法なものであると判断しました。
また、警察官Xによる「弁護士さんと接見したときに目撃者がいてどうすればいいのか相談とかしてるんだろ」との発言は、弁護人との接見の具体的内容を質問・聴取する内容であり、弁護人の援助を受ける機会を確保している刑事訴訟法39条1項の趣旨を損なうものであるから、捜査機関としての注意義務に違反し、接見交通権を侵害する違法なものであると判断しました。
なお、Aさんの代理人弁護士B(逮捕当時の弁護人)は、家庭裁判所の審判の後、甲県警察本部に対して、書面での苦情申出を行うとともに、事実関係の調査や取調べを担当した警察官Xに対する適切な処分等を行うことを求めましたが、甲県警察本部からは、調査の結果、黙秘権や接見交通権を侵害するような取調べを行ったとの事実は認められなかった旨の回答がなされていました。
【掲載誌】
令和3年3月3日 熊本地方裁判所判決(判例時報2504号113頁、LLI/DB判例秘書登載)
令和3年9月3日 福岡高等裁判所判決(LLI/DB判例秘書登載)
取調べの問題事例 事例5
取調べ担当検察官の発言によって共犯者が虚偽の供述に及んだ可能性があることが、取調べの録音・録画によって明らかとなり、無罪判決が言い渡された事例(2021年、業務上横領)。
- 概要を見る
-
不動産販売等を行う会社の代表者であるAさんは、学校法人の土地売却にかかる手付金21億円を横領したとの嫌疑を受けて起訴されました。検察官(大阪地検特捜部)は、Aさんが、学校法人の元理事長らと共謀して、学校法人を買収する計画に当初から荷担しており、業務上横領の故意も有していたとの「見立て」に基づく捜査を行い、裁判でもそのような主張を続けました。一方、Aさんは、捜査段階から一貫して、業務上横領の共謀や故意を否認する供述を続けていました。
大阪地検特捜部は、不動産会社の社長である甲氏およびAさんの部下である乙氏を、本件の共犯として逮捕し、それぞれに対する取調べを行いました。なお、甲氏および乙氏は、いずれも逮捕直後には本件への関与を全面的に否認していましたが、その後自らの関与を認めるに至り、業務上横領事件の共犯者として起訴され、有罪判決を受けています。
甲氏および乙氏に対する取調べは、逮捕後連日行われ、取調べ時間は、いずれも合計70時間を超えていました。取調べの録音・録画映像により、甲氏の取調べを担当した検察官Y1は、Aさんの関与を否定していた甲氏に対して、「現時点ではAと同じくらい関与した、情状的にかなり悪いところにいる、Aの意向があったというなら情状は全然違うと思う」などの発言をしていたことが明らかになっています。また、乙氏の取調べを担当した検察官Y2は、Aさんの関与を否定していた乙氏に対して、「確信的な詐欺である、今回の事件で果たした(部下の)役割は、共犯になるのかというようなかわいいものではない、(会)社の評判を貶めた大罪人である、今回の風評被害を受けて会社が被った損害を賠償できるのか、10億、20億では済まない、それを背負う覚悟で話をしているのか」などの発言をしていたことが明らかになっています。取調べが行われる中で、甲氏および乙氏は、いずれも供述を変遷させ、Aさんも事件に関与していたと説明するに至りました。検察官は、甲氏および乙氏のぞれぞれについて、Aさんとの間で本件業務上横領の共謀を行ったことを認める内容の供述調書を作成しました。なお、甲氏は、その後の取調べで、さらに供述を変遷させ、Aさんが関与していたことを再度否定する説明をしていましたが、検察官Y1は、Aさんの関与を否定する内容の供述調書を作成しませんでした。
Aさんが起訴された後、公判を担当する検察官は、Aさんとの共謀を認める内容の甲氏および乙氏の供述調書について、刑事裁判の証拠として取り調べるよう請求しました。Aさんの弁護人は、裁判において、取調べの録音・録画映像に記録されたやりとりを根拠に、検察官Y1およびY2による不当な発言が繰り返された結果、Aさんに不利な虚偽供述がなされるに至ったことを主張しました。
裁判所(大阪地方裁判所第14刑事部)は、甲氏について、検察官Y1の発言により、甲氏が、自らの処分が軽くなると考えてAさんに不利な供述をするに至った可能性があることを指摘し、甲氏の供述調書の信用性には疑問が残ると判断して、証拠とすることを認めない決定をしました。
また、乙氏について、検察官Y2の発言が、「必要以上に強く責任を感じさせ、その責任を免れようとして真実とは異なる内容の供述に及ぶことにつき強い動機を生じさせかねない」ものであると指摘し、このような取調べ後に乙氏が供述を変遷させて、Aさんに不利な説明をするようになったことについて、「変遷以降の供述内容の真実性には疑いが残る」と判断しました。
これらの判断を前提に、裁判所は、Aさんについて、業務上横領事件について故意があったと認定するには合理的な疑いが残るとして、無罪判決(求刑懲役3年)を言い渡しました(検察官が控訴せず、判決は確定)。
 令和3年10月28日 大阪地方裁判所判決(裁判所ウェブサイト)
令和3年10月28日 大阪地方裁判所判決(裁判所ウェブサイト)
取調べの問題事例 事例6
弁護人が選任されておらず、録音録画もされていない状況で実施された取調べで作成された自白調書の信用性を肯定して、赤信号を「殊更に無視」する危険運転致死罪が成立するとした第一審判決を破棄して、赤信号を看過した過失運転致死罪が成立するにとどまるとの判決を言い渡した事案(2020年、危険運転致死被告事件)。
- 概要を見る
-
トラック運転手として働いていたAさん(50代男性)は、事件当日、仕事が早番であったため早朝から勤務を開始し、取引先数カ所を回った後、正午ころ会社に戻るためにトラックを運転していました。
Aさんにはガンに罹患して医師から余命宣告を受けた弟がおり、この日の昼に弟に付き添って病院に行き、医師からの説明を受ける予定になっていたことから、Aさんは、運転中に注意散漫で「心ここにあらず」といった状態になっていました。
事故が起きた交差点に進入する際、Aさんは、対面の信号機が赤色に変わるのを見落としてしまい、交差道路を自転車で通行していた被害者(70代男性)の存在に気付かないまま運転を続けてしまいました。衝突直前になって被害者に気付き、急ブレーキをかけましたが間に合わず、Aさんの車と被害者の自転車は衝突しました。被害者は、自転車もろとも路上に転倒し、頭を強く打って脳挫傷の傷害を負い、ほどなく搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは逮捕され、事故当日およびその翌日にかけて、警察官の取調べを受けました。事故の2日後、Aさんは釈放されましたが、その後は在宅被疑者として取調べや実況見分への立会い等に応じました。事故から約9か月が経過した頃、Aさんは危険運転致死罪で起訴されました。Aさんは、起訴されるまで弁護人を選任したことはなく、当番弁護士制度(弁護士会が派遣した弁護士が、無料で逮捕勾留された人の相談に応じる制度)等を利用して弁護人から助言を受けるということも一度もありませんでした。
Aさんは、逮捕直後は、警察官に対して、信号の色ははっきりとは覚えおらず、赤信号を見落としていた(看過していた)可能性があるという説明をしていました。しかし、その後の取調べが重ねられる中で、対面信号機が赤色だと認識していたのにあえて(殊更に)無視したことを自白する不正確な(Aさんの実際の記憶とは異なる)内容の供述調書が作成されてしまいました。
Aさんは、第一審の裁判では、赤信号を殊更に無視したことはないとして危険運転致死罪の成立を争いましたが、裁判所は、同罪の成立を認め、懲役5年の実刑判決を言渡しました。そして、Aさんの自白調書についても信用性が認められると判示しました。
この判決に対してAさんが控訴したところ、控訴審の裁判所は、「危険運転致死罪という重大事件として起訴がされるまでの捜査の全過程を通じ、弁護人が選任されていないという状況の下、被告人の安定しない供述経過や供述内容には、被告人にうかがわれる投げやりな気持ちに基づく迎合的な供述傾向の影響があり、自白調書の信用性判断においても、このことが大きな影を落とすことは避けられないというべきである。そうすると、対面信号機の赤色信号の殊更無視を認めた自白調書の供述記載については、本件事故時の被告人の認識を正確に表現したものではない可能性があるといわざるを得ない。」と判示して、Aさんの捜査段階の自白調書の信用性を否定しました。そして、第一審の判決について「自白調書の信用性を肯定し、これに依拠して危険運転致死の事実を認めた原判決は、事実認定を誤ったもので是認でき」ないとしてこれを破棄し、Aさんに対して、過失運転致死罪が成立するにとどまることを前提に、禁錮3年(執行猶予5年)の判決を言い渡しました。
【掲載誌】
令和元年10月3日 大阪地方裁判所判決(判例時報2476号108頁)
令和2年7月3日 大阪高等裁判所判決(判例時報2476号102頁)
取調べの問題事例 事例7
コンビニエンスストアで現金を奪ったとの嫌疑で逮捕・勾留された後に窃盗罪で起訴され、302日間の身体拘束を受けたが、無罪判決が言い渡され、事件発生から10年後に捜査機関が誤認逮捕であることを認めて謝罪した事案(2014年、窃盗被告事件)。
- 概要を見る
-
Aさん(当時20代男性)は、約2か月前に自宅近所のコンビニエンスストアで発生した強盗事件の犯人であるとの疑いをかけられ、ある日、突然逮捕されました。Aさんには身に覚えがないことであったため、自分は犯人ではないと説明しましたが、検察官はAさんの勾留を請求し、裁判所はこれを認めました。
Aさんは、両親が依頼した弁護人の助言を受けて、取調べに対しては一貫して黙秘する方針をとりました。
警察官は、黙秘権を行使すると述べているAさんに対して、連日長時間の取調べを行い、顔を近づけて、大声で「おまえがやったんやろ!」「クズが!」「警察なめたらあかん」等の暴言を繰り返すなどして、執拗に「自白」を強要しました。Aさんは、暴言を繰り返す警察官に対して、取調べを録音・録画してほしいと頼みましたが、認められませんでした。
その後、検察官はAさんを窃盗罪で起訴し、保釈が許可されるまでの302日間にも及ぶ身体拘束が続きました。
裁判において、検察官は、コンビニエンスストアの店員の目撃証言や、防犯カメラ映像(犯人の画像とAさんが類似しているというもの)、Aさんの指紋がコンビニエンスストア出入口の自動ドアのガラス面から採取されたこと等を理由に、Aさんが犯人であると主張しました。
裁判所は、店員の目撃証言や防犯カメラの映像といった状況証拠を積み重ねてもAさんが犯人であると推認する力は高くないことや、Aさんの指紋は事件とは別の日に付着した可能性があること、さらには、Aさんには事件当時のアリバイ(自宅の部屋で友人と過ごしていたこと)を示す証拠があったこと等から、本件について「犯罪の証明がない」として、Aさんに無罪判決を言い渡しました(検察官は控訴せず判決は確定)。
無罪判決を受けたAさんは、警察および検察に対し、誤って逮捕したことについて謝罪を求めましたが、一切応じられることはありませんでした。
ところが、事件発生から約10年が経過した後、警察が、ようやくAさんを誤認逮捕したことを正式に認め、謝罪しました。警察が、改めて現場に残された指紋を登録システムで照会したところ、レジカウンター付近に落ちていたポリ袋に付着していた指紋がAさんとは別の男性の指紋と一致することが判明し、その男性から任意で事情聴取したところ、容疑が固まったことから、その男性を改めて窃盗容疑で書類送検したという経緯を受けた対応でした。ちなみに、事件から長期間経過しており、窃盗罪の時効期間(7年)を過ぎてしまっていたことから、上記男性については不起訴処分となっています。
【掲載誌】
平成26年7月8日 大阪地方裁判所岸和田支部判決(LLI/DB判例秘書登載)
取調べの問題事例 事例8
警察官が、余罪である強盗事件について、黙秘権を侵害し自白を強要する発言を繰り返したことにつき苦情を申し入れた結果、検察官および県警察本部から注意がなされた事案(2020年、窃盗被告事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、窃盗事件で逮捕・勾留され、その後、起訴されました。
起訴後、裁判官が、Aさんの保釈を許可する決定を行ったところ、警察官XおよびYは、身体拘束の理由となっていた窃盗事件とは無関係の余罪(強盗事件)についての取調べを行いました。
Aさんが余罪について関与を否認すると、XおよびYは、黙秘権を侵害して自白を強要するような発言を繰り返しました。Aさんが、自身の弁護人に説明した内容によると、XおよびYは、「正直に言えや。」「話をしてないことがあるだろうが。」などと言って、Aさんに自白を迫りました。また、Aさんが、取調べに対して黙秘権を行使すると告げたことに対して、「人間として返事するのが当たり前やろうが。」「(保釈で)出るんだったらきれいになってから出た方がいいんちゃうか。」「本当のことを話さなくて子供にどうやって教えるんや。」「〇さんの質問に答えずに、〇さんの顔に泥を塗るんか。」などの発言を繰り返しました。さらに、強盗事件に関与していないAさんに対して、「(共犯者から)犯行後に車に乗せろと言われたのではないか。」、「(共犯者と)事前に約束していて現場に迎えに行くことになっていたのではないか。」、「犯行現場近くで女性の悲嗚を聞いたんじゃないか。」、「これまで窃盗は近くでやっていたのに、このときだけ遠い犯行現場にいたのはおかしい。」などと、Aさんが強盗事件の共犯者であると決めつけるような発言を繰り返しました。
Aさんが上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、XおよびYを監督する立場にある警察署長、県警察本部および検察官に対して、苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べの状況を調査するよう求めました。
その結果、県警察本部および検察官から、弁護人に対して、Aさんに対する取調べの実施方法について、XおよびYに対する注意喚起を行ったとの回答がなされました。
このような、Aさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
取調べの問題事例 事例9
警察官が、取調べで、被疑者の個人の性的なプライバシーを侵害する発言を繰り返した事案(2020年、覚醒剤取締法違反被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、当初、覚醒剤を所持していたとの被疑事実で逮捕・勾留されましたが、その後、さらに、覚醒剤を有償で譲り渡したという嫌疑でも、再逮捕・勾留されました。
Aさんは、性的少数者(マイノリティ)でした。
Aさんが自身の弁護人に説明した内容によると、Aさんの取調べを行った警察官Xは、覚醒剤の譲渡事件の捜査に必要であるなどと言って、Aさんの性行為の具体的方法や避妊具を使用するのか等といった、被疑事実と無関係かつ性的なプライバシーを侵害する質問(発言)を繰り返しました。さらに、それらの質問に対してAさんが回答を拒んだところ、Xは、「勾留が長くなる。」「再逮捕できる。」などと言って質問に答えないことで刑事手続で不利益を受けることを示唆したり、「共犯者と言っていることが違うから、合っているように話せ。」など、捜査機関が考えるとおりの説明(自白)をするように強要する発言がなされました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の捜査を監督する立場にある担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べの状況を調査するよう求めました。
その結果、検察庁から回答があり、上記のうち、XがAさんのプライバシーを侵害する発言をしていたことは確認できたとする一方、自白を強要する発言があったことは確認できなかったというものでした。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
その後、Aさんは、覚醒剤の所持罪でのみ起訴され、覚醒剤を譲り渡したという嫌疑で起訴されることはありませんでした。
取調べの問題事例 事例10
警察官が黙秘権を侵害して、自白を強要する発言を繰り返したことにつき苦情を申し入れた結果、検察官および公安委員会の調査により、発言の一部が確認され、注意がなされた事案(2022年、強要未遂被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、暴力団関係者と共謀して、飲食店に賭博のための遊技機を設置するように求める強要未遂事件を起こしたとの被疑事実で逮捕・勾留されました。
Aさんは、被疑事実がおよそ1年も前の事であり、記憶も定かでなかったことから、弁護人からの助言を受けて、黙秘権を行使していました。
Aさんが自身の弁護人に説明した内容によると、取調べを担当した警察官Xは、「この態度なら徹底的にやるからよ。」「今後別件とかで逮捕していくからよ。」「色々あるからな。俺が数えるだけでも○件はあるからな。」「マスコミに出たら大変なことになるな、仕事も家族も。」「家族、子どもが周りの人にお父さんはヤクザって言われるんだな。」など、黙秘をするAさんに対して、マスコミ等に暴力団と関係を持っているといった報道がなされて、家族にも迷惑がかかることを示唆するような言動を繰り返し、自白を強要しました。
Aさんが上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、Xを監督する立場にある警察署長、県警察本部、検察官および公安委員会に対して、苦情を申し入れるとともに、Aさんに対する取調べの状況を調査するよう求めました。
その結果、検察官から回答があり、上記のような発言があったことを確認し、Xに対して注意をしたとのことでした。また、公安委員会による調査が行われ、それによればAさんおよびXに対するヒアリングが実施され、Xが地元紙にAさんの名前が出ることで不利益が生じることを示唆するような発言をしたことを認めたとのことでした。
このような、Aさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
なお、弁護人が苦情申入れを行った翌日から、Aさんに対する取調べは実施されず、その後、Aさんは釈放されました。
取調べの問題事例 事例11
検察官が、黙秘権を行使する被疑者に対し、その尊厳を傷つける発言をして供述を迫った事案(2020年、保護責任者遺棄致死被告事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、未成熟子を出産後、必要な措置をとらずに死なせたという保護責任者遺棄致死の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんの取調べを行った検察官Yは、黙秘するAさんに対し、「亡くなった赤ちゃんに対する罪の意識はないのか」「仏壇に手を合わせられるのか」などと発言して供述するように迫りました。検察官Yの発言は、Aさんに保障されている黙秘権の行使を不当に妨害しようとする、極めて悪質なものでした。この取調べは、録音・録画されていたため、上記のような不当な発言があったことを、弁護人は、取調べ記録映像を視聴して確認しています。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、検察官の捜査を監督する立場にある担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べの状況を調査するよう求めました。
その結果、検察庁から回答があり、Yがそのような発言をしたことはあったが、供述するよう説得するための言動であり、問題ないと判断している、というものでした。
取調べの問題事例 事例12
警察官が、黙秘権を行使する被疑者に対し、暴言を吐いて供述を迫った事案(2020年、殺人被告事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは夫を殺害したとする殺人の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんの取調べを行った警察官Xは、黙秘するAさんに対し、「人一人殺して何を開き直っているのか」「黙秘しますで通ると思っているのか」「反省している奴が黙秘なんてしないんだ」「黙秘する権利なんかない」「逃げんじゃねえ」「黙秘することは卑怯だ」「人一人殺しておいて何が黙秘だ」「人殺しなんだから反省しろ」「黙秘なんて言葉に逃げるんじゃない」「黙秘は反省していたらできない」などと暴言を吐き、供述するよう迫りました。さらに、体調不良を訴えるAさんに対し、Xは「取調べなんか苦しくて当然」という趣旨の発言をしました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の捜査を監督する立場にある担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べの状況を調査するよう求めました。
その結果、検察官は取調べ録音・録画を確認し、「確かに行き過ぎた言動があった」と回答しました。
取調べの問題事例 事例13
検察官が、供述調書への署名を拒否する被疑者に対し、署名するよう迫った事案(2020年、窃盗被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは転売目的で万引きをしたという窃盗の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんの取調べを行った検察官Yは、供述調書への署名・指印を拒否したAさんに対し、「署名しないのは否認しているのと同じだ」と述べ、署名・指印をするように迫りました。その結果、Aさんは強い恐怖を感じ、供述調書に署名・指印をしました。なお、Aさんはもともと、窃盗の事実を認めており、被害者に対して示談の申入れをしていました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、検察官の捜査を監督する立場にある担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べの状況を調査するよう求めました。
その結果、検察庁は取調べ録音・録画を確認し、実際にYがそのような発言をしたことがあったと認めました。さらに、Yの発言により署名・指印をしてしまった供述調書については証拠として請求しない予定であると回答しました。
Aさんは、この万引き事件については処分保留で釈放されました。
取調べの問題事例 事例14
警察官および検察官が、黙秘し供述調書への署名を拒否する被疑者に対し、その権利行使を非難し供述や署名・指印を迫った事案(2020年、不正アクセス被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんの取調べを行った検察官Yは、取調べに対して黙秘をし、供述調書への署名・指印を拒否したAさんに対し「捜査機関をなめているのか」「なぜ署名・指印を拒否するのか」などと権利行使が許されないかのような発言しました。Aさんの取調べを行った警察官Xも同様に、「黙秘権等の行使は公判において被疑者の不利益になる」などと、Aさんが黙秘することや供述調書への署名・指印を拒否することが、Aさんにとって不利益になるという趣旨の発言をし、Aさんが供述していない内容の供述調書に署名・指印をするよう迫りました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、担当検察庁宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、上席検察官および次席検事が、取調べの録音・録画を確認し、申入れどおりの事実が概ね認められたとして、改善を約束する旨の回答がありました。同時に警察官に対しても改善を指導するとの約束がなされました。
取調べの問題事例 事例15
警察官が、長時間の取調べを行い、供述を迫った事案(2021年、暴行被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは同居する成人した子どもに対する暴行(DV)の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんには適応障害、抑うつ状態等の精神疾患がありました。
Aさんの取調べを行った警察官Xは、Aさんを逮捕する前に、午後3時から午後11時までAさんを参考人として取り調べました。その後、同日午後11時にAさんを逮捕した後も翌午前4時まで取調べを続けました。
また、精神疾患があると説明するAさんに対し、Xは「精神障害者手帳はないの?手帳は?」と高圧的に述べて、あしらいました。
さらに、Aさんが勾留された後の取調べにおいて、Aさんが黙秘すると、Xは「弁護人に言われたの」「なんでそんなことするの」などと言い、供述するよう迫りました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、担当検察庁宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、申入れに対し、主任検察官から回答がありました。弁護人が指摘する言動はあったが、威圧的な態度などはとっていない、ただし検察官から被疑者の特性や黙秘権に配慮するよう指導した、との回答でした。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
Aさんは、略式請求により罰金刑になりました。
取調べの問題事例 事例16
警察官が、「てめえやったんだろ」などと威圧的な発言をして余罪の供述を強要した事案(2021年、窃盗被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは特殊詐欺の受け子をしたという窃盗の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんの取調べを行った警察官Xは、Aさんの交通系ICカードの履歴を示し、余罪について「てめえやったんだろ」「早く言えよ」などと迫りました。Aさんが「覚えていない」と答えると、「とぼけんじゃねえ」「どうせ覚えてんだろ」などと発言しました。さらに、Aさんが「覚えていないことを覚えてない」と言うと、Xは「てめえふざけんなよ」「しらばっくれるな」「どうせもっとやってんだろ」「お前今年やったんだから覚えてんだろ」「弁護士にどうせ否定しろとか言われたんだろ」「反省してねえじゃねえか」などと繰り返し発言して自白を迫りました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の取調べを監督する立場である担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、申入れに対する回答はありませんでしたが、取調べを担当する警察官が交代しました。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
取調べの問題事例 事例17
警察官が、虚偽ないし不正確な事実を告知して供述を強要した事案(2021年、詐欺被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは偽ブランド品のバッグを販売したという詐欺の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんはパニック障害および逆流性食道炎という疾患を有していました。
Aさんは、警察官による取調べの際、パニック発作ないしパニック症状を起こし、泣き叫ぶ等の状態になりました。しかし、取調べを担当した警察官Xは、Aさんの疾患に配慮せず、黙秘権を行使するAさんに対し、「都合が悪くなると黙秘する」「民事事件で、(携帯電話が押収されているのに、紛失しているなどと)虚偽の陳述をした」「嘘をついている」「真実を言わなかった」などと告げて、民事事件において虚偽の陳述をしたために、Aさんが処罰されるかのような虚偽ないし不正確な事実を告知し、被疑者が取調べにおいて供述しなければならないと誤解させて供述を強要しました。さらに、この取調べにおいて、Xは、Aさんが供述を拒否しているのに、一方的に、Aさんが供述していないことを勝手にまとめた供述調書を作成しました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の取調べを監督する立場である担当警察署の署長や担当検察庁の検察官宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、Aさんに対するその後の取調べはされず、Aさんは嫌疑不十分で不起訴になりました。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
取調べの問題事例 事例18
警察官が、被疑者の家族に働きかけて供述を強要した事案(2021年、傷害被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは被害者に対し加療1週間の怪我を負わせたという傷害の嫌疑で、逮捕・勾留されました。Aさんは傷害の事実を一部否認していました。
Aさんは、取調べに対して黙秘していました。Aさんの捜査を担当している警察官Xは、Aさんの母親に対し、「A氏が素直に話さないから勾留が長引く」「弁護士がどういうアドバイスをするかわからないが、犯行を認めるようお母さんから言ってほしい」などと告げました。Aさんの母親とAさんは、Xのこの発言によって、今後の取調べでも、警察が指示する内容どおりに認めれば早く帰れるという趣旨の発言をされるのではないかと不安になりました。
さらにXは、Aさんの母親に対し、真実は加療1週間とされている怪我について「相当な怪我を負わせている」と告げ、また、自白するよう働きかけて供述を強要しました。
Aさんの母親が、上記のような発言をされたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の取調べを監督する立場である担当警察署の署長や担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、Aさんの家族に対する事情聴取は行われなくなりました。
このようなAさん母親に対する発言や働きかけは、録音・録画が実施されることなく行われています。
取調べの問題事例 事例19
警察官が、「客観証拠は出ている」と自白を強要し、「私たちと弁護士、どちらを信じるのか」などと発言した事案(2021年、強制性交被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは知人の恋人に対する強制性交等の嫌疑で、逮捕・勾留されました。Aさんは被疑事実を否認していました。
取調べ担当の警察官Xは、「友達に相談して弁護士を選んだ方がいいんじゃないか」「私たちと弁護士、どちらを信じるのか」などと発言して、弁護人とAさんとの信頼関係を積極的に破壊しようとしました。
また、黙秘をしようとしたAさんに対し、Xは「何の意味があって、黙っているのか」「家族のことを考えるんだったらどういう対応した方がいいか考えた方がよい」「客観的証拠は出ている。そのまんまでいいんですか」「私はどっちでもいいし、しゃべらなくてもいいけどAさんのことを考えたらそのまんまでいいのかな」などと述べ、黙秘をすることで不利益が生ずるかのような説明をし、供述を強要しました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の取調べを監督する立場である担当警察署の署長宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、取調べ担当の警察官が交代し、Aさんは不起訴となりました。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画が実施されることなく行われています。
取調べの問題事例 事例20
特捜部の検察官が、黙秘権を行使する被疑者に対し、1か月以上にわたり、連日、長時間、脅迫的文言を繰り返した事案(2021年、詐欺、会社法違反被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは数億円の詐欺と背任の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
黙秘するAさんに対し、取調べ担当の検察官Yは、1か月以上にわたり連日長時間の取調べを行いました。
Yは、Aさんに対し、「黙秘は検察に対して喧嘩を売っている」「徹底的にやる」「反省が見えない」「刑務所に行くことが確定」「再逮捕もあり得る」「子供が微妙な時期で心配だ」「反社と同じ」「検察の上は本当に冷たい奴だから黙秘なのねと淡々と100件でも立件する」「皆を敵に回してあなたは有罪となる」「罪状からしたら1件で10年、2件で15年」「自首してくる人間は適正に配慮する」「再逮捕されたらまたマスコミにも報道される」「1年から2年は今のままでそこから出れずに裁判受けてそのまま刑務所に行く」「我々の知らないことまで話をしたらやっとプラスマイナスゼロになる」「われわれ捜査のことをなめてる」「俺の言っていることは信用できないのか」「どうせ話しても嘘を話すのだろうけど」「保釈は絶対に無理」「そのまま裁判で相当に重い罪になる」「たちの悪いやくざの親分のようだ」「黙秘では裁判で大きな恥をかく」「麻薬の密売人の親分でさえ必死になって最後は俺に話していた」「いずれにしても必死にならないとだめだ」「とにかく全てを話して検察に任せなさい」「今後どれだけ立件していくか想像もつかない」「求刑を決めるのも我々だ」「私自身が本当に反省してるんだと思わせることをしないと人生台無しになる」などと脅し、黙秘していることを責め、供述を強要しました。また、有罪が決まっている、実刑になることが決まっているかのような発言もしました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、検察官の取調べを監督する立場である担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画が実施された状態で行われています。
取調べの問題事例 事例21
検察官が、黙秘権を行使する被疑者に対し、事件関係者から被疑者宛てに手紙を書かせ、それを見せながら取調べを行い、供述を強要した事案(2021年、窃盗被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは車上荒らしを行ったという窃盗の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんは取調べに対して黙秘していました。取調べ担当の検察官Yは、逮捕・勾留中の事件関係者甲のところに赴き、Aさん宛ての手紙を書かせ、それを証拠品として預かりました。Yは、Aさんの取調べで「私が接見禁止をつけたのに、手紙というのはあり得ないんだけど、甲さんがどうしてもと言うので、とりあえず証拠品として採用し、その中身から私が抜粋したものを読み上げます」と告げて、その手紙を読み上げました。手紙の内容は、「自分の口から責任を取れ」「Y検事に素直に話したほうがいい」というものであり、Aさんに供述することを強要しました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、検察官の取調べを監督する立場である担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、苦情に対する回答はありませんでしたが、Aさんは不起訴になりました。
取調べの問題事例 事例22
警察官が、人格を蹂躙する性的な発言を繰り返すなどして、供述を強要した事案(2021年、殺人被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、出産直後の子を殺害したという殺人の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
Aさんは風俗店で働いていました。
取調べに対して黙秘しているAさんに対し、取調べ担当の警察官Xは、「黙秘をすることは本当に無責任だ。現実から逃げている」「事件に向き合おうとしていない」「赤ちゃんがかわいそう」「何の力もない赤ちゃんの人生を奪う権利なんてなかったよね」「赤ちゃんの人生はなくなったのにあなたの人生はあるからね」「黙秘権というのは与えられた権利だけど、一人の人間としてどうかと思うよ」などと怒鳴って供述を強要しました。
この事件では、弁護人が選任される前の別事件の取調べにおいても、Xは、「自分は風俗店の捜査をしたこともあるけど、(風俗で働く女性は)性行為が好きだからやってるんだよね」「ガリガリだからふっくらした方が男は好きだよ」「首を締められると興奮するんでしょ」などとAさんを侮辱するような発言しました。さらに、腰紐がきついか問われて大丈夫と答えたAさんに対して、「そうだよね、縛られるの好きだもんね」などと、Aさんの人格を蹂躙する性的な発言を繰り返しました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、検察官の取調べを監督する立場である担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めましたが、回答はありませんでした。
このようなAさんに対する取調べは、録音録画が行われた状態でなされています。
取調べの問題事例 事例23
警察官の取調べ中、通訳人が、黙秘権を行使する被疑者に対して供述するよう、被疑者を殊更に不安にさせるような発言をした事案(2020年、出入国管理及び難民認定法違反被疑事件)。
- 概要を見る
-
ベトナム人のAさんは、出入国管理及び難民認定法反の嫌疑で、逮捕・勾留されました。
取調べに対して黙秘しているAさんに対し、取調べにおけるベトナム語の通訳人は、警察官がそのような発言をしていないにもかかわらず、「ずっとこの状態だと外にも出られないよ」「日本の警察は親切でベトナムの警察のように拷問とかはしないから話して」などと供述するようまくし立てました。Aさんは動揺し、不安になり供述してしまいました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の取調べを監督する立場である担当検察庁の検事正宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べを改善するよう求めました。
その結果、通訳人は変更され、検察官から、通訳人に対し勝手に話さないように注意したとの回答がありました。
取調べの問題事例 事例24
警察官が、事実を否認する被疑者に対して認めたほうが有利になるかのように発言して自白を強要し、さらに、弁護人の選任について非難するなどした事案(2021年、商標法違反被疑事件)。
- 概要を見る
-
会社の代表であるAさんは、偽ブランド品を販売したという商標法違反の嫌疑で、任意の取調べを受けていました。
Aさんの取調べを担当した警察官Xは、事実を否認しているAさんに対し、
「この事件、すぐに終わらせたい。否認を続けるのもいいんだけど、取調べが長くなるし、それによって、こちらの対応も変わる」「裁判官がどう捉えるかってのを、考えたほうがいい。本物とつっぱね続けるのか、ごめんなさい、もうしませんっていくのか、どういう身の振り方をしたいのか。」などと否認すると不利益になり、認めれば早く終るかのような発言をしました。また、「●●警察署(注:捜査をしている警察署のこと)は在宅でやってるけど、他の警察はわからないよ」と、否認を続ければ別件で逮捕されるかのように脅しました。
さらにKは、「商標法って、初犯から実刑いくわけでもないし、裁判で罰金でも弁護士費用の方が高いから、なぜつけたのか不思議に思った。計算できてるのかな」「なぜ東京の弁護士なの」などと、弁護人の選任について非難するような発言をしました。
Aさんは、このようなXの発言によって恐怖を感じ、泣きじゃくりましたが、その際もXはAさんに対し、なお認めるように迫りました。
Aさんが、上記のような取調べを受けたことを弁護人に相談したことから、弁護人は、警察官の取調べを監督する立場である捜査担当の警察署長および公安委員会委員長宛てに苦情を申し出るとともに、Aさんに対する取調べの改善をするよう求めました。
その結果、公安委員会から、一部弁護人選任に関して配慮に欠ける点が認められたとの回答がありました。
このようなAさんに対する取調べは、録音・録画されることなく行われています。
取調べの問題事例 事例25
<取調べ音声を聴けます>
警察官が、任意の取調べにおいて、事実を否認し、ときに黙り込む被疑者を恫喝して自白を強要したことについて、裁判所が国家賠償請求訴訟で担当警察官の行為の違法性を認め、当該被疑者に対する慰謝料の支払を命じた事案(2017年、窃盗被疑事件)。
- 概要を見る
-
Aさんは、従業員として働いていた店舗の売上金を盗んだという窃盗の疑いで、任意の取調べを受けていました。
Aさんの取調べを担当した警察官Xは、黙秘権を告知せず、事実を否認しているAさんに対し、以下のように犯人であると決めつけ、否認することを非難して自白を迫りました。
「お見通しで物言うとんのにふざけるなって。否認しとったら通っていくと思うとったら、もうふざけるな。自分がやってきたことをよう思い返せ、今まで。そんな甘ないがね。」
「取ってないとは何や。自分が何やってきた、今まで。何も知らんと思うとんの?こっちが。」
「やってないってどの口が言うとんねやって怒ってやりたくなるんやわ、こっちは。泥棒が何言うとんねんってなってくんねん、こっち。」
「じゃあ、誰が取った?誰が取ったの?あんたしかおらへんがな。」
「当たり前や、そんなもんわかっとるやん。さっきまでの話は何なん。ええって、何を今驚いてんの。何を今驚いてるの。何を驚いてるの。驚くとこと違うやんかね。驚くとこ?これ。ええって、今さら。驚くとこ違うやろ?何言うとんの。驚くとこかい?何なん、その演技。」
「犯人やないかお前が。誰がおんのや、ほかに。ええかげんにせえ。」
「顔見とったらわかるわな、泥棒みたいなもん。泥棒!!!」
さらにXは、Aさんが否認することで自分に迷惑が掛かっているなどと言い、捜査に掛かった費用をAさんに請求できるかのように脅しました。
「わかっとって、物言いとんな。うそつき。ばればれやないか、お前みたいなもん、うそ。都合悪うなったら、物言わんと。物言うたと思ったら、わかりません。社長に聞いてもうたらどうですかて、知らんがね、んなもん。お前が答えろや。お前のことやろ。お前の人生やろ。こんなことでお前の人生に俺を関わらすな。迷惑な。いつまで俺に迷惑掛けとる。他人やぞ、俺。この事件担当した他人やぞ。何様や。人に迷惑掛けて。俺にも迷惑掛けて。何様じゃあ。こんな時間、お前、税金掛かっとんねんぞ。おい、俺に給料発生しとんじゃ。電気も使うて、紙も使うて、お前の捜査に幾ら掛かっとると思うとる。全部請求するぞ、お前。」
また、Xは、質問に対して黙り込むAさんに対し、以下のように脅して自白を迫りました。
「おい、何か言うたらどうや?黙秘か?黙秘権を行使しとんのか?そんなもん、泥棒に黙秘権あるか。おい。終わらへんに、いつまでたっても。ああ?終わらんぞ。おおい。終わらんぞ。終わらんぞ。終わらんぞ。」
「何しとんねや。おい。ふざけに来とんか、われ。おい。何しに来とんのや、われ。きっちり責任とれや。おい。」
Aさんは、その後不起訴になりました。
Aさんは、このような取調べによって精神的苦痛を受けたとして国家賠償請求訴訟を提起しました。その結果、裁判所は、「本件取調べは、社会通念上相当と認められる限度を超えた態様で行われており、その内容としては、原告の黙秘権を侵害し、原告の人格を繰り返し否定するものであり、全体として社会通念上相当な方法および限度を逸脱したものであって、国賠法1条1項の適用上、違法である」と判断しました。
このようなAさんに対する取調べは、捜査機関による録音・録画がされることなく行われています。本件は、Aさん自身が、弁護士Bの助言により、本件取調べを録音していたことから、明らかになりました。
【掲載誌】
令和4年3月10日 津地方裁判所判決(LLI/DB判例秘書登載)
【本件取調べの音声】
*本動画(音声)は合計7時間21分の取調べの一部を抜粋・編集したものです。
*警察官が罵声を浴びせるなどの過激な音声が含まれています。苦手な方は視聴をお控えください。
*複写・複製・転載を禁止します。