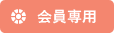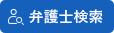語句解説
裁判員制度の説明によく出てくる語句について説明します。
裁判員の職務内容等
対象事件
- 解説
-
死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪(ただし、刑法第77条の罪を除く)又は、法定合議事件(短期1年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪の事件の一部)であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪のものが対象となります。
裁判員やその親族の生命・身体に危害が加えられる虞がある場合(例えばテロ事件など)、裁判員裁判の対象事件であっても、裁判官のみで審理することがあります。
合議体の構成
- 解説
-
合議体は原則として、裁判官3人、裁判員6人で構成されることになっています。
被告人が公訴事実を認めている場合には、検察官、被告人及び弁護人に異議がなく、また、事件の性質を考えて相当と認めるとき、裁判所は、裁判官1人、裁判員4人の合議体で審理することを決定することもできます。
裁判員、補充裁判員の権限
- 解説
-
裁判員は、有罪・無罪の決定及び刑の量定に関し、審理及び裁判をします。また、審理において、裁判長に告げて、証人を尋問し、被告人の供述を求めることができます。
補充裁判員は、審理に立ち会い、審理中に合議体の裁判員が欠けた場合に、これに代わって、その合議体に加わります。合議体に加わる前であっても、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができ、また、評議に出席することもできますが、裁判官が認めない限り、意見を述べることはできません。
裁判員及び補充裁判員の解任
- 解説
-
裁判員又は補充裁判員が前述の義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないと認められるとき、裁判官はそれらの者の解任を決定することができます。また、裁判員又は補充裁判員がその資格を有しないことが明らかになった場合も同様です。
公判期日の指定
- 解説
-
審理に2日以上を要する事件については、出来る限り連日開廷し、継続して審理が行われます。そのため、公判が始まる前に、準備手続において検察官、弁護人によって争点整理がなされ、審理に要する見込み時間(日数)が明らかにされることになっています。
宣誓
- 解説
-
選任された裁判員および補充裁判員は、裁判官から裁判員および補充裁判員の権限、義務その他必要な事項の説明を受け、宣誓をします。
評決
- 解説
-
有罪とする場合評決は単純過半数です。ただし、裁判官の1名以上および裁判員の1名以上が賛成する意見によらなければなりません。
判決書
- 解説
-
判決書は評議の結果に基づいて裁判官が作成します。判決書には裁判官のみが署名押印し、裁判員の身分・任務は判決宣告時に終了します。
控訴審
- 解説
-
裁判員は第一審の裁判にのみ関与し、控訴審は職業裁判官だけで行われます。
裁判員の選び方
裁判員の要件
- 解説
-
衆議院議員の選挙権を有する者(18歳以上)が裁判員に選ばれることができます。
欠格事由
- 解説
-
中学校を卒業していない人(ただし、中学校卒業と同等以上の学識を有する場合は、欠格事由になりませ ん。)、禁錮以上の刑に処せられた人、心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある人は、裁判員になることができません。
就職禁止事由
- 解説
-
法律の専門家(裁判官、検察官、弁護士、法律学の教授など)や国会議員、国務大臣、行政機関の幹部は裁判員になることを制限されます。政府によれば、これらの人が除かれる理由は、国民の社会常識を反映させるという裁判員制度の趣旨や三権分立の観点を考慮したもの、と説明されています。その他、自衛官なども裁判員になることができません。
また、禁錮以上の刑に当たる罪で起訴されている人、逮捕または勾留されている人も裁判員になることはできません。
事件に関連する不適格事由
- 解説
-
公平な裁判所による裁判を実現するためには、事件の当事者や事件自体と関係のある人が裁判員に選ばれてはなりません。被告人や被害者、その親族などは、その事件の裁判員になることができません。
辞退事由
- 解説
-
70歳以上の人や学生、生徒、会期中の地方公共団体の議員は裁判員に選ばれても辞退することができます。その他にやむを得ない事由(例えば、重い病気で裁判所に行くことが困難な人や、介護または育児で家を離れられない人など)がある場合、裁判所が認めれば辞退することができます。
裁判員候補者名簿
- 解説
-
裁判員候補者名簿は、選挙人名簿をもとに、毎年、くじで選定して作成されます。
裁判員候補者の呼出し
- 解説
-
裁判員は、有罪・無罪の決定及び刑の量定に関し、審理および裁判をします。また、審理において、裁判長に告げて、証人を尋問し、被告人の裁判所は、公判期日が決まると、必要な数の裁判員候補者を、裁判員候補者名簿からくじで選定します。そして、質問手続を行う期日を定めて、裁判員候補者を裁判所に召喚します。裁判員候補者には、事前に欠格事由等を確認するために、質問票が送付されます。この質問票に虚偽の回答をすると罰せられることがあります(後述)。
質問手続の日の2日前までに、召喚した裁判員候補者の氏名を記載した名簿が、検察官と弁護人に開示されます。そして、裁判所は、質問手続の日、その手続が行われる前に、裁判員候補者の質問票に対する回答の写しを、検察官と弁護人に閲覧させることができます。
裁判員候補者の義務
- 解説
-
裁判員候補者は、呼出状で指定された質問手続期日に出頭する必要があります。また、送付された質問票または裁判所における質問手続において、虚偽の回答をしたり、正当な理由なく質問に対する回答を拒むことはできません。
裁判員および補充裁判員となるに当たっては、宣誓をします。
裁判員および補充裁判員は、法令に従い誠実にその職務を行わなければなりません。裁判員は、職務に就いている間、職務終了後を通じて、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為はできません。また、評議の経過や裁判官、裁判員それぞれの意見、その多少の数など職務上知り得た秘密を漏らすことは禁じられます。
質問手続
- 解説
-
裁判員候補者に対する質問手続には、裁判官および裁判所書記官、検察官、弁護人が出席して行われます。裁判官が必要と認める場合には、被告人が同席することもあります。この手続は非公開で行われます。
質問手続では、裁判官が、裁判員候補者に対して、欠格事由やその他の裁判員の資格に関する事由の有無を確認するために質問を行います。検察官、被告人または弁護人は、裁判員候補者に必要な事項を質問したい場合には、裁判官に質問を求めることができます。裁判官は、相当と認める場合には、この求めに応じて裁判員候補者に質問を行います。
この制度は、当事者それぞれが納得できる裁判員の構成となるようにとの趣旨で設けられました。当事者は、質問手続の結果などをもとにして、請求をするかどうかを決めます。当事者(検察官、被告人または弁護人)は、それぞれ4人につき理由を示さない不選任請求をすることができます。裁判官は、理由を示さない不選任請求があった裁判員候補者については選任しない決定をすることになります。
公平さについての不適格事由、理由を示さない不選任請求
- 解説
-
公平な裁判を実現するために、当事者からの申立て等によって不公平な裁判をするおそれのある者を裁判員の職務から排除する制度があります。当事者は質問手続において、それぞれ4人まで理由を示さずに不選任請求することができます。
裁判員に対する補償
- 解説
-
裁判員、補充裁判員および召喚に応じ出頭した裁判員候補者に対しては、旅費、日当および宿泊料が支給されます。また、裁判員等が、その職務に関して負傷等をした場合には補償されることになっています。
罰則等
罰則
- 解説
-
裁判員、補充裁判員となった方には、守っていただかなければならない事項があります。それらに違反した場合には、罰則が課せられることがあります。また、裁判員、補充裁判員に不当な影響を与える行為にも罰則が課せられます。
裁判員等の不出頭
- 解説
-
呼出しを受けた裁判員候補者、裁判員または補充裁判員が正当な理由なく出頭しないときは、過料に処せられる場合があります。また正当な理由なく宣誓を拒んだ場合にも同様です。
裁判員等の秘密漏洩罪
- 解説
-
裁判員、補充裁判員またはこれらの職にあった者が、評議の経過もしくは各裁判官もしくは各裁判員の意見もしくはその多少の数その他の職務上知り得た秘密を漏らし、または合議体の裁判官および他の裁判員以外の者に対しその担当する事件の事実の認定、刑の量定等に関する意見を述べたときには、懲役または罰金に処せられることがあります。
裁判員候補者の虚偽回答罪
- 解説
-
裁判員候補者が、自己に送付された質問票または裁判所における質問手続において、虚偽の回答をし、または正当な理由なく質問に答えなかったときは、決定で、過料に処せられることがあります。虚偽の回答をした場合には、罰金になることもあります。
裁判員等に対する請託罪等
- 解説
-
裁判員または補充裁判員に対し、その職務に関し、請託した者は、懲役または罰金に処せられます。また、事件の審判に影響を及ぼす目的で、裁判員または補充裁判員に対し、その担当事件に関する意見を述べまたはその担当事件に関する情報を提供した者は懲役または罰金に処せられます。
裁判員等威迫罪
- 解説
-
裁判員、補充裁判員もしくはこれらの職にあった者もしくは裁判員候補者またはその親族に対し、面談、文書の送付、電話その他のいかなる方法によるかを問わず、その担当事件に関して、威迫の行為をした者は、懲役または罰金に処せられます。
裁判員の保護等のための仕組み
裁判員等の個人情報の保護
- 解説
-
裁判員、補充裁判員もしくはこれらの職にあった者もしくは裁判員候補者またはその親族に対し、面談、文書の送付、電話その他のいかなる方法によるかを問わず、その担当事件に関して、威迫の行為をした者は、懲役または罰金に処せられます。
裁判員等に対する接触の規制
- 解説
-
誰でも、裁判員又は補充裁判員に対して、その担当事件に関し、接触してはなりません。そして、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員であった者に対して、その担当事件に関し、接触することはできません。
裁判員又は補充裁判員に対し、接触すると疑うに足りる相当な理由があることは、被告人の保釈不許可事由及び接見禁止事由になります。また、裁判員又は補充裁判員に接触したことは保釈取消事由となります。
出頭の確保
- 解説
-
誰であっても、他人が裁判員となることを妨げることはできません。
労働者は、その事業主に申し出ることにより、裁判員の職務を行うために必要な範囲で休業(裁判員休業)ができます。事業主は、労働者から裁判員休業の申出があったときは、その申出を拒むことができません。
事業主は、労働者が裁判員休業申出をし、または裁判員休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。