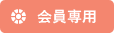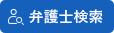「集団的消費者被害救済制度」の検討にあたっての意見
2011年5月13日
日本弁護士連合会
本意見書について
日弁連は、2011年5月13日付けで、「『集団的消費者被害救済制度』の検討にあたっての意見」をとりまとめ、同年5月27日、内閣府の消費者委員会の下に設置されている集団的消費者被害救済制度専門調査会(第10回)に提出しました。
意見書の趣旨
消費者委員会及びその下に設置された集団的消費者被害救済制度専門調査会における集合訴訟制度の今後の検討にあたっては、実効性のある制度が速やかに提言されるよう、特に下記の点につき留意して進められるとともに、平成24年通常国会において集団的消費者被害救済制度の導入が実現されることを求める。
記
- 制度の適用対象となる事案の類型
いわゆる二段階型を基本として集合訴訟制度を構築するのであれば、制度の対象となる事案につき、対象消費者の個々の損害額が定型的であるような事案などに限るべきではなく、そのような事案を中心としつつも、製造物責任被害事件や薬害事件など、重要な共通争点はあるが、他方個別争点の審理も一定程度求められる類型の事案についても適用対象に含みうるようにすること。
また、請求額についても、特段の金額上の制限は設けられるべきではないこと。
- 訴訟追行主体
いかなるタイプの集合訴訟制度を導入するにせよ、適切な訴訟追行が期待できる一定の主体に限り訴訟追行主体として認めることが適切であるが、現在の適格消費者団体だけでなく、例えば、相当数の被害者と複数の弁護士からなる弁護団で構成される被害者団体にも、適切な訴訟追行が期待できることが担保されておれば、訴訟追行主体として認めるようにすること。
なお、集合訴訟のための適格消費者団体の認定要件については、現在の差止請求を基本とする適格消費者団体の認定要件と基本的には同一のものとし、集合訴訟に関する業務の拡大に伴って必要となる規定の整備の範囲にとどめ、それ以上の特別の加重要件を設けないこととすること。
- 「総額判決」制度の導入
いわゆる二段階型を基本として集合訴訟制度を構築するものとしても、対象消費者の請求権の成否を一括して審理し、総員に対して支払うべき金額の総額について判決をするものとするオプトアウト方式を組み込んだ「総額判決」制度(いわゆるC案)についても、特に低額被害事案における実効的救済のために導入の検討をすすめること。
- 対象消費者への通知や公告の方法、費用負担
いかなるタイプの集合訴訟制度を導入するにせよ、通知や公告の具体的な在り方を検討するにあたっては、個々の事案の特徴を踏まえた柔軟な対応が可能な制度とすること。
また、通知等の費用のために制度の活用が阻害されることがないよう必要な手当が検討されるべきこと。
- 二段階型における二段階目の手続について
いわゆる二段階型における二段階目の手続については、対象消費者の手続への参加をより促す観点から、原則として通常訴訟よりも簡略な手続としつつ、慎重な審理を要するような対象消費者のケースのみ通常訴訟に移行して審理するという構造を基本として検討すること。
また、一段階目の訴訟追行主体の訴訟追行意欲を削ぐことの無いように、一段階目の訴訟追行主体の訴訟追行費用が適切にまかなわれる仕組みを設けること、及び二段階目においても一段階目の訴訟追行主体が引き続き重要な役割を果たしうるような仕組みとすること。
- 和解の在り方について
いかなるタイプの集合訴訟制度を導入するにせよ、適切な時期に適切な和解をなしうるような制度とすること。
この具体的な検討にあたっては、和解内容の妥当性確保のための具体的な方策とともに、一段階目において対象消費者の個々の請求権を束ねることを前提としない案(いわゆるA案)を前提とする場合には、一段階目の審理段階においても実効性のある和解がなし得るような方策についても検討すること。
- 集合訴訟の管轄裁判所について
集合訴訟制度の裁判管轄については、少なくとも実際に被害が生じている地を管轄する裁判所での審理が排除されないようにすること。
(※本文はPDFファイルをご覧ください)