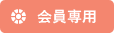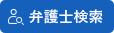区分所有法の改正に関する要望書
日弁連総第6号
2001(平成13)年5月16日
法務大臣
森山 眞弓 殿
法制審議会 長
竹下 守夫 殿
区分所有法の改正に関する要望書
日本弁護士連合会
会長 久保井一匡
貴殿におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当連合会におきましては、一昨年から『建物の区分所有等に関する法律』(以下「区分所有法」という。)の改正の要否、必要とされる改正点について検討を開始し、昨年6月16日に別添の『区分所有法の改正に関する意見書』(以下「日弁連意見書」という。)を対外的に公表いたしました。
ところで、日弁連意見書において改正を要する点、改正の方向として指摘した事項は多岐にわたり、また、具体的な意見として指摘できなかった課題も多く残されていました。しかし、社会的にも注目を集めていた管理会社の問題については、さっそく昨年12月に『マンションの適正な管理の推進に関する法律』が成立し、その限りで日弁連意見書における指摘事項が一部実現される運びとなりつつあります(別添意見書第6の3、4)が、その余の指摘事項については、実現化への機会をみないまま今日に至っております。
このたび法制審議会においては、区分所有法の改正問題が検討の俎上にのせられる旨聞き及びましたが、前回の昭和58年の区分所有法改正から既に17年が経過し、その間に膨大な数の区分所有建物、いわゆるマンションが分譲され、わが国民に普遍的な居住形態となっています。他方で、かかる普遍化に伴い大量の老朽化マンションが出現し、分譲時には顕在化していなかったいびつな売り方に起因する問題が多発し、購入者の団体でもある管理組合にとって、重い十字架となって困難な訴訟問題となっております。平成7年の阪神・淡路大震災は、建替問題にみられるように、制度上の不備を現実化させています。さらにまた、例えば管理組合の原告適格のように、前回の法改正ではあまり意識されていなかった制度的な不備の問題についても、訴訟の激増とともに、裁判実務上の緊急の課題となってきています。
前回の昭和58年の法改正は、主として登記実務の側から提起された改正だったといわれておりますが、今回の法改正では、居住形態として既に定着しているマンションの購入者、及び居住者の意識された問題点について、下記の諸点を是非検討項目に取り上げていただきたく、要望いたします。
第1 専有部分と共用部分について
1. 共用部分の登記について
共用部分については、登記書類に各階平面図など図面を添付させるなどの方策を採り、区分所有者らに、専有部分と共用部分を明確に区分けして認識できるようにすることによって、分譲後の共用部分の維持、管理の範囲を明確にすべきである。
2. 規約による例外条項について
共用部分の割合、処分、管理の決議、管理費について、規約で別段の定めができることから生じる弊害について、是正措置を講じることを検討事項とすべきである。
3. 共用部分の変更に関する決議要件について
共用部分の管理の変更決議について、不合理な反対に代わる許可の裁判の導入、ないしは現行の4分の3を3分の2に減少させることについても検討事項とすべきである。
第2 敷地利用権について
1. 専有部分と敷地利用権との分離処分禁止の例外規定の改正について
専有部分と敷地利用権との分離処分禁止の原則に関する例外規定(22条1項ただし書、「ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りではない。」)については、必要と認められる例外事由を、例えば、下記のように限定列挙する方法に改正されるべきである。
限定列挙の事由
- 棟割長屋等の区分所有建物において、一棟の建物の敷地を専有部分の底地ごとに別筆としているとき
- 共有地上の小規模区分所有建物の場合
2. 敷地利用権の割合に関する例外規定について
(区分所有者が数個の専有部分を所有する場合における各専有部分の敷地利用権の割合に関する例外規定の改正について)
区分所有者が数個の専有部分を所有する場合における各専有部分の敷地利用権の割合(区画の内側線で囲まれた専有部分の床面積の割合)に関する例外規定(22条2項ただし書、「ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。」)は、専有部分の床面積割合の複雑な数値を避け、わかり易い割合を定めるため、買受人の不利益・不公平感を招かない程度の端数処理をする場合にのみ適用される旨、改正されるべきである。
第3 規約について
1. 原始規約の問題について
以下のような改正の方策を検討すべきである。
- 原始規約について、行政庁による審査手続を新設し、行政庁に不公正条項について、改正命令ないしは改正勧告権限を与える。
- 分譲業者や等価交換方式の元地主に対して特別な利益を与えるような不平等条項については、無効とする規定を設ける。
- 分譲業者や等価交換方式の元地主作成の原始規約に限っては、過半数決議で改正することができることとし、この場合には「特別の影響」の規定は適用しないものとする。
2. 不公正な分譲方法に対する禁止条項の新設について
駐車場専用使用権の分譲、留保、無償の広告塔や袖看板などの不公正な分譲方法について、これを禁止する強行規定を新設すべきである。
第4 敷地の同一性の確保について
(建築確認敷地と登記敷地との同一性確保)
建築確認上敷地として表示された敷地と区分所有建物登記上の敷地が同一であることを確保する制度を設けるべきである。
第5 マンションの管理について
1. 分譲後管理組合の理事長選任までの管理体制について
分譲後管理組合の設立までの管理体制については、分譲業者に責任を持たせる制度を確立すべきである。
2. 管理組合の法人化要件について
47条1項の法人化の要件のうち、区分所有者の数(30人以上)の要件は撤廃すべきである。
3. 管理組合の法制度化について
区分所有法において、法人格のない管理組合についても、理事会方式による管理方式を明文化すべきである。
4. 管理組合の当事者適格について
建物の共用部分、敷地の維持、管理に関する訴訟について、管理組合が当事者適格を有することを法律で定めるべきである。
第6 復旧・建替えについて
1. 復旧について
(1) 買取請求の相手方(61条7項)について
買取請求を受ける側の区分所有者が一定の者に集中しないように限定すべきである。
(2) 買取請求権行使の期限(61条7項)について
買取請求のなしうる期限を設けるべきである。
(3) 「時価」の算定方法(61条7項、同条8項、63条4項)について
算定基準や算定方法を定めるべきである。法61条8項は削除する方向で検討されるべきである。
2. 建替えについて
(1) 建替え決議の要件(62条1項)について
下記の要件を明確にする表現に改めるべきである。
-
「建物の価額その他の事情」
-
「効用を維持し、又は回復する」
-
「過分の費用」
(2) 建替え手続に協力的でない決議賛成者への対処方法について
建替え決議賛成者の建物明渡義務を明確にすべきである。
(3) 決議無効の提訴期限について
決議無効確認訴訟の提訴に期限を設けるべきである。
(4) 建替え決議後の区分所有者の地位について
建替え決議後の区分所有者の地位について、法律で明確にすべきである(条文の新設)。
その場合、建替え事業を目的とする団体(再建団体又は再建組合)の規定を置くとともに、大規模マンションの場合には再建組合の法人化の道を考慮すべきであり、あわせて再建組合員の権利の譲渡及びその承継人の義務の範囲等に関する関連規定も整備することが望ましい。
3. 区分所有法の適用範囲について
老朽化と地震等による損壊の場合は、別に規定すべきである。
第7 その余の検討課題
1. 現行の区分所有法は、第二章において「団地」に関する規定を設けている。しかしながら、その多くは第一章の「建物の区分所有」の規定を準用(読み替え)するものであり、かならずしも現実に即応しているとは言えず、実効性に乏しいと言わざるを得ない。
現行の区分所有法は、区分所有建物を一元的にとらえ、一律に規定を適用することをその前提としている。
しかしながら、現実の区分所有建物は、もっぱら居住用としての使用を前提とする、いわゆる分譲型マンションや、たとえば数社の企業が共同出資して建築する事業用ビル、さらには居住用マンションと営業店舗等の混在する複合型マンション等非常に多岐にわたっている。
このように多様な区分所有建物に対し,区分所有法を一律に適用することは無理があるのみならず、現実に合致しない場合がある。
したがって、区分所有建物の形態ごとに、場面に応じ個別的な規定を設ける必要がある。
3. 現行の区分所有法は、いわば民法の特別法として立法化されたものと位置付けることができよう。
ところで、たとえば分譲型マンションの場合で言えば、マンションの建築、販売、管理、補修そして建替えと、それぞれの場面において数々の問題があり、また紛争が発生している。これらの問題ないし紛争に、実定法としての現行区分所有法の規定のみでは十分に対処しきれていない。
もっと時間的,動態的視点に立った規定にする必要がある。とくにマンション等の復旧、建替え等については、かかる視点が是非とも必要である。
また、区分所有者のみをその対象とするのではなく、その場面に応じマンション関係する、例えば分譲業者や管理会社等の関係者をも対象とする法律の規定が必要である。区分所有法と一体のものとするか否かはともかく、宅建業法のような、いわば一種の業法も必要と考える。
4.マンションに関する種々の紛争解決のために、もしくは紛争の発生を防止するために、例えば、非訟事件手続を新設するなどして、裁判所等の機関による後見的制度を確立すべきである。