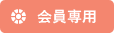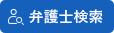日弁連新聞 第554号
ご挨拶~2年間の御礼~
日本弁護士連合会会長
菊地裕太郎
 2年間の任期中の会員の皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。
2年間の任期中の会員の皆さまのご支援・ご協力に心より感謝申し上げます。
日弁連の力の源泉は、100以上にも及ぶ各種委員会等にあります。各委員会が、司法のみならず社会全体の動きに鋭敏に目を凝らし、さまざまな意見や政策等の提言を行います。全国的な運動を展開する原動力でもあります。執行部としては、これまでの日弁連意見や意見照会の結果との整合性、政治・社会的背景などを勘案しながら、理事会などで合意形成を図り、日弁連の正式な意思として公表します。委員の方々はもとより、委員を日弁連に送り出している弁護士会・弁護士会連合会の皆さまの重層的なご尽力にもあらためて深く御礼申し上げます。
また任期中に発生した豪雨災害、震災などの自然災害時に行われた会員による支援活動は、市民が弁護士を身近で頼れる存在であると感じる貴重な機会にもなりました。支援に尽くされた会員の献身的なご努力に深甚なる感謝を申し上げます。
この3月に民事司法制度改革推進に関する関係府省庁連絡会議が「取りまとめ」を公表し、いよいよ民事司法制度改革が動き出します。具体的には、裁判のIT化、国際仲裁の活性化、ジェトロと連携しての中小企業の海外展開支援、外国人の司法アクセスの充実・強化、国際法務で活躍できる人材育成に向けた取り組みなどがあります。
行政手続への関与、民事信託、スクールロイヤーなどに関しては、関係委員会や関係省庁等との協議においてその基本的制度の枠組みがある程度できたと認識しています。
若手会員の方々には、これらの業務にぜひチャレンジしてほしいと思います。
この2年間の理事会は、私にとって実に楽しく充実したものでした。建設的な意見を交わし、修文を重ね、多くの意見書などを取りまとめる過程に、会内の合意形成に向けた意欲を感じました。理事の発言には重いものがあり、素晴らしい会議体にしていただいたことにあらためて御礼申し上げます。
最後になりますが、心強い支えとなったのは、正副会長会で毎週議論を交わし合った2年度にわたる副会長や、片腕とも両腕とも言える菰田事務総長、事務次長、嘱託弁護士、職員の皆さんで、一生の絆であり、友であり、思い出であります。ありがとうございました。
災害を対象とした義援金の差押えを禁止する
一般法の制定を求める意見書を公表
 災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書
災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書
日弁連は1月17日、「災害を対象とした義援金の差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書」 を取りまとめ、衆議院議長、参議院議長および各政党代表者宛てに提出した。
昨年発生した令和元年台風15号および19号による被害をはじめ、近時、日本全国においてさまざまな災害が発生し、各地で甚大な被害が生じている。これらの被災地に対しては、災害が発生するたびに全国から善意の寄付が寄せられ、義援金として被災者などの生活再建のための貴重な資金となっている。
しかし、債権者による義援金の差押えが法律によって禁止されなければ、被災者の生活再建が妨げられる。また、住宅ローン等を減免する「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」利用の際に義援金を自由財産として手元に残すことができなくなるおそれが生じる。
これまでこの問題については、災害発生の都度、事後的に義援金の差押えを禁止する個別法が制定され、一定の対応がなされてきたが、その立法例は東日本大震災や熊本地震、昨年の台風災害等を対象とした4例にとどまっている。
このため、現状では、これら個別法の対象とされなかった災害の被災者については、義援金の差押えが禁止されておらず、災害によって義援金に関する法律上の取り扱いに差異が生じている。
そこで日弁連は、災害対策基本法第2条第1号に定める全ての災害において、事後的な個別法の立法を待つことなく、被災者が安心して義援金を生活再建資金として活用できるように、災害時に地方自治体(都道府県または市町村(特別区を含む。))が一定の配分基準に従って交付する義援金について、その差押えを禁止する一般法の制定を求める意見書を取りまとめた。
意見書の趣旨を実現する速やかな立法を期待したい。
(災害復興支援委員会 幹事 在間文康)
日本国憲法企画
「憲法動画コンテスト」
表彰式&記念講演会
〜伝えませんか? あなたの瞳に映る人権の姿〜
1月25日 弁護士会館
 日本国憲法企画「憲法動画コンテスト」表彰式&記念講演会~伝えませんか?あなたの瞳に映る人権の姿~
日本国憲法企画「憲法動画コンテスト」表彰式&記念講演会~伝えませんか?あなたの瞳に映る人権の姿~
日弁連は、2017年度のポスター、2018年度の詩(ポエム)に続き、多くの方々が憲法について考える契機とするため、動画(ショートムービー)のコンテストを開催した。応募総数70作品の中から選出された入賞作品の上映と表彰式を行った。
 菊地裕太郎会長は開会の挨拶で、応募作品にはさまざまな人権の姿が映し出されており、審査は驚きと感激の連続だったと述べた。
菊地裕太郎会長は開会の挨拶で、応募作品にはさまざまな人権の姿が映し出されており、審査は驚きと感激の連続だったと述べた。
青井未帆教授(学習院大学)が、「人権ってなんだろう?〜憲法を『手がかり』に考えてみる」と題して講演を行った。憲法12条が規定する自由・権利の保持の義務に言及しながら、今の日本社会にまん延する強い同調圧力で法を守らせる仕組みに警鐘を鳴らした。
その後、高校生以下の部と大学生・社会人の部の入賞作品合計15作品を上演し、表彰式を行った。
グロテスク化したスマートフォンを通して表現の自由を描いた「スマホ男」(高校生以下の部金賞)の作者である山田淳也さんは、「人権侵害をしたら自分に跳ね返ってくるということを表現した」と作品のテーマを力強く語った。
大学生・社会人の部の金賞は、主人公がメガネをかけることで、日常生活の中で見えていなかった他人への配慮の必要性が見えてくるというストーリーを描いた「見えているなら」が受賞した。作者の松本京冴さんは、「大学生である自分にとって身近な人権をテーマに制作した。見て見ぬふりをしないという気持ちを込めて作った」と作品の意図を語った。
審査員を務めた松島哲也教授(日本大学芸術学部映画学科/日本映画監督協会常務理事)は、特に高校生以下の部の応募作品は柔らかな発想で表現しようとする気合いの伝わる作品が多かったと講評し、若い感性で人権、憲法を考えることの重要性を強調した。三上智恵氏(映画監督)は動画を作る、観る、審査するという行為そのものが憲法や人権を理解するために意義のある行為だと感じているとコメントした。そのほかの審査員からもビデオメッセージを含め講評があった。
ビジネスと人権に関する行動計画(NAP)発表に向けて
ステークホルダー報告会
1月23日 弁護士会館
 ビジネスと人権に関する行動計画(NAP)発表に向けて ステークホルダー報告会
ビジネスと人権に関する行動計画(NAP)発表に向けて ステークホルダー報告会
2011年に国連人権理事会で「ビジネスと人権に関する指導原則」が支持されて以来、20か国以上で行動計 画が策定されている。日本政府も2016年11月にビジネスと人権に関する行動計画(NAP)の策定を発表 し、本年半ばまでに公表することを目指しており、日弁連を含むステークホルダー団体は、NAP策定のための 作業部会・諮問委員会に参加している。パブリックコメントのためのNAP原案の公表を控え、ステークホルダ ー団体が一堂に会し情報や課題を共有した。
菊地裕太郎会長は開会の挨拶で、日本企業が国際社会でリーダーシップをとるためには、人権尊重を前提とした企業活動の展開が必須であり、NAP策定はもとより、その後の実践も含め粘り強く提言していきたいと意気込みを語った。
南慎二氏(外務省総合外交政策局人権人道課長)は、NAP策定は持続可能な開発目標(SDGs)の実現と表裏の関係にあり、SDGsの実現に向けた取り組みの一部であると説明した。また、これまでの取り組みについて、NAP策定のための作業部会や諮問委員会を設置し、ステークホルダーから意見を聞いて検討した結果、ビジネスと人権に関する意識・理解の向上、国内外のサプライチェーンにおける人権課題への対応、救済メカニズムの活用が主な課題であると整理したことを報告した。今後、パブリックコメントを経て本年半ばまでにNAPを策定すると見通しを示した。
続いて、南氏のほか作業部会に参加したステークホルダーによるパネルディスカッションを行った。長谷川知子氏(経団連SDGs本部長)は、企業の自主的取り組みを政府として最大限支援し、SDGs達成に貢献する内容にしてほしいと要望した。弁護士業務改革委員会の齊藤誠委員(東京)は、政策を指導原則の趣旨に沿った一貫性のあるものとすることが重要であり、既存の施策と指導原則との間のギャップを踏まえて、具体的な行動計画を提示すべきであると述べた。
質疑応答では、市民社会の立場からNAPのフォローアップについて質問が寄せられ、南氏は、初版のNAPの行動計画期間は5年を想定しており、モニタリングの手法や中間レビュー、改定作業については国際社会の動向や企業の取り組み状況も踏まえて今後検討することになると答えた。
2019年懲戒請求事案集計報告
日弁連は、2019年(暦年)中の各弁護士会における懲戒請求事案ならびに日弁連における審査請求事案、異議申出事案および綱紀審査申出事案の概況を集計して取りまとめた。
弁護士会が2019年に懲戒手続に付した事案の総数は4299件であった。 懲戒処分の件数は95件であり、昨年と比べると7件増えているが、会員数との比では0.22%(昨年は0.21%)で、ここ10年間の値との間に大きな差はない。
懲戒処分を受けた弁護士からの審査請求は30件であり、2019年中に日弁連がした裁決内容は、棄却が23件、処分取消が3件、軽い処分への変更が1件等であった。
弁護士会懲戒委員会の審査に関する懲戒請求者からの異議申出は48件であり、2019年中に日弁連がした決定内容は、棄却が36件、その他8件であった。 弁護士会綱紀委員会の調査に関する懲戒請求者からの異議申出は1271件、綱紀審査申出は479件であった。日弁連綱紀委員会および綱紀審査会が懲戒審査相当と議決し、弁護士会に送付した事案は、それぞれ16件、2件であった。
* 一事案について複数の議決・決定(例:請求理由中一部懲戒審査相当、一部不相当など)がなされたものについてはそれぞれ該当の項目に計上した。
* 終了は、弁護士の資格喪失・死亡により終了したもの。日弁連においては、異議申出および綱紀審査申出を取り下げた場合も終了となるためここに含む。
表1:懲戒請求事案処理の内訳(弁護士会)
| 年 | 新受 | 既済 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 懲戒処分 | 懲戒しない | 終了 | 懲戒審査開始件数 | |||||||
| 戒告 | 業務停止 | 退会命令 | 除名 | 計 | ||||||
| 1年未満 | 1~2年 | |||||||||
| 2010 | 1849 | 43 | 24 | 5 | 7 | 1 | 80 | 1164 | 31 | 132 |
| 2011 | 1855 | 38 | 26 | 9 | 2 | 5 | 80 | 1535 | 21 | 137 |
| 2012 | 3898 | 54 | 17 | 6 | 2 | 0 | 79 | 2189 | 25 | 134 |
| 2013 | 3347 | 61 | 26 | 3 | 6 | 2 | 98 | 4432 | 33 | 177 |
| 2014 | 2348 | 55 | 31 | 6 | 3 | 6 | 101 | 2060 | 37 | 182 |
| 2015 | 2681 | 59 | 27 | 3 | 5 | 3 | 97 | 2191 | 54 | 186 |
| 2016 | 3480 | 60 | 43 | 4 | 3 | 4 | 114 | 2972 | 49 | 191 |
| 2017 | 2864 | 68 | 22 | 9 | 4 | 3 | 106 | 2347 |
42 |
211 |
| 2018 | 12684 | 45 | 35 | 4 | 1 | 3 | 88 | 3633 | 21 | 172 |
| 2019 | 4299 | 62 | 25 | 0 | 7 | 1 | 95 | 11009 | 38 | 208 |
※ 日弁連による懲戒処分・決定の取消し・変更は含まれていない。
※ 新受事案は、各弁護士会宛てになされた懲戒請求事案に弁護士会立件事案を加えた数とし、懲戒しないおよび終了事案数等は綱紀・懲戒両委員会における数とした。
※ 2012年の新受事案が前年の2倍となったのは、一人で100件以上の懲戒請求をした事案が5例(5例の合計1899件)あったこと等による。
※ 2013年の新受事案が前年に引き続き3000件を超えたのは、一人で100件以上の懲戒請求をした事案が5例(5例の合計1701件)あったこと等による。
※ 2016年の新受事案が3000件を超えたのは、一人で100件以上の懲戒請求をした事案が5例(5例の合計1511件)あったこと等による。
※ 2018年の新受事案が前年の4倍となったのは、一人で100件以上の懲戒請求をした事案が4例(4例の合計1777件)あったこと、特定の会員に対する同一内容の懲戒請求が8640件あったこと等による。
※ 2019年の新受事案が3000件を超えたのは、関連する事案につき複数の会員に対する同種内容の懲戒請求が合計1900件あったこと等による。
表2:審査請求事案の内訳(日弁連懲戒委員会)
| 年 | 新受(原処分の内訳別) | 既済 | 未済 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戒告 |
業務 停止 |
退会 命令 |
除名 | 計 | 棄却 |
原処分 取消 |
原処分 変更 |
却下・終了 等 |
計 | ||
| 2017 | 23 | 15 | 0 | 1 | 39 | 22 | 3 | 2 | 2 | 29 | 37 |
| 2018 | 14 | 12 | 1 | 0 | 27 | 24 | 6 | 4 | 3 | 37 | 27 |
| 2019 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 23 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 |
※ 原処分取消の内訳
【2017年~2019年:戒告→懲戒しない(11)】【2019年:業務停止1月→懲戒しない(1)】
※ 原処分変更の内訳
【2017年:業務停止3月→業務停止2月(2)】
【2018年:業務停止1年6月→業務停止9月(1)、業務停止1年→業務停止9月(1)、業務停止6月→業務停止4月(1)、業務停止3月→業務停止2月(1)】
【2019年:業務停止1月→戒告(1)】
表3:異議申出事案の内訳(日弁連懲戒委員会)
| 年 | 新受 | 既済 | 未済 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棄却 | 取消 | 変更 | 却下 | 終了 | 速やかに終了せよ | 計 | |||
| 2017 | 42 | 41 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 46 | 45 |
| 2018 | 27 | 42 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 49 | 23 |
| 2019 | 48 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 44 | 27 |
※ 取消の内訳
【2018年:懲戒しない→戒告(1)】
※ 変更の内訳
【2017年:業務停止3月→業務停止6月(1)、業務停止6月→業務停止1年(1)】
【2018年:戒告→業務停止1月(1)】
表4:異議申出事案の内訳(日弁連綱紀委員会)
| 年 | 新受 | 既済 | 未済 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査相当 | 棄却 | 却下 | 終了 | 速やかに終了せよ | 計 | |||
| 2017 | 904 | 1 | 824 | 20 | 8 | 39 | 892 | 174 |
| 2018 | 2036 | 5 | 1179 | 41 | 2 | 102 | 1329 | 918 |
| 2019 | 1271 | 16 | 1041 | 13 | 8 | 655 | 1733 | 456 |
※ 2018年の新受事案のうち、同一の異議申出人による計1200件の異議申出事案を含む。
※ 2019年の新受事案のうち、同一の異議申出人による計502件の異議申出事案を含む。
表5:綱紀審査申出事案処理の内訳(日弁連綱紀審査会)
| 年 | 新受 | 既済 | 未済 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 審査相当 | 審査不相当 | 却下 | 終了 | 計 | |||
| 2017 | 376 | 35 | 246 | 6 | 0 | 287 | 161 |
| 2018 | 398 | 3 | 325 | 6 | 0 | 334 | 225 |
| 2019 | 479 |
2 |
475 | 7 | 2 | 486 | 218 |
※ 2017年の審査相当事案のうち、同種事案に関する議決32件を含む。
日弁連短信
雑 感
 事務総長は、理事会の審議で選任・解任される役職だが、実質的には会長の推薦によるため、会長の任期に合わせ任免が決められる。本稿の校了時点では、次期会長が決まっていないため、事務総長の引き継ぎもできないでいるのは、少し残念である。
事務総長は、理事会の審議で選任・解任される役職だが、実質的には会長の推薦によるため、会長の任期に合わせ任免が決められる。本稿の校了時点では、次期会長が決まっていないため、事務総長の引き継ぎもできないでいるのは、少し残念である。
この2年間で事務総長として最高裁判所や法務省をはじめとする諸官庁の方々と交流できたことは貴重な経験であった。法務省で事務総長や事務次長のカウンターパートになる方は、裁判官・検察官が異動で来ており、法曹三者としての交流になる。時には、厳しい交渉をしなければならないことはあるが、法曹三者の交流は、他の省庁の方との交流とは異なる楽しさがある。
◇ ◇
最近、裁判所において、地域社会との交流を進めていく方向性が示されている。大谷最高裁判所長官の談話や挨拶でも触れられており、2019年6月の長官・所長会同では、地域社会とのつながりを維持・深化させていくことについての協議がなされている。裁判員を務めた人に対しても、2018年後半からは「みなさんの貴重な経験を周りの方々にぜひお伝えください」とのペーパーを渡すようになった。
これらの動きは、日弁連・弁護士会がかねてから目指してきた地域に根差した司法にしていくことと軌を一にするものであり、歓迎したい。
2019年11月の日弁連理事会において、裁判官制度改革・地域司法計画推進本部からこのような裁判所の動きについて報告があり、各地で協力して具体的取り組みをするよう要望があった。その際、山口県弁護士会をはじめ中国地方の弁護士会を中心として、裁判所の新しい動きや弁護士会との協議について報告があった。
今後も各地で、裁判所との地域に根差した交流がなされるよう、各地の実情に応じて各弁護士会に取り組んでいただくことを期待したい。
◇ ◇
中村愼最高裁判所事務総長とお目にかかったときに、中村事務総長が水戸地方裁判所所長を務めていた2019年3月に茨城県弁護士会の要請で「今後の司法を考えてみませんか」というテーマで弁護士を対象に講演をされたと伺った。この18年間の茨城県の弁護士数の増加率の話などは興味をそそったようである。このような交流は地域司法の取り組みとは趣旨が少し異なるかもしれないが、お互いの理解を深める端緒にもなり、意義があると思う。
2年間多くの方にお世話になり、ありがとうございました。
(事務総長 菰田 優)
院内集会
実現させよう! 公益通報者保護法の実効的改正
2月4日 衆議院第一議員会館
 院内集会「実現させよう! 公益通報者保護法の実効的改正」
院内集会「実現させよう! 公益通報者保護法の実効的改正」
2020年の通常国会に公益通報者保護法改正法案が提出される見通しである。実効性のある法改正を実現するため院内集会を開催した。集会には約140人が参加した(うち国会議員本人出席9人、代理出席8人)。
 研究費の不正使用や医療事故について公益通報を行った小川和宏准教授(金沢大学)が、通報を理由にさまざまな嫌がらせを受けた経験や訴訟の苦労などを語り、通報者保護のための法改正や体制整備が不可欠であると訴えた。
研究費の不正使用や医療事故について公益通報を行った小川和宏准教授(金沢大学)が、通報を理由にさまざまな嫌がらせを受けた経験や訴訟の苦労などを語り、通報者保護のための法改正や体制整備が不可欠であると訴えた。
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)の大塚喜久雄氏は、具体的な企業不祥事事案を分析し、内部通報で解決できず対処までに長期間を要する実態など現行法の問題点を指摘した。
志水芙美代会員(東京)は、約120件の企業不祥事案件の第三者委員会報告書を分析した結果について、これらの企業の内部通報制度が、通報しても「是正されない」「報復される」との理由で利用されなかったことなどを指摘し、林尚美会員(大阪)は、公益通報者保護EU指令が禁止する不利益取り扱いの具体的内容(けん責、配置転換、精神医学的な紹介等)を詳細に明記する点や通報妨害・報復・守秘義務違反に罰則を定めている点は参考になると紹介した。
拝師徳彦会員(千葉県/全国消費者行政ウォッチねっと)は、最重要課題である不利益取り扱いに対する行政処分・刑事罰の導入を最後まで働きかけたいとし、関連団体からも同様の決意表明がなされた。
坂田進氏(消費者庁審議官)は、消費者の安全安心を確保するため公益通報を通じた事業者の法令遵守が確保される改正法案にしたいとコメントした。
出席した国会議員からは、「公益通報者の保護は消費者のみならず企業の発展にも寄与する」「実効性のある法改正を実現すべきである」などの意見が寄せられた。
市民集会
刑事法廷内における手錠・腰縄問題を考える
1月20日 弁護士会館
 市民集会「刑事法廷内における手錠・腰縄問題を考える」
市民集会「刑事法廷内における手錠・腰縄問題を考える」
日本では、被疑者・被告人が刑事法廷内に入廷または退廷する際、手錠・腰縄をされたままであること(以下「手錠・腰縄問題」)が多く、無罪推定の原則との関係などから問題になっている。日弁連が、2019年10月に「刑事法廷内における入退廷時に被疑者又は被告人に手錠・腰縄を使用しないことを求める意見書 」(以下「意見書」)を公表したものの、手錠・腰縄問題が広く議論される状況には至っていない。この問題に対する市民の関心を喚起すべく集会を開催した。
太田健義会員(大阪)が基調報告を行い、問題の所在、意見書の内容のほか、2019年5月の大阪地方裁判所の国賠訴訟判決をきっかけに、申し入れに応じて傍聴席から見えないように衝立で遮蔽されたスペースで手錠・腰縄を外すなど、裁判所の運用が変わりつつあることを説明した。
続いて、劇団往来が刑事裁判の被告人となった父親とその裁判を傍聴した娘の心情やその他の傍聴人らの反応を描いた寸劇「手錠・腰縄必要ですか?」を上演し、えん罪被害者であるミュージシャンのSUN―DYU氏が自作の歌「12の言葉」を歌唱した。
パネルディスカッションで、SUN―DYU氏は、手錠・腰縄に繋がれ「反省しています」と言わんばかりに前屈みの自分の姿を見て裁判官が有罪の印象を抱くのではないかと心配し、思い切り胸を張るようにして法廷の入退廷をしたことなど自身の経験を踏まえ、無罪推定の原則と相容れない日本の刑事裁判の現実の姿を批判した。
元裁判官の水野智幸会員(第一東京)は、逃走防止や裁判の効率化は重要な視点であるとしつつ、これらの視点が重視されるあまり無罪推定の原則を実際の刑事裁判に反映させるための方策についてあまり検討されてこなかったのではないかと問題提起した。
第5回
弁護士学校派遣事業に関する意見交換会
1月24日 弁護士会館
社会との連携・協働による「社会に開かれた教育課程」を目指す新学習指導要領の影響もあり、弁護士学校派遣のニーズは高まっている。弁護士学校派遣事業について、関連委員会による意見交換会を行った。
基調講演
〜学校現場から望むこと
河村新吾教諭(広島市立広島工業高等学校)は、新学習指導要領による新しい教育理念や成年年齢引下げの影響で教育現場は大きく変化しているが、教員がこれに追いついていないと現状を報告した。そして、今こそリアルな法律問題を扱う弁護士と教員が協働し、法律を用いてトラブルを解決する力を養う教育を実施することが求められていると指摘した。具体的な協働の方法として、弁護士は「答え」ではなく「問い」を生徒に与え、教員は生徒に議論させるという役割分担が効果的であること、生徒の学習段階には「気付く」「知る」「活用する」があるため、知識ではなく気付きを与える必要があること、リアルな題材を提供し利害対立を明確にした上でそれぞれの立場で主張させ、答えが出なくてもその過程が学びとなること等を丁寧に解説した。
ワークショップ
〜実際の授業案の検討
ワークショップでは、労働法制委員会の立田久義委員(岡山)のワークルール授業教材と市民のための法教育委員会の春田久美子委員(福岡県)の授業案を検討した。
河村教諭からは、リアルな事例を示すのは良いが、長時間労働の問題を議論させてから論点を残業代に絞ると生徒の関心も高まる、労働基準法の存在理由を生徒に考えさせるのが効果的である、一方の意見に偏りがちな論点も場面設定を少し変えたり登場人物を増やすなどの工夫次第で多面的な思考を引き出す授業展開が可能であり、弁護士と教員が協働することで、そのような授業を効果的に実現できるなどの指摘がなされた。
シンポジウム
スコアリングを巡る法的問題
2月7日 弁護士会館
 シンポジウムスコアリングを巡る法的問題
シンポジウムスコアリングを巡る法的問題
近年、人工知能(AI)を用いた貸付(AIレンディング)サービスが拡大し、これに対応した割賦販売法改正が予定されている。個人の信用調査にとどまらず、さまざまなスコアリングサービスが広く提供されている現状を踏まえ、スコアリングを巡る法的問題について議論するシンポジウムを開催した。
消費者問題対策委員会の板倉陽一郎副委員長(第二東京)は、事業者が現在展開しているスコアリングサービスの具体的な内容や、貸付判断におけるスコアの利用実態を紹介した。また、総務省の情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会の資料を用いて、同意取得の方法、信用スコアの利活用方法の制限、基礎データや説明責任の問題など個人情報保護法上の論点等を整理した。
山本龍彦教授(慶應義塾大学大学院法務研究科)は、スコアリングにおける憲法上の懸念として、用いられる情報や算出方法が明らかにされない点、不適切なデータが混入する可能性とその検証が困難な点、スコアを気にして行動が制約される萎縮効果などを指摘した。その上で、スコアリングの利用を無批判に広げると「スコア利用社会」から「スコア監視社会・国家」となりかねないと警鐘を鳴らした。
パネルディスカッションでは、中国のスコアリングについて、ジャーナリストの高口康太氏が、クレジット会社による金融的信用スコアや地方自治体による道徳的信用スコア等の各種類型を紹介し、類型に応じた課題があることを説明した。また、池本誠司委員(埼玉)は、AI・ビッグデータを活用した与信審査の許容や、それを前提とした決済情報の利活用等を掲げる割賦販売法の規制緩和に向けた議論状況と課題を解説した。
山本教授、板倉副委員長を加えたパネリストによる討論では、基礎データとして、性別、人種など自ら修正・変更できない属性や生理的・身体的な情報をスコアリングに用いるべきではないこと、スコアリングの適正さを担保する仕組みやスコアリングの限界を意識して利用する必要性などが指摘された。
第31回 全国弁護士業務改革委員長会議
2月3日 弁護士会館
日弁連の弁護士業務改革委員会では、弁護士会の業務改革委員会の委員長が一堂に会する全国会議を毎年開催している。31回目となる今回は、弁護士報酬ガイドブックの改訂や民事裁判手続のIT化などについて議論した。
弁護士報酬ガイドブックの改訂
 弁護士報酬等検討PTの佐瀬正俊座長(東京)は、2009年に発行された弁護士報酬ガイドブックの改訂について報告した。日弁連の旧報酬等基準規程が廃止されて15年以上経過し、報酬に関する用語等について確認する機会が減っていること、弁護士業務が多様化し、これまでの経済的利益を基準とした報酬以外にタイムチャージなどの新たな報酬体系の利用が増えていることなど、改訂の必要性を説明した。佐瀬座長は、関連委員会に対する意見照会の結果を示すとともに、現在の進捗状況を報告した。
弁護士報酬等検討PTの佐瀬正俊座長(東京)は、2009年に発行された弁護士報酬ガイドブックの改訂について報告した。日弁連の旧報酬等基準規程が廃止されて15年以上経過し、報酬に関する用語等について確認する機会が減っていること、弁護士業務が多様化し、これまでの経済的利益を基準とした報酬以外にタイムチャージなどの新たな報酬体系の利用が増えていることなど、改訂の必要性を説明した。佐瀬座長は、関連委員会に対する意見照会の結果を示すとともに、現在の進捗状況を報告した。
民事裁判手続等のIT化
IT問題検討PTの内野真一座長(東京)が、2月3日から始まったウェブ会議による期日の実施等(フェーズ1)の内容を中心に、民事裁判手続のIT化について概要を説明した。平岡敦副委員長(第二東京)らがマイクロソフト社のTeamsを使用して実演した。また、鶴山昂介幹事(大阪)らから、周囲に情報が漏れる危険があるため事務所内個室での通信を心掛ける必要がある等の注意喚起があった。具体的な使用方法等についてはeラーニング研修が有用であると紹介された。
弁護士会の取組課題
低迷している女性委員の比率を上げる方策について議論したほか、山口県弁護士会のEAP(従業員支援プログラム)による業務拡大、福岡県弁護士会の行政連携、公正取引委員会地方事務所との連携など特徴的な取り組みについて紹介した。
JFBA PRESS -ジャフバプレス- Vol.150
2019年度 日弁連の広報
「伝わる」広報の強化・促進を
日弁連は2013年度から市民向け広報活動の充実・強化に努めており、会務執行方針でも重要課題として「広報の充実」が挙げられています。
2019年度は、全国統一ポスターのさらなる掲出、法律相談会などイベント用の広報ツールの制作、ウェブ広告の実施、雑誌広告の掲載、裁判員制度10周年記念ムービーの公開、広報キャラクター「ジャフバ」の活用などを中核に据え、広報活動を展開しました。
本稿では、2019年度に日弁連が実施した広報活動の概要を紹介します。
(広報室)
全国統一ポスターのさらなる掲出
2018年度に制作した武井咲さん起用の全国統一ポスターの掲出先を、文化会館・センター・ホールといった全国の公立文化施設にも広げました。
ポスターの制作に合わせて設けたスペシャルサイトも、引き続き日弁連ウェブサイトに掲載し、弁護士が、学校・職場・家庭・経営・老後など、さまざまなライフステージで頼れる存在であることを訴え、弁護士への相談の契機となることを目指しています。
ロールアップバナー・ミニのぼりの制作
 2020年2月に、スペシャルサイトに掲載している武井さんの画像を用いたロールアップバナーとミニのぼりを制作しました。ロールアップバナーは、全国で実施される法律相談会などでの活用を想定しています。
2020年2月に、スペシャルサイトに掲載している武井さんの画像を用いたロールアップバナーとミニのぼりを制作しました。ロールアップバナーは、全国で実施される法律相談会などでの活用を想定しています。
CM動画広告の継続
2016年度に制作した武井さんのCM動画を引き続き活用し、JR東日本・JR西日本・東京メトロの電車内ビジョン、YouTube TrueⅤiewで広告を実施しました。
バナー広告の実施
武井さんのポスター用画像などを利用し、Yahoo!やGoogle、これらの提携サイトでバナー広告を実施しました。
中小企業経営者向け雑誌広告の継続
ビジネス誌『日経トップリーダー』にタイアップ広告(記事風の広告)を掲載しました。働き方改革と民法の改正を取り上げ、顧問弁護士の有用性を訴えました。
また、武井さんを起用した広告を『プレジデント』、『日経トップリーダー』に掲載し、「ひまわりほっとダイヤル」の周知を図りました。
高齢者向け雑誌広告の掲載
月刊誌『家の光』などに4コマ漫画を用いた広告を掲載し、かかりつけ弁護士であるホームロイヤーをアピールしました。また、日弁連ウェブサイト内に「ホームロイヤーのすすめ」と題したページを設け、暮らしの安心のためにホームロイヤーが有用であることを訴求しています。
裁判員制度10周年記念ムービーの公開
裁判員制度10周年記念ムービーを2019年末に公開しました。「モモタロウ裁判」など昔話の主人公たちが被告人、証人、裁判員として登場する3本立てのムービーで、連続して見ることで、裁判員制度の意義が伝わるようになっています
ウェブサイトのリニューアル
 日弁連ウェブサイトの一般ページを全面リニューアルしました。サイトマップを抜本的に見直すとともに、検索機能を強化しています。デザイン面では、日弁連のコーポレートカラーであるブルーは残しつつ、武井さんのポスターの背景色や、ひまわりをイメージしたクリーム色を加え、温かみが伝わるよう工夫しました。
日弁連ウェブサイトの一般ページを全面リニューアルしました。サイトマップを抜本的に見直すとともに、検索機能を強化しています。デザイン面では、日弁連のコーポレートカラーであるブルーは残しつつ、武井さんのポスターの背景色や、ひまわりをイメージしたクリーム色を加え、温かみが伝わるよう工夫しました。
仕事体験テーマパーク「カンドゥー」への協賛継続
2019年3月から、千葉県のイオンモール幕張新都心内にある仕事体験テーマパーク「カンドゥー」に協賛し、子どもたちが弁護士の仕事を体験できるアクティビティを提供しています。参加する子どもたちは、犯罪の疑いをかけられた被疑者・被告人を救うため、証拠を収集し、刑事裁判で弁護人として活動します。
全国各地のイオンモールでも「出張カンドゥー」と銘打ったアクティビティが提供されており、2019年度は「出張カンドゥー」向けに、弁護士に関するクイズを制作しました。
「カンドゥー」での体験を通し、子どもたちに弁護士の社会的役割を理解してもらい、弁護士を将来の職業選択の候補にしてもらうことを目指しています。
法曹三者共催企画「法曹という仕事」の開催
2019年7月、将来の進路として法曹に関心がある若者を対象に、最高裁判所で法曹三者の仕事の魅力を紹介するイベント「法曹という仕事」を初めて開催しました。中学生や高校生、大学生ら約180人が参加しました。
弁護士会との連携強化
2019年度も、弁護士会の広報担当者が一堂に会する全国広報担当者連絡会議を開催しました。
今回は、新潟県弁護士会のマスコットキャラクター「まもルン」も駆け付け、同会におけるキャラクターの活用が紹介されたほか、福岡県弁護士会の対外広報活動について報告がありました。また、弁護士会を規模別に4つのブロックに分け、地域の実情を踏まえつつ情報共有・意見交換を行いました。
今後も各地の意見を参考に、弁護士会と連携して、よりよい広報活動につなげていきます。
マスメディアへの対応
新聞社やテレビ局等からの問い合わせ対応のほか会長声明や意見書等のプレスリリースを行いました。
また、憲法改正手続や日本の刑事司法制度などに関するプレスセミナーを4回開催しました。
日弁連広報キャラクター「ジャフバ」の活用
 日弁連広報キャラクター「ジャフバ」の着ぐるみは、人権擁護大会をはじめ、日弁連・弁護士会のさまざまなイベントに参加しました。全国各地でたくさんの市民と触れ合い、「えがお推進部長」として職責を果たしています。
日弁連広報キャラクター「ジャフバ」の着ぐるみは、人権擁護大会をはじめ、日弁連・弁護士会のさまざまなイベントに参加しました。全国各地でたくさんの市民と触れ合い、「えがお推進部長」として職責を果たしています。
また、「ジャフバ」のツイッターとインスタグラムでは、情報を発信しています。
70周年記念誌の発刊
日弁連創立70周年記念誌『日弁連七十年』を発刊し、60周年以降の日弁連のあゆみを紹介しました。内容は、日弁連ウェブサイトにも掲載しています。
法律相談についての広報
2018年12月に制作した、時短勤務者と中間管理職との間で起きた出来事を双方の視点で描いた法律相談ムービー「ハラスメントA面・B面」が、公益社団法人映像文化製作者連盟(映文連)が主催する「映文連アワード2019」で、コーポレート・コミュニケーション部門の部門優秀賞を受賞しました。これを受け、日弁連ウェブサイトでの公開期間を延長して法律相談センターの広報・周知を続けています。
NHKラジオ第1で放送中の「Nらじ」では、暮らしに関する法律が取り上げられることとなり、その放送時に「ひまわり相談ネット」などを案内しました。
また、希望する弁護士会に対し、法律相談用の特設ページ制作と、同ページに誘導するためのリスティング広告・バナー広告出稿のサポートを行いました。
ブックセンターベストセラー
(2019年12月・手帳は除く) 協力:弁護士会館ブックセンター
| 順位 | 書名 | 著者名・編者名 | 出版社名・発行元名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究 | 司法研修所 編 | 法曹会 |
| 2 | 有斐閣判例六法 Professional 令和2年版 | 中里 実・長谷部恭男・佐伯仁志・酒巻 匡・大村敦志 編集代表 | 有斐閣 |
| 3 | 改正相続法と家庭裁判所の実務 | 片岡 武・管野眞一 著 | 日本加除出版 |
| 4 | 契約類型別 債権法改正に伴う 契約書レビューの実務 | 滝 琢磨 著 | 商事法務 |
| 5 | 労働法[第12版] | 菅野和夫 著 | 弘文堂 |
| 6 | 模範六法 2020 令和2年版 | 判例六法編修委員会 編 | 三省堂 |
| 7 | 破産実務Q&A220問 | 全国倒産処理弁護士ネットワーク 編 | きんざい |
| 8 | 裁判員裁判と裁判官 | 司法研修所 編 | 法曹会 |
| 9 | 契約書作成の実務と書式[第2版] | 阿部・井窪・片山法律事務所 編 | 有斐閣 |
| 10 | クレジット・サラ金処理の手引〔6訂版〕 | 東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会 編著 | 東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会 |
海外情報紹介コーナー⑧
裁判官は内部通報者として保護されるか?
英国最高裁判所は、司法関係予算の削減を公に批判した地裁判事が内部通報者保護制度の対象となる「労働者」に該当すると判断した。判決では、主要な就業条件が法定されていること等から委任関係を否定した上で、欧州人権条約に照らして「労働者」として保護を受け得るとした。
内部通報者保護重視の動きを反映した判決とみられている。
(注:本稿中「英国」はイングランドおよびウェールズを指す。)
(国際室嘱託 片山有里子)