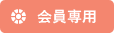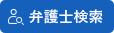令和6年能登半島地震から1年が経過したことを受けての会長談話
2024年(令和6年)1月1日に令和6年能登半島地震(以下「能登半島地震」といいます。)が発生してから1年が経過しました。
内閣府非常災害対策本部の発表によれば、2024年(令和6年)12月24日時点における被害状況は、死者・行方不明者が491名(うち、災害関連死が261名)、負傷者が1379名、半壊以上の住家被害が2万9670件となっており、2011年(平成23年)に発生した東日本大震災以降、最大の被害が生じています。加えて、同年9月に能登豪雨災害が発生し、同被災地に再び大きな被害をもたらしており、生活再建を目指す被災者の方々にのしかかる不安は更に増大しています。
当連合会では、能登半島地震の発生を受け、2024年(令和6年)1月5日に令和6年能登半島地震災害対策本部を設置し、金沢弁護士会、福井弁護士会、富山県弁護士会及び新潟県弁護士会による被災者への支援活動のバックアップを行っているほか、各地の弁護士会や弁護士会連合会に支援活動への協力を要請し、複数の弁護士会、弁護士会連合会による被災地弁護士会への協力体制を構築してきました。また、被災地で生じている法的な問題を解決するため、立法提言や制度改善の提言を行ってきたところです。
被災地においては、徐々に復旧が進みつつあるものの、被災地へのアクセスの困難さ、自治体や事業者の人材不足等を原因とする公費解体の遅れなどの問題点も指摘されています。環境省の発表によると、2024年(令和6年)12月16日時点において、公費解体の申請数3万4221件に対し、解体の完了は1万2361件であり、解体の完了率はわずか36%にとどまっています。公費解体は、被災者の方々が今後の生活再建を目指していく上で重要な一歩となるものですが、未だ多くの被災者が解体を待っている状態であり、新たな住宅の再建などについて考える前提にも至っていないと言わざるを得ません。
このような状況からすれば、能登半島地震の被災地においては、これから生活再建に向けた相談などが本格化していくものと思われます。しかしながら、日本司法支援センター(以下「法テラス」といいます。)による資力を問わない被災者相談については、総合法律支援法の規定により、発災から1年で利用できなくなってしまいます。当連合会は、過去の災害における相談件数の推移や能登半島地震の被災地の現状を踏まえ、2024年(令和6年)10月22日付けで「 総合法律支援法における被災者法律相談援助に関する実施期間の改正等を求める意見書」を取りまとめ、総合法律支援法を改正して、資力を問わない被災者相談を実施できる期間を延長すること、又は能登半島地震に関する特例法を制定することを求めましたが、現時点において法改正及び特例法制定のいずれも実現されていません。
総合法律支援法における被災者法律相談援助に関する実施期間の改正等を求める意見書」を取りまとめ、総合法律支援法を改正して、資力を問わない被災者相談を実施できる期間を延長すること、又は能登半島地震に関する特例法を制定することを求めましたが、現時点において法改正及び特例法制定のいずれも実現されていません。
2024年(令和6年)12月に、同年9月に発生した能登豪雨災害が、総合法律支援法第30条第1項第4号に規定する著しく異常かつ激甚な非常災害として指定されたことで、同災害の被災地とされる能登半島の3市3町では、同災害に関する法テラスによる資力を問わない被災者相談が利用可能となったものの、他の地域の被災者は、資力を問わない被災者相談は利用できないこととなります。
一部地域でも資力を問わない被災者相談が継続されることになったことは歓迎しつつも、能登半島の3市3町を除く被災地においては、未だ生活再建のめども立たない状態にありながら、資力を問わない被災者相談を利用する機会を失うこととなるため、当連合会は、引き続き、能登半島地震の被災地における、資力を問わない被災者相談の継続を実現すべく、国への働きかけ等を行っていく所存です。
また、今後は、復旧作業が進行し、被災者の生活再建への動きが本格化していくこととなります。一人一人の被災者の状況に応じた、きめ細やかな支援が必要となり、行政、士業、NPOなど被災者に関わる支援者が協力して、必要な支援を届けていく災害ケースマネジメントの動きが必要となります。当連合会は、そうした災害ケースマネジメントに関しても、被災地弁護士会を中心とした活動を全面的にバックアップし、被災者の一日も早い生活再建が実現するよう尽力していく所存です。
当連合会が、かねてより述べているとおり、災害からの復興は、「人間の復興」でなければなりません。被災者支援は、被災者の基本的人権を回復するための支援であり、当連合会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の団体として、被災者の「人間の復興」を実現すべく、できる限りの支援を継続していく所存です。
2025年(令和7年)1月1日
日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子