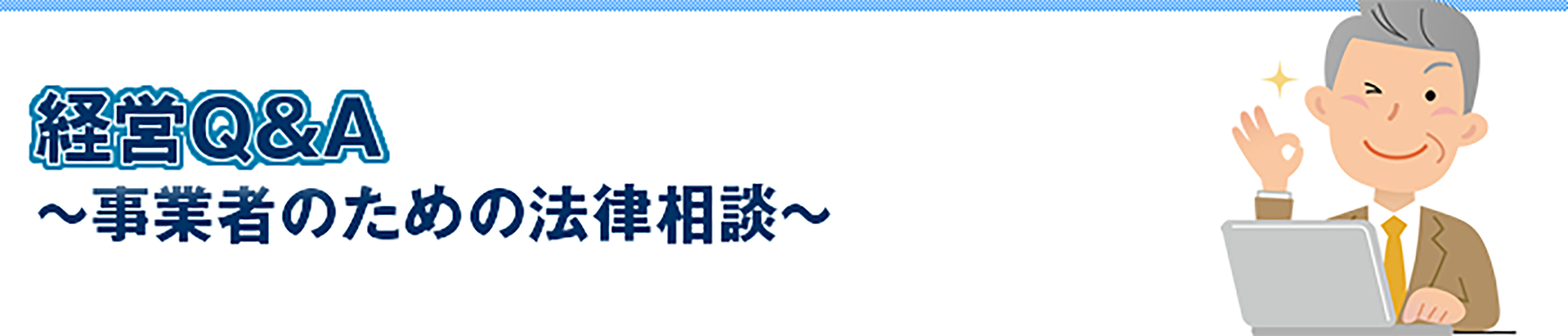
第2回 2017年5月号 会社設立時における法律の予備知識
※本記事はPDFでもご覧になれます PDF版はこちら
Q.私は、ソフトウェア制作会社等から委託を受けて開発を行っているフリーのITエンジニアです。この度、友人らと企業向けに組織の業務効率を高めるアプリビジネスを始めることになりました。友人らからは共同出資による会社設立を提案されているのですが、なにぶん初めてのことで勝手がわかりません。会社にすることでどのようなメリットがあるのでしょうか。また、会社の設立にあたっては、どのような点に気をつければよろしいのでしょうか。
A.会社を設立して事業の主体とすることで、経営者は出資や保証債務の範囲に責任を限定しながら事業を行うことができます。他方、法人の経営者は法人の所有者に対して経営責任を負っているため、任務に背いて会社に不利益を与えたときは損害賠償や退任を求められるおそれがあります。 会社の設立にあたっては、目的とする事業を遂行するのに最適な会社形態を選択するとともに、将来の重要な意思決定に支障を生じないように、経営(業務執行者)の人選や利益配分(費用分担)のルールなどを慎重に決定し、書面に残すようにしましょう。
1 法人化のメリット・デメリット
事業の主体を個人から法人にすることで、経営者は様々な法律上及び事実上のメリットを享受することができます。一方、法人化することにより、法令や定款(※)に従った会社運営、会計税務、登記等の様々な負担が生じます。
(※)定款とは、法人の目的、事業内容、機関構成、役員の権限、意思決定手続等が記載された会社の設計図ともいうべきもので、株式会社においては、発起人が作成して公証人の認証を受けることが会社設立の要件とされ、株式会社設立後は総会における特別の決議によらなければ変更できません。
介護事業など、法人でなければ営むことができない事業を目的とするのでない限り、必ずしも事業の開始時から法人である必要はありません。しかし、法人にすることで経営者個人が債権者に対して直接の無限責任を負うリスクを排除できますので、事業の規模が拡大し、全ての責任を個人で負うことが難しくなる前に、法人化について検討を始めるのがよいでしょう。 法人化のメリット、デメリットについては、下表を参照ください。
| 法人化のメリット | 法人化のデメリット |
|---|---|
・会社の行為は会社のみが原則として責任を負い、経営者個人が責任を負うリスクを排除できる など |
・会社法及び同法施行規則など法令の規制を受ける など |
2 選択可能な会社の種類と特徴
会社の設立を選択した場合、次に検討しなければならないのは会社形態です。 現行の会社法下で設立することのできる会社には、株式会社、合同会社(日本版LCC)、合名会社及び合資会社の4つの形態がありますが、営利事業を営むことを目的にこれから法人を設立するのであれば、事業のリスクを出資額に限定でき、会社債権者から直接請求を受けることのない株式会社か合同会社を選ぶのが適切です。
このうち、株式会社は、所有(株主)と経営(業務執行者)が分離しており、所有者である株主は経営の専門家である取締役に業務執行の意思決定を委ねることができる会社形態です。
株式会社は定款によりある程度柔軟な組織設計が可能であり、1人株主のオーナー会社から少数の同族株主が支配する閉鎖会社、株主が数万人規模の公開会社まで、あらゆる規模の事業運営に対応できますが、組織設計に一定の縛りがあるほか、定款変更や役員の選任などの重要事項の決定のためには株主総会を必ず開催する必要があるなど、小規模であっても株主が複数いる場合には、維持運営にそれなりの手間とコストがかかります。
一方、合同会社は、出資者である社員が自ら経営を行い、定款に別段の定めがない限り、社員各人が会社を代表し業務を行うことが予定されている会社形態です。合同会社は社員の個性が重視され、持分の譲渡に他の社員の同意が必要とされる反面、出資額にかかわらず利益や議決権の分配割合を自由に定めることができるなど、株式会社よりもさらに柔軟な組織設計が可能です。複数の社員がいる場合でも社員総会によることなく迅速な意思決定ができ、株式会社と同様に社員一人の合同会社も設立可能であることから、小規模で機動的な事業展開をするのに適した会社形態であるといえます。
ご質問のケースで株式会社、合同会社のどちらを選択するべきかについては一概には決められませんが、少数の信頼できる仲間と可能な限りコストを抑えながら機動的に会社を運営し、かつ出資額にとらわれることなく事業に貢献する者に利益分配をしたいとのニーズが強いのであれば、合同会社を設立するのも一案でしょう。
他方、将来はプロの投資家を含むより多くの出資者から出資を集めて事業を発展させたいということであれば、投資家に出資額に応じた議決権が保証される株式会社の形態で最初から事業を始めるか、投資を受け入れるタイミングで合同会社から株式会社への組織変更を検討することになるでしょう。
なお、いわゆるエンジェル税制(※)は株式会社である中小企業のみが投資対象になりますので、エンジェル投資家から資金調達することを計画するのであれば、出資を受ける時点で株式会社にしておく必要があることにご留意ください。
(※)エンジェル税制とは、一定の要件を満たす未上場のベンチャー企業(中小企業等経営強化法2条3項3号,同7条に定める「特定新規中小企業者」)に投資を行った個人投資家が、株式取得時又は株式譲渡による損失発生時に、所得税の優遇措置(寄附金控除もしくは損失の繰り延べ)を受けることのできる制度です。
(3)会社の設立手順と設立費用
株式会社と合同会社の設立手順と設立費用は以下のとおりです。合同会社は、株式会社の設立時に必要とされる公証役場による定款認証が不要であり、設立登記の登録免許税も安く設定されていることから、設立にかかる費用と手間を節約することができます。
<株式会社の場合>
(1)設立手順

※株式会社の定款は公証役場で認証を受ける必要があります。
(2)設立費用
・ 定款印紙代4万円(電子定款にすれば0円)
・ 公証役場の定款認証手数料5万円
・ 設立登記の登録免許税15万円(資本金の額の1000分の7。最低額は15万円)
・ その他、法人印鑑購入代金、登記を司法書士に依頼する場合の費用など
<合同会社の場合>
(1)設立手順

(2)設立費用
・ 定款印紙代4万円(電子定款にすれば0円)
・ 公証役場の定款認証手数料0円(認証自体不要)
・ 設立登記の登録免許税6万円(資本金の額の1000分の7。最低額は6万円)
(4)共同出資・共同経営における留意点
共同出資により会社を設立するためには、出資に関する基本的な事項、すなわち出資額または給付する財産の内容と価額、払込みまたは給付の期限、引受株式数などを、設立時の原始定款で定めておく必要があります。定款の作り方がわからないという場合は弁護士や司法書士、公証人などお近くの専門家にお尋ねください。
それでは、質問のケースのように、投資や会社経営の経験に乏しい友人同士が共同で出資して会社を設立し、共同経営していく場合、どのようなリスクを想定して備えることが有益でしょうか。
経営者にとっては、運命共同体ともいうべき他の共同出資者との間で足並みが揃わないことが最大の経営リスクです。少なくとも次に挙げる事項については、事前によく話し合って、共同出資契約書などの合意文書の形で残しておくことが望ましいでしょう。
①各自の役割に応じた役職、報酬額とその支払条件
②事業に対する注力の度合い(コミットメントの程度)
③競業行為・利益相反行為の禁止又は許容の程度
④追加の出資又は貸付の義務の有無
⑤共同経営者の1人が途中で離脱する際の株式又は出資持分の取扱い
⑥重要な経営方針等を巡って意見が対立したときに誰が最終的に判断するかの取り決め
⑦借入金、負債の最終的な負担者及び負担割合
事業を始めるときはいかに成功するかということに意識が集中しがちですが、厳しい局面というのは必ず訪れます。上手くいかないときに誰がどうやって事業を支えるかがはっきりしていれば、お互いを信頼して仕事に取り組むことができ、いずれ事業を成功に導く力につながります。共同出資・共同経営に関する合意文書について専門家に相談されたい方は、ひまわりほっとダイヤルをご利用ください。
≪執筆者紹介≫ 弁護士 樽本 哲(第一東京弁護士会)
日本弁護士連合会ひまわり中小企業センター事務局次長
第3回 2017年6月号 契約書の作成時における留意事項
事業者のための法律相談 トップ
第1回 2017年4月号 中小企業・小規模事業者によくある法律問題は?




