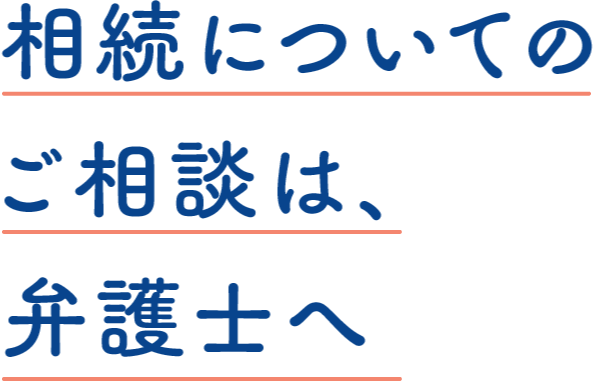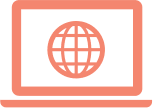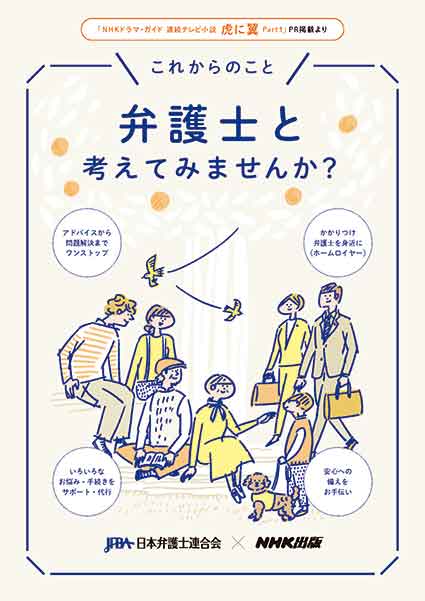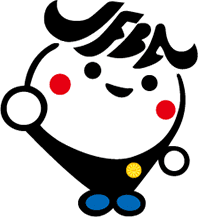「大した財産もないのに、
相続なんて大げさだ」
「弁護士に相談するのは、
トラブルや裁判になってから」
と思っていませんか。
でも、こんな話を聞きませんか?
-

亡くなった友人の子どもたちが、相続で揉めているみたい。
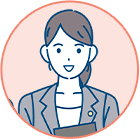
なるべく争いが起こらないような備えを考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、必要となる準備を全面的にサポートします。
-

先祖の空き家が放置されたままになっている。
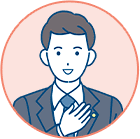
もし建物が崩れて通行人が怪我をしてしまったら、相続人の責任問題にもなりかねません。早めの対策を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、トラブルが起きた時はもちろん、それを未然に防ぐ方策もアドバイスします。
-

急に親が亡くなって、相続って言われて戸惑っています。
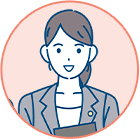
故人の供養だけでも大変なのに、相続ではやることがたくさんあります。一人で抱え込まず、専門家の活用を考えてみてはいかがでしょうか。弁護士は、すぐにやらないといけないこと、少し先でもよいことなどを整理しながら、相続全体を計画的にサポートします。
-

身寄りのない私の財産は、
どうなるのかしら。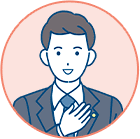
お世話になった方に財産を有効に使ってもらうことなども考えられます。弁護士は、遺言を始め、財産承継のために適切な手続のご提案から必要書類の作成まで、トータルでお手伝いします。
誰にとっても、相続はいつか
自分ごとになります。
相続で気になることは、お気軽に弁護士にご相談ください。
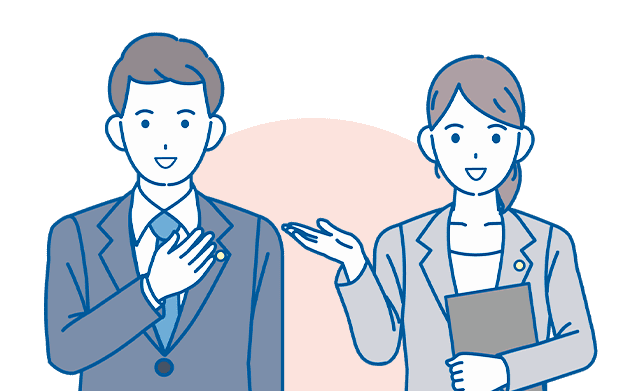
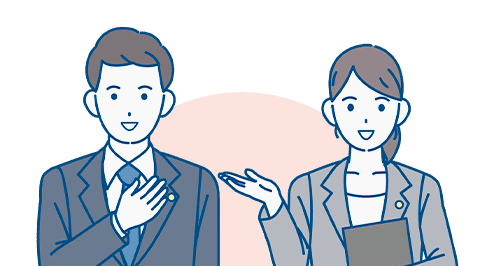
弁護士は、相続全般の
エキスパートです。
日々、紛争を解決している弁護士だからこそ、トラブルを未然に防ぐための最善策を提案することができます。
弁護士は、あなたに必要となる手続の全体像をご案内し、スムーズで適正な相続の実現に向け、あなたのアドバイザー、代理人として、ともに取り組みます。
弁護士へのご相談なら
全国の法律相談センターで、弁護士による法律相談を受けることができます。
電話またはネットでお近くの法律相談センターをお探しいただけます。
相談時間はおおむね30分、相談料は地域や相談内容により異なりますが、5500円前後です。
また、弁護士会によっては、専門の相談窓口を設置している場合があります。
詳しくはこちら
「遺言・相続」を取扱業務等として登録する弁護士を、ご自身で探すこともできます。
弁護士情報提供サービス
「ひまわりサーチ」
次のような疑問やお悩みも
弁護士がサポートします。
相続
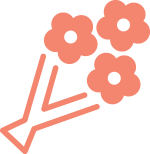
親や配偶者などの家族・親族(被相続人)が
亡くなると、相続が始まります。
- 家族や親族が亡くなったら、必ず相続手続が必要なの?
- 私が相続できる範囲はどれくらい?
- 不動産の名義を変えるには、どうしたらいいの?
- 亡くなった人が貸していたお金は、どうなるの?
- 先祖の名義のままの不動産は、このままで大丈夫?
遺産分割
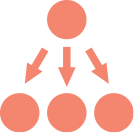
相続人が2人以上いるときは、
遺産をどう分けるかを決める必要があります。
- どのような分け方ができるの?
- 疎遠になっている相続人がいるときは、どうしたらいいの?
- 亡くなった人の世話をしていたから、財産を多くもらいたい。
- 亡くなった人から援助を受けていた相続人が、他の相続人と同じように財産を取得するのは 納得できない。
- 「遺産分割協議書」を作りたい。
遺言
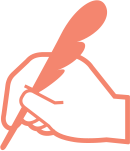
遺言があれば、それに従って
遺産を分けていくことになります。
- 「遺言書」と書かれた封筒は、相続人が開けていいの?
- 公正証書遺言は、普通の遺言と違うの?
- この遺言書って有効なの?
- 遺言書に書かれている内容と異なる分け方ってできるの?
- 遺言執行者って何をする人?
負債

相続をすると、被相続人の財産だけでなく、
負債も引き継ぐことになります。
- 亡くなった人の借金は、どうしたらいいの?
- 残っている財産だけ取得して、借金は返さないことってできるの?
- 亡くなった人の債権者を名乗る人から返済を求められた。
相続放棄
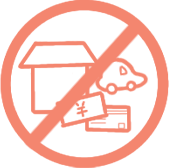
相続を望まないときは、
相続放棄の手続が必要となります。
- 相続放棄するには、どんな手続をとればいいの?
- 相続放棄って、いつでもできるの?
- 相続放棄すれば、空き家を放っておいて大丈夫?
「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 虎に翼 Part1」(NHK出版)とタイアップしたパンフレット
「NHKドラマ・ガイド 連続テレビ小説 虎に翼 Part1」(NHK出版)とタイアップしたパンフレットでは、ライフステージに応じた弁護士の活用例をご紹介しています。
チェックシート「これからのことを考えるために確認したい7項目」を使って、元気なうちにできる備えを進めましょう!
パンフレット(PDF)
新しいルールが、
スタートしています!
2023年(令和5年)4月1日から、
相続(遺産分割)に関するルールが
変わりました。

相続開始(被相続人が亡くなった)時から10年を経過してからの遺産分割では、相続する割合が変わります。原則として、亡くなった人から生前に贈与を受けたり、財産の増加に貢献したりしていても、そうした事情が相続に反映されなくなります。
このルールは、2023年(令和5年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
同日までに被相続人が亡くなっていて、被相続人が生前にした贈与や相続財産への自分の貢献などを踏まえた相続を希望するときは、早期に遺産分割手続を進める必要があります。
新しいルールの詳細や遺産分割への影響などを知りたい方も、弁護士にご相談ください。
2024年(令和6年)4月1日からは、
相続登記の申請の
義務化も始まりました。

相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に法務局に相続登記の申請をしなければならないことになります。また、この義務に違反したときには、罰則が科せられる可能性もあります。
このルールは、2024年(令和6年)3月31日以前に発生した相続にも適用されます。
相続登記を申請するにあたっては、遺言の有無・種類・内容の確認、相続人の調査、遺産分割協議など、ケースに応じた手続や準備が必要になります。
期限が迫って慌ててしまうことがないよう、お早めに弁護士にご相談ください。