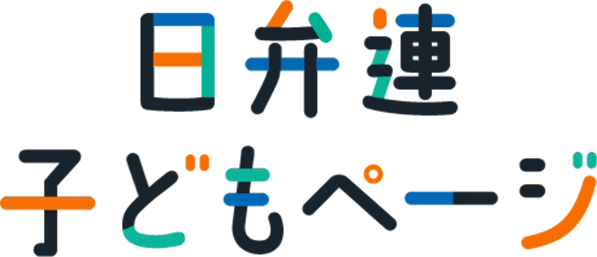
みなさんの生活を守る
弁護士の仕事や法律、
裁判について
わかりやすく説明します。







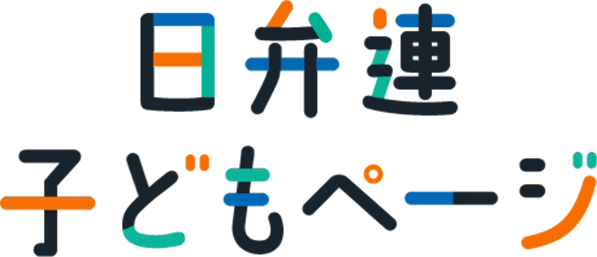
みなさんの生活を守る
弁護士の仕事や法律、
裁判について
わかりやすく説明します。






